魔性の女
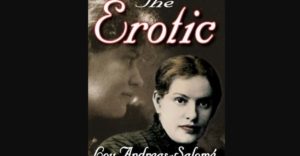
これは426回目。先日、カルメンのことを書きました。カルメンは小説の登場人物です。しかし、わたしは昔から、そのシルエットがどういうわけかカルメンとオーバラップする実在の女性がずっと気になっているのです。ルー・フォン・サロメ(今は、ルー・ザロメというのが普通らしいのですが)です。
:::
魔性の女とはサロメのことを言うのだろうと、昔から思っていた。
カルメンは性的魅力を振りまき、男の間を渡り歩いては、ことごとく不幸のどん底に陥れていく。
知性の片鱗も見られない。これに対してサロメは、知の塊だ。
しかし、知性が高いか低いかは、魔性とは関係ない。ただ知性の有無が、ときに関わる男の運命を大きく変えてしまうことはある。
サロメとかかわった男たちは、ことごとく(といってもいい)悩乱に陥り、熱愛し、求婚し、物の見事に振られる。(最後に結婚したアンドレアスを除いて)
そして、ある者はニーチェのように狂死し、ある者は自殺する。
ただ、その多くは彼のうちにある天才性を激発され、まさに歴史上に名を残す偉業を遺していった。
ニーチェは、サロメに翻弄された挙げ句、一週間で『ツァラトゥストラはかく語りき』を書き上げた。
1861年、サンクトペテルブルグ、ロシアの貴族階級(父は帝政ロシアの将軍)生まれのユダヤ人。ルー・フォン・サロメ(ルイーズ・フォン・ザロメ)は、欧州各地を転々し、ヨーロッパの知性を先々で開花させていく、一種の触媒のような効果をもった人生を送った。
カルメンと同じく、自由がすべてであった。だから、あらゆる求婚を拒絶した。(相手にそうした魅力を感じなかっただけかもしれないが)
先述のニーチェとドイツのやはり哲学者パウル・レーとの間で三角関係になる。結局レーがサロメを手に入れる。サロメ、21歳である。
しかし、「恋人の関係」にはならなかったとも言われる。3年後、スイスでレーは山歩きの最中に事故死している。一説には自殺とも言われる。
その後、ペルシャの歴史研究では著名なフリードリヒ・カール・アンドレアスに求婚される。サロメ、26歳だ。アンドレアスは、目の前でナイフを胸に突き刺すという荒業でサロメを説得して結婚に成功する。
ところが、その後、ドイツの詩人リルケ(22歳)がサロメに夢中になる。サロメ、36歳のときだ。リルケは二度にわたって、サロメが長いこと離れていた故郷ロシアを一緒に旅する。
そして、リルケを突き放す。そもそも、アンドレアスと夫婦だったはずではないか。夜アンドレアスが就寝するころに、サロメは出歩き、彼女の「仕事」をする。言わば、仮面夫婦を何十年にもわたって続けたのだ。
リルケはその後、病で短い生涯を閉じる。『僕のどこが悪かったのか、ルーに聞いて欲しい』と言いつつ事切れたのだ。
いったいこのサロメという女は何者なのだろうか? 以来、多くの人が、今や地下に眠るこの魔性の女に悩乱され続けてきた。
これは歴史上著名な人物だけをかいつまんで列挙しただけで、数々の有名無名の男たちが、サロメの魔性に狂っている。
『男を妊娠させる女』とも言われた。男は子供を産めないが、天才としての偉業を生み出させる。そういう意味での強烈な触媒にはなっている。ちょうど、サルバドール・ダリにとっての妻ガラのような存在だ。ダリもガラから絵画創作では決定的なインスピレーションを得ていた。しかし、ガラもサロメと同じくダリをほっぽりだし、何人もの男と浮名を流し、そのたびにダリを狂乱の淵に追い詰めた。
サロメは19世紀末から20世紀初頭におけるヨーロッパの知の尾根を、ただ次の風景が観たいだけに歩き続けただけなのか? それともたまたま、彼女に見合うパートナーに出会えなかっただけなのか。それとも、サロメこそ実在のカルメンなのか。わからない。
サロメは、著述家でもあり、後半生はフロイトのもとで精神科医を志す。さすがに年令が高じてきたからなのか、浮名は少なくなったものの、フロイトの下の学究生はサロメの魔性に狂い、自殺している。
一見、サロメは知の尾根を歩き続けた、といわれるだけに、知的な女性であるというイメージが強いが、彼女の「毒牙」にかかった男たちの状況を並べていくと、その狂乱ぶりから、知以上に性的な魅力というものを強烈に感じる。
サロメのフロイトへの手紙にこういう文面がある。
「これはセクシュアリティの主要な問題なのではないでしょうか。セクシュアリティは、渇望を癒やしたいというよりも、むしろ渇望自体を切望することから構成されているのですね? 身体的緊張の解放と満足に到った状態は、同時に失望ということですね? というのは、緊張と渇望が減ってしまうのですから。」
これは、フロイトが着目した深層心理の本源、性的欲求というものを、物の見事に覆す一節として知られる。
フロイトは、性的欲求が人間の情動の本源にあるとしたわけだが、それは快感への欲求という仮説だった。
ところが、サロメは快感ではないと言い放っているわけだ。欲望の満足を求めているのではなく、欲望自体を欲望している、それが人間なのではないかと指摘しているのだ。
これでフロイトがまた悩乱する。5年もかけて、彼の仮説であった「快原理」を修正しなければならなくなったのだ。
サロメは、これといって歴史に残るような著作を遺したわけではない。いろいろなものは書き残したのだが、残念ながら世界の思想や歴史を動かすインパクトの著述は無い。
いずれも、サロメという理解不能の女性を研究する上ではきわめて基調な著述が多いだけだ。
典拠元が不明だが、サロメは異常性欲者、あるいは性的倒錯者だったのではないかという見方がある。ある証言だが、老紳士のサロメに関する回想だ。かつてサロメに翻弄された無名の紳士の一人なのであろう。
『彼女の抱擁には、自然力のというのか原初的というか、何か恐ろしいものがあった。きらきら光る青い目でみつめながら、“精液をうけとることは私にとって恍惚の絶頂です”と言うのである。そしてそれを飽くことを知らず求めた・・・愛しているときの彼女は、まったく無情だった・・・彼女はまさに不道徳であって敬虔であり、吸血鬼と子供とが同居している。彼女を愛したいという男たちに関するかぎり、彼女は自分の本能しか信じなかった・・・』
最終的にサロメがフロイトにたどり着き、そこで真正面から人間の心理と性の関係にのめり込んでいったことと、この老紳士の回想は不思議に符号する。
かつて、ハイネがこんなことを書き残している。
・・・愛とは何か、とお前はたずねる。たちこめる霧に包まれたひとつの星だ。・・・悪魔であるのか、天使であるのか、それは知らない。女にあってはどこで天使が始まり、どこで悪魔が始まるのかもわからない。・・・恋に狂うと言うが、言葉の重複だ。恋とはすでに狂気なのだ。・・・
それはサロメのような女のことなのかもしれない。男を狂死させ、あるいは男を天才に昇華させて世に送り出し、ナチスがその軍靴の響きを轟かし始めた頃、1937年、尿毒症で死んだ。
住居の名にちなんで、『ハインベルグの魔女』と呼ばれた女のその魔性は、永遠に謎という霧の中に埋もれたままだ。
魔女は、幸福だったのか、そうではなかったのか。それも謎のままだ。


























