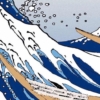実用と美~実用に耐えぬものは、美しくない

これは41回目。美とは何でしょう? 私たち日本人は、ときとしてなんでも美で解釈して事足りているような悪いクセがあるかもしれません。そんなお話。
:::
近年なんでも「癒し」である。この言葉もわたしは嫌いなのだ。なんでも「癒し」のために、材料に供されてしまう。音楽や、マッサージなら、そのものだから良い。犬や猫などのペットも、迷惑だろう。向こうはわたしたちを癒しているつもりなど、さらさらない。人間が勝手に「癒し」を求めて、「愛玩」しているにすぎない。向こうは、徹頭徹尾、生きるのに必死だ。
観光や物見遊山もいいだろう。だが、歴史的文化財、とくに寺社や城などになってくると、わたしなどは抵抗を感じてしまう。
美しいという言葉は、とても曖昧に使われる。実用の美と芸術の美が一緒くたになっているということだ。芸術といったら、ちょっといささか格好つけすぎかもしれない。「見かけの美しさ」とでも言ったほうが正しい。
たとえば、百歩譲って城とか民家など、古い文化財を観覧するという際に問題がでてくる。とりわけ、寺や神社の場合は、いわゆる物見遊山では困るのだ。
いいじゃないか、そう堅いことをいわなくても、というわけにはいかない。本人のためにも良くない。正しい美意識が育たないのだ。見かけの「閑静なたたずまい」はそれ自体、心地よく鑑賞して構わないのだが、それで終わってもらっては困るのだ。寺社までわざわざ足を運んだ意味がない。
先日亡くなった生態・民族学者・梅棹忠夫が、「文明の生態史観」の中で、こうのべている。
・・・これは寺である。寺は宗教にかかわるものであって、芸術作品ではない。われわれは宗教的体験の場としての寺を、美的標準からのみ評価するというあやまちをおかしている。・・・わたしたち日本人は、なんでもかんでも美の尺度ではかろうとしているのではないだろうか。・・・
この梅棹忠夫の懸念は、実用(寺の場合は、祈りという宗教的な場である)としての寺の美しさを観取することもできず、曖昧な美的感覚に漂うだけで、ロジックというものの発達も損なわれる。
現代、「癒し」という言葉の氾濫に見られるように、すべては自分の快感のための材料を求めているだけであり、それ自体の実用的な美というものへの知的好奇心は皆無な精神風土が蔓延しているのだ。
寺のような文化財の観光名所だけではない。骨董品もそうだが、皿や碗、壷などの小物にも言える。奇しくも、梅棹と同じことを言っている巨匠がいる。
柳宗悦は、その「民芸四十年」の中でこう書いている。
・・・偉大な古作品は、一つとして鑑賞品ではなく、実用品であったということを胸に銘記する必要がある。いたずらに器の美のために作るなら、用にも堪えず、美にも耐えぬ。・・・
そうなのだ。優れて実用的なものは、まず間違いなく美しい。しかし、美しいものが必ずしも実用に耐えるとは限らない。そして、それが果たして本当の意味で美しいかすら、疑問だ。
ついついわたしたち日本人は、美しいかどうかで感覚も思考も止まってしまい、それが正しいのか、間違っているのかとかにまで思考が進まない嫌いがある。美しいことで、免罪符にしてしまっている癖があるようだ。
熊野古道のようなものが世界文化遺産に登録となったことは良いことなのだが、しかしそもそもが観光地ではない。本来の姿、かつてそこにあったもののほうが、遥かにわたしたちには財産なのだ。
熊野古道は登山やハイキングコースではない。大峯奥駆け(おおみねおくがけ)という、修験者たちがそれこそ1000年にわたって登攀し続けてきた霊場にほかならない。多くの行者が命を落とした場所なのだ。深山のヒーリングや、都会の喧騒から逃れた「癒し」の場ではないのだ。
熊野古道の世界遺産としての価値や意義は、風光明媚な自然などではない、と思っている。命を懸けた「大峯七十五靡(おおみねななじゅうごなびき)」という、修行の場だったことだ。
祈りとはなにか、行(修行のこと)とは何か、ということを考えずに、寺も神社もくそもない。信仰の有無や宗派の別は、まったくここでは問わない。だから、古刹(こさつ)を観光巡りをして、古色蒼然とした風情に美しいと思うことは構わないのだが、その寺ができたときには、黄金と原色に満ちていたのだ。その事実と、ただ、古くなった風情との整合性をどうつけるつもりだろうか。
もっとわかりやすく書こう。あなたが今見ている寺は、観光スポットと化し、葬式宗教に堕したただの、言わば宗教的には死んだ寺である。あなたが想像もしたことがないような絢爛豪華な色彩で埋め尽くされていた、創建当時のその寺の、強い使命感や情熱と深い信仰に満ち満ちていた当時の寺の風情ではないのだ。
いま、わたしたちが美しいと思う枯山水のような「出がらし」の寺の風情がその寺の真実なら、1000年前のこの世に生まれたばかりの、溌剌とした文化の発信地としての燦然と輝く色彩感覚の寺も真実なのである。
金箔が剥げ、絢爛豪華な色彩も褪せて、枯れた侘(わ)び寂(さ)びの風情も、その永遠に受け継がれてきた気の遠くなるような迫力に美しさがあるのだ。両者の気の遠くなるような時間の経過の中に、歴史の移り変わりがあり、それでも絶やさず点(とも)され続けてきた「千年の法灯」の感動があるのだ。