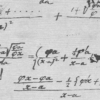ねがわくは・・・旅はいつもそれ自体が答えであった。

これは69回目。俳句のことは書いたことがありますが、まだ、短歌(和歌)のことは、書いていませんでした。俳句に比べて、歌は字数が多いこともあって、なんとなくわかりやすい。そんな気がするだけなのですが・・・
:::
だいたい、詩集とか、歌集とか(漢詩も含めて)、韻文(いんぶん)というのは、一冊買っても、気に入った作品は、一つか二つであることが多い。わたしだけだろうか。軒並みこれはいいなあ、と思える作品で満ちていた、などということがほとんどないのだ。
しかし、基本的には好みではない歌読みの作品でも、たった一つ、極端に好きなものがあったりもする。不思議だ。
たとえば、明治以降、近代の歌で言えば、与謝野晶子や石川啄木といった歌人の作品というのは、そもそも自意識過剰とも、逆に自虐的(かつ反社会的)ともいった印象が強く、どうにも好きになれないのだが、それでも、わずかばかり、その素直な青春の謳歌(懐旧)といったものには、同調できる作品がある。
「みだれ髪」に収められている、有名な代表作の一つがある。
その子二十(はたち)櫛(くし)にながるる黒髪のおごりの春のうつくしきかな
(与謝野晶子)
これは自分のことを謳っている。これが、他人のことを歌ったのであれば、ただそれだけの佳作として残っただろう。しかし、本人のことなのだ。だから、自意識過剰という。しかし、それであればこそ、この歌はロマン主義の傑作として未だに燦然と輝きを放っているのだろう。
蛇足とは言え、解説してみれば、「私は、今年で20歳。あなたが美しいとほめてくれた髪をとかせば、櫛に流れるような豊かで美しい黒髪が若々しい香で、今が春と輝いています。今夜も女の悦びを教えてくれたあなたを思い、切ない気持ちです。」といったような意味になる。
そんな、青春期の恋愛至上主義的な発露が、周囲に炸裂するような歌だ。日本浪漫派の金字塔を打ち立てた与謝野晶子の面目躍如たる作品だろう。これなどは、けっこう好きなのだが、これだけなのだ。あとはもう、正直言って食傷気味になってしまう。おなか一杯、胸やけがする。
強いていえば、こんなのは素直に読めて、心安らかだ。
海恋し潮(しお)の遠鳴りかぞへては少女となりし父母の家
これなどは、与謝野晶子特有の自意識過剰の癖(へき)がかなり後ろに引っ込んでいて、同調しやすい。
啄木などは、もう社会や自分の運命に対する、うらみつらみねたみそねみの集積回路のような作品ばかりであるから、逆立ちした自意識過剰といっていい。与謝野晶子より、もっと手ごわいのだ。それでも、わずかに次のようなものは、「海恋し」に近い感情移入ができるもので、わたしは好きだ。
不来方(こずかた)のお城の草に寝ころびて空に吸はれし十五の心
(石川啄木、「一握の砂」より)
文字通りだろう。ちなみに、不来方の城とは、もちろん盛岡城址のことである。
与謝野晶子にしろ、石川啄木にしろ、膨大な歌を詠んでいるにもかかわらず、わたしが好みを覚えるのは、ほんのわずかだ。正直、5本の指でも数えられるていどでしかない。それだけ、わたしの感性が鈍いのか、芸術性が無いということなのか。好みだと言ってしまえば、それまでだが。
これは、万葉集だろうと、その他の個人的な歌集だろうと同じなのだ。なかなか、一冊に収められている作品が、どれもこれも気に入るということが、まず無い。一つあれば、十分すぎるではないか、と理屈ではわかっているが、ほかを読むと、もううんざりしてくる自分がいる。恥ずかしい話、買って損したなどと思ってしまうケチな自分が嫌になる。
ところが、(これも好みと言えば、それでいっぺんに話は終わってしまうのだが)実は、一冊を手に取って、のきなみ感情移入ができるような作品が、ぞろぞろ出てくるという歌集がある。西行(さいぎょう、佐藤義清・さとう のりきよ。憲清、則清、範清とも。)の「山家集」だ。
どういうわけだか、波長が合うというのであろうか。非常に、気に入る「あたり」が多いのだ。この西行は、平安末期から、鎌倉時代にかけてのもともとは武士である。僧になり、歌人になった。
藤原秀郷9世の孫にあたる。18歳で、左兵衛尉に任ぜられ、鳥羽院の北面武士として奉仕していたことも記録にあるから、武士の血統としては、申し分ない。はずだったが、なぜか23歳のとき、突如として出家し、心赴くまま、諸国放浪、草庵をいとなんだ。
当初は、鞍馬山など京都北麓に隠棲し、後奥羽地方、さらに高野山に入っている。さらにその後は、中四国に旅立ち、いったん高野山へ戻る。伊勢のあと、二度目の奥羽地方への旅立ちをしており、途次に鎌倉で源頼朝に面会している。
武士であっただけに、頼朝から「弓馬の事」をたずねられたらしいが、「とうに忘れてしまいました」とトボケたそうだ。
武士を辞めたのが、親友の死が関係している説や、失恋説などあるが、よくわからない。4歳のわが子が泣くのを、蹴落として家を出奔した、というが、一体なにがあったのだろうか。
その歌風は、非常にわかりやすく素直な、平俗的な内容にもかかわらず、同時にすこぶる気品が高く、閑寂にして艶がある。旅、仏道、歌という三点セットは、この西行という価値の不可欠な要素だ。芭蕉に影響を与えたことも知られているが、芭蕉も西行の歌だけを切り取ったわけではない。西行の全人的な存在こそが、影響を与えたのだ。
なにより、この西行の魅力は、その人間的な「未熟さ」だ。各地に残る西行の事跡と呼ばれるもの、あるいは逸話というものは、ほとんどが彼の「みっともない所業」ばかりだ。それがまた、親近感を持たせる。
日本人の宗教観を表す一例によくつかわれるのが、西行が伊勢神宮参拝の折に詠んだこの歌だろう。
何事のおわしますをば知らねどもかたじけなさに涙こぼるる
仏教も神道も、民間俗信も、なにもかもごった煮状態の日本人の、独特の宗教観は、この歌一つに見事に表されている。理屈はどうあれ、とにかく頭(こうべ)が下がり、かしこまってしまう日本人の心もちだ。
西行の最も有名な歌がある。
ねがはくは花の下にて春しなんそのきさらぎの望月(もちづき)のころ
花、月といった美しいものの象徴と、覚りを得た釈迦の入滅した日の憧れをあらわしたものとされている。
この如月(きさらぎ)とは、旧暦の2月。望月とは満月のことだ。現在の太陽暦では3月下旬から4月上旬ころになる。西行は、文治6年(異説あり)、1190年、2月16日(この日が満月らしい)に大阪府の南河内町の弘川寺で亡くなったが、先年詠んだ上記の歌の通りだったので、当時の人々は驚いたようだ。
気負いも何もない漂泊の人生というものに、どうにも憧れてしまう。わたしも「未熟」だからだろう。そして、旅というものは、問いかけなのだが、旅自体が答えであるとも言える。