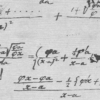霊性の震災学

これは221回目。怪談というものを、もっとまじめに考えても良い時代になってきていると思います。震災などの直後、怪談を語るというのは、どうしても不謹慎のそしりを被りかねません。被災遺族の立場にたてば、痛みをより深くし、怒りすら覚えるかもしれないからです。しかし・・・
:::
時が経ち、災害にかかわる怪談が、ちらほらと地元で語られ始める頃は、ようやくその災害や事件、事故といったものが、社会的に落ち着き、遺族関係者たちの心の整理もついたということを意味する。少なくとも、社会学的にはそう分析することが可能だ。
人の死というものが、たくさんあったような、不条理な状況であったにもかかわらず、何年経っても、怪談の一つも出てこないということは、それだけその事象のことを、人々はほとんど気にもかけておらず、何とも思っていないということにほかならない。
だからというのも、(こじつけに聞こえるかもしれないが)怪談というのは、やはり文明や文化のバロメーターなのだ。
阪神淡路大震災の悲劇の後、しばらくは怪談の「カ」の字もなかったが、10年位経過したあたりから、日本各地で「実はあのとき・・・」と、ちらほらと震災にまつわる怪談が語られ始めた。
東日本大震災の場合は、もっと早かった。4年で、驚くべきことにNHKで特番が組まれ、被災遺族たちと、故人の幽霊との邂逅を取り上げた実例が、紹介された。
もちろん、幽霊の存在の有無を巡る議論ではないのだ。それが科学的にどうかということではなく、遺族たちにとって、心の整理をつけるきっかけが、霊との再会であったということなのだ。
話は飛ぶが、昔、「異人たちとの夏」という映画があった。原作は、1987年に発表された山田太一の小説である。映画は、風間杜夫、片岡鶴太郎、秋吉久美子といった俳優陣が演じたものだ。
主人公の子供の頃、とうに亡くなった両親との、ふとした再会から始まる。居住するマンションにおける怪談という別の伏線も絡み合いながら、なかなか心に染み入ってくる。
たった一人で生きてきた傲岸不遜・傍若無人な主人公が、両親の幽霊と出会う。それからというもの、毎日、両親の元を訪れ、たわいのない、失われた昔日の親子水入らずの日常が繰り返されるようになる。
主人公は、すっかり記憶の外に追いやっていた家庭の暖かさにしみじみと感じ入り、なにか大事なものを取り戻し始めていく。浅草・今半における最後の晩餐のシーン。思い残すことがなくなった両親たち。その影が、夕闇迫る中で次第に消えていく。感動すら覚える一場面である。
ここでも、やはり親しい者の死というものを、生き残ったものがどこで「折り合い」をつけるか、という点がテーマなのだ。
ここに、東日本大震災にまつわる一つの怪談がある。震災から3ヶ月ほど経った、ある深夜のことだ。タクシー運転手の男性が、石巻駅の近くで客待ちをしていると、初夏だというのに、真冬のようなコートを着た30代くらいの女性が乗車した。
「南浜まで」と一言。そこは、津波で、壊滅的な被害を受けた地区だ。運転手は不審に思って「あそこはもうほとんど更地(さらち)ですけど、構いませんか?」と聞いた。
すると、女性は震える声で答えた。「わたしは死んだのですか?」運転手が慌てて後部座席を確認すると、そこには誰も座っていなかった。
実はこれは、怪談にして怪談ではない。1月末に発売された、「呼び覚まされる霊性の震災学」(新曜社)に収録された東北の女子大生の卒論に書いてある内容だ。
彼女は、執筆にあたり、震災の死者数が約3500人と最多となった宮城県石巻市の人々に「幽霊を見た経験がないか?」と聞いて回る実地調査をした。卒論という限られた時間の中で、まとめなければならないから、日本の震災史上、類例をみないほど広域にわたる大震災であったので、彼女は石巻一箇所に絞ったのだ。
こういう聞き込み調査のことを、フィールドワークという。彼女としても、フィールドワークを一度もしたことがなかったので、直球で聞いて歩いてしまったようだ。当然、スルーされたり、茶化されたり、ときには「不謹慎だ」と怒鳴られたりとさんざんだったようだ。
身内に震災で亡くなった人がいた場合に、そんなことをいきなり直球で尋ねられて、平気でいられるとおもうか、とそういうことである。
こういうタッチーな話を聞き込むときには、まず相手の懐に入るしかない。そういうワザを彼女は知らなかったから、大変苦労したようだ。
雑談などをし、石巻に長期で遊びに来たということにでもし、「暇だねえ」などとからかわれながら、だんだんと核心に迫っていく以外にないのだ。
フィールドワークというのは、実にそういう意味では、時間が必要だ。人間関係をつくることのほうが先決だからだ。そこから、やがて、ぽろぽろと相手が自分の口から語りだすものだ。
そうして苦労して得た怪談は、300-400人に尋ね歩いてようやく多少なりとも、集まってきた。そのうち、タクシー運転手は100人ほどという。幽霊の目撃者が、「確信を持って言える」と断言したのは、そのタクシー運転手100人のうちわずか4人だけだったという。
300-400人というとかなりのユニバースである。その苦労の割には、「収穫」が少ない。もっともこの女学生は、「みんな話をしたがらないだけで体験している人はもっと多いと思うよ」と言われることもあったようだから、なかなか本当のことは語られないのかもしれない。
彼女が最も衝撃を受けた怪談は、次のようなものだったという。
「巡回してたら、真冬の格好の女の子を見つけてね」。その運転手は、13年の8月の深夜、タクシー回送中に手を挙げている人を発見し、タクシーを歩道につけた。すると、小さな小学生くらいの女の子が季節外れのコート、帽子、マフラー、ブーツなどを着て立っていた。
時間も深夜だったので、とても不審に思い、「お嬢さん、お母さんとお父さんは?」と尋ねると「ひとりぼっちなの」と女の子は返答をしてきた。迷子なのだと思い、家まで送ってあげようと家の場所を尋ねると、答えてきたのでその付近まで乗せていくと、「おじちゃんありがとう」と言ってタクシーを降りたと思ったら、その瞬間に姿を消した。
確かに会話をし、女の子が降りるときも手を取ってあげて、実際に触れたのに、突如消えるようにスーっと姿を消した。
タクシー運転手の4件の証言には、ある共通項がある。それは幽霊のように感じた人物がいずれも「季節外れの冬服」を着ていたものだ。
タクシー運転手は、いずれも地元の居住者だ。したがって、震災の悲劇を目の当たりにしてきた経緯がある。土地にも通じている。津波による死者が圧倒的であろうから、地震発生から死亡まで、時間差があった。彼らはそのことをよく知っている。
だから、「あのとき逃げる時間はあった。」「もしかしたら助けられたのではないか」という、自身に置き換えて、後悔の念が強く深層心理に働いている可能性は高い。それだけに、偶然、若干でも季節外れの服を着ている乗客を目にしたときに、いわば幻覚、幻想を見たのではないか。ある種の脳内変換をしてしまったのではないか、とそういう意見もある。
タクシー運転手の4件の証言のうち2件は、乗客が目的地に指定したのが、甚大な被害があった石巻市南浜地区だった。いずれも、乗客は目的地に到着する前に姿を消している。まるで亡くなった被災者が、それぞれ思い描いていたであろう未来にたどり着けなかったことを暗示しているかのようだ。
ここでは、震災にまつわる怪談を書いているわけだが、なにも悲劇は震災にとどまらず、戦争や事故のようなものも同じである。
不思議なことに、昔に比べて、鎧武者(よろいむしゃ)の亡霊といった話、生首が飛ぶといったような怪談を近年はあまり聞かなくなった。時代によって、古い霊というものは、浄化されるか、異質なものに変化してしまうのであろうか。
ある高齢の女性がいたのだが(現在はもう故人である)、長崎出身。本人も被爆しているが、長命を保った。彼女が生前、長崎恒例の8月15日夕刻から行われる精霊流しについて、語ったことを覚えている。
昔から、この精霊流しを見てきた人物で、戦後ももちろんである。ある年の精霊流しでは、ふとこんなことをつぶやいた。「ずいぶん、人が減ったねえ。」周囲にいた誰しもが、それは精霊流しに参加している人や、旅行客・見物人のことを言っているのかと思ったが、そうではなかった。
彼女曰く、昔(といっても戦後しばらくのことだが)「黒い人たち」がそれはあたりを埋め尽くすほどいっぱい集まっていたが、今年はずいぶん少なくなった、とそういう意味だったのである。ふだん、幽霊とか怪談の話をまずしないような婦人だったので、みなびっくりした。
時代が下るにつれて、異界の人たちも往くべきところへ往くということなのかもしれない。
直近、元ハーバード大学の脳神経外科医を務めたエベン・アレキサンダー3世(ドクター)が、「Proof of Heaven(天国の証明)」という本を著した。NYタイムズのレポートでも取り上げられ、ドクター自身が体験した死後の世界が詳細に書かれているベストセラーだ。
ドクターは、2008年に細菌性の脳髄膜炎に冒され、昏睡状態になるまで悪化した。絶望的と思われた7日間の昏睡状態から奇跡的に蘇生したドクターは、奇妙な体験をしたこをと語り、それを本にしたのである。
詳細は、興味があれば、原本を読んでいただくとして、要するに、あちらでは言葉が無く、すべてはテレパシーでコミュニケーションがとれ、さまざまな光を放つ球体(オーブイ)に満たされた巨大な空間で、愛が満ち溢れているという。
こういう要約をすると、よく聞くような「蘇り」の話と大して変わらない。昏睡中に脳内で再生されたイメージを語っているものだということを普通は言われるだろう。ドクターが、そこで行った普通と違う点は、まさにそこから科学的に立証している点だ。
どういうことかというと、ドクターは、自分が昏睡状態に陥っていた(いわゆる臨死ないしは仮死状態になっていた)間、さまざまな医療データから、脳が昏睡中にまったく機能していなかったことを証明し発表しているのである。
機能していない脳ということは、幻覚などを含め、何かが脳内で処理されていた事実は無い、ということである。従って、ドクターが体験した「天国」というものは、脳内で勝手につくりあげられたイメージではなく、実際にドクターが体験した事実そのものだということになる。
戦争や、事故、震災のような天変地異によって、不条理な死を遂げた人たちは、そもそも自身の肉体が失われたことにも気づかないという場合も多いと聞く。「迷う」というのは、そのことを指すとも言われるが、それも年月が経つにつれ、次第に減っていく。
仏教では五十回忌が、一般的には弔い上げの最後である。遺族もほとんど存命していない場合も多かったことから、五十回でいわば「打ち止め」という慣習になっていったのだろうと推察されるが、もしかすると、五十年(正確には仏教的には死後49年後だが)というざっくりとした数字には、意味があるのかもしれない。それは、四十九日に意味があるのと同じように。
阪神淡路大震災から24年。東日本大震災から8年。あと4年で関東大震災からちょうど100年に当たる。昔は、ずいぶん関東大震災にまつわる怪談というものがあちこちで聞かれたものだ。
わたしの出身地・横浜でも、とくに有名だったのは、横浜正金(現在、神奈川県立歴史博物館)の怪談がある。震災時、横浜も焦土と化したが、運よく正金の地下金庫に逃げ込んだ人たちは助かった。正金にたどり着くのが遅かった人たちは、分厚い鉄の門扉を閉じられた後だったために、正金前には140柱もの焼けた犠牲者の遺体が重なり合っていたという、有名な逸話である。
以来、現在県立歴史博物館になっている旧横浜正金本館( 1904年、日露戦争開戦の年に建造)では、昔から幽霊の話で持ちきりだった。しかし、それも、近年ではまったく聞かれなくなってきたような気がするが、どうだろうか。わたしも、出身地の横浜から離れてずいぶん経つので、聞く機会が無いだけかもしれない。
まつわる怪談を聞かなくなるということは、誰もかつてそこで起こった悲劇を、何とも思わなくなっている、気にもしない、知っている人もいなくなった、ということだ、といったようなことを冒頭で書いた。怪談は、基本的に民度を測る重要なバロメーターだとわたしは思っている。