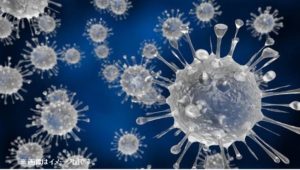アマゾンが震える~新たな時代の胎動

これは282回目。かつて、ミルトン・フリードマンが、規制のない自由主義経済の設計を目指しました。基本的には、通貨制度や経済政策の範疇で市場原理市場主義を打ち出したのですが、ときに麻薬の解禁にまで言及していました。
:::
さらに分野を拡大して、経済学のみならず、政治哲学、法哲学、心理学にまでわたる主張として、完全自由主義を唱えたのが、フリードリヒ・ハイエクである。彼は、中央銀行すら不要と断じている。
いずれもノーベル経済学賞受賞者だ。この人脈はオーストリア学派(ウィーン学派)と呼ばれるが、ナチスの迫害を避けて、多くはアメリカに移り、現在ではこの流派の本拠地はアメリカだ。
そしてアメリカで、この流れを一段と強めた主張にしたのが、経済学者のマレー・ロスバードだ。俗に、彼とその流派を、リバタリアン(自由至上主義、完全市場主義)と呼んでいる。循環論を唱えた有名なシュンペーターもこの学派出身である。
従来の伝統的な経済学、たとえば、古典派経済学やマルクス主義は、商品の価格が供給する側(企業)の労働投入量のみによって決定されるという「労働価値説」を前提にしていた。平たく言えば、労働とその生み出す価値こそが、経済のすべての現象を決定づけるというイデオロギーだ。
ところが、ウィーン学派はそうではない。商品の需要側(家計、消費者)の限界効用と、供給側(企業)の限界費用の相互関係によって商品価格が決定されるという前提にたっている。これが「効用価値説」である。消費に重点を置いているのである。労働をいくらしたところで、消費されなければ無価値だからだ。
今、その「効用」には限界が無く、それこそ無限に多様化と膨張をしようとしている。新たな需要が幾何級数的に創造されつつあるのだ。それを可能にしているのが、インターネットの普及である。
伝統的な小売り業態に、破壊的な地殻変動を起こしたアマゾンですら、この流れの中では、ただの一里塚でしかない。実際、アマゾンは、中身が空っぽの企業である。ただ、インターネットという未曽有の効率システムを活用することで、既存の小売業界のシェアを奪っただけにすぎない。
そのアマゾンが震撼しているのは、D2Cの台頭である。「ダイレクト・トゥー・コンシューマー」だ。アマゾンは、しょせん既成の商品をインターネットの活用によって経済合理性を極限にまで追及し、根こそぎ個々の企業体の収益を収奪しているにすぎない。
新たな創造は個人事業や中小企業など、ベンチャー精神溢れる最小単位から生まれる。それらは従来、大企業によって蹂躙される対象でしかなく、運が良ければ大企業によってくみ取られ、吸い取られ、利用される運命に甘んじていた。
ところが、インターネットの普及は、これらが合従連衡することで、開発、生産、販売、物流すべて、相互に得意分野を補完し合い、無限に多様化する需要に瞬時に応えようとする社会変革が進行している。これが、D2Cだ。
アメリカのネット消費市場において、アマゾンはそのシェア37.7%と断トツだが(伝統的な店舗型小売りの巨人ウォルマートはわずか4.7%だが、猛烈な追い上げをしている)、そのアマゾンが震撼しているのは、なんと47.7%を占めるD2Cという恐るべき個々の集団の連合体である。
おしきせのアパレルやブランド価値というものに踊らず、あきたらない20-30代の、いわゆるミレニアム世代というのは、最大公約数の需要に効率的に答えようとするアマゾン的小売りに満足しない。アマゾンに満足するのは、中高年層以上である。昔に比べれば、格段に便利になったというだけのことで満足する世代なのだ。しかし、若年層はそうではない。自分に合ったものはなにか、にあくなき関心と希求があるのだ。多様化し、細分化をとめどもなく続ける個々の需要・消費というものに、十把一絡げのアマゾン・システムは、答えることができていないのである。
事は、単にこうした消費・小売りにとどまらない。インターネットという化け物は、経済学という範疇を飛び越えて、政治、社会、あらゆる生活共同体に激震を巻き起こしている。その急先鋒が、冒頭で述べたオーストリア学派(ウィーン学派)に始まる、リバタリアン(自由至上主義)の台頭である。
このリバタリアンは、いわゆるリベラル(リベラリズム)とはまったく違う。リベラリズムというものは、自由を重視しているものの、それが実現するために「社会的公正」というものを掲げる。たとえば、リベラリズムは、貧困者や弱者を救済するため、富の再分配や法規制など、政府による一般社会への介入を肯定するのである。それにより実質的な「平等」を確保しようとする。
しかし、リバタリアンは、「平等」という概念を忌避する。平等は、自由の圧殺にほかならないと断じるのだ。たとえば、「徴税」に反対する。この徴税によって富を再分配する行為は、公権力による強制的な財産の没収であると説くのだ。リバタリアンにとって最大にして唯一の価値とは、あらゆる意味での私有財産の自由である。
だから、億万長者のビル・ゲイツやマイケル・ジョーダンから税金をたくさん奪い、彼らが自身の努力によって正当に得た報酬を、人々に「勝手に」分配することは、それがたとえ用途が道義的に正しいものであったとしても、権利の侵害以外の何物でもない、と考えるのである。こうした「慈善行為」は彼ら自身の意志によって行われなければならない、とする。貧困者や弱者への救済は、あくまでも国家の強制ではなく、自発的な仕組みによって行われるべきだと主張するのだ。
リバタリアンによれば、社会主義者や左翼思想というものは、個人的自由は高いが経済的自由度が低いという。そして保守主義や右翼思想は、個人的自由は低いが、経済的自由は高いという。どちらも、帯に短したすきに長しで、用をなさない、というわけだ。
共産主義、そしておしなべて前近代的な独裁主義・ファシズムなど、ほとんど論外である。これらは「全体主義」そのものであって、究極の敵である。
このリバタリアンは、これら「全体主義」とは対極に位置しており、ほぼ「無政府主義」に近いといっていい。だから、リベラルからは「弱肉強食」の強欲資本主義だと非難され、保守からは伝統的価値や社会の安定を軽視していると非難される。
暴力や詐欺、侵害など他者の自由を阻害する行為は、その自由を守るために、強制力の行使には反対していない。志願制は良いが、徴兵制は否定である。
現在このリバタリアンの頂点に立っている旗手が、先述のようにアメリカのマレー・ロスバードである。彼は、国家というものは「組織化された大規模な収奪組織」で、あらゆる社会の中でもっとも非道徳的で、貪欲で破廉恥な人間の生息地であるとみなした。
独占的な政府が供給するすべてのサービスは、民間部門によってより効果的に供給できると結論づけている。そして表面上「公共の利益」を表明する規制や法律の多くは、政府の官僚システムによる自己利益のための権力獲得にほかならないとする。
徴税などは、その最たるもので、大規模で強制的な「泥棒」だと断定している。そして、国家が独占する不換紙幣システムにおける中央銀行や連邦準備制度(連銀)は、合法化された財政的恐怖(テロ)であり、リバタリアニズムの原則や倫理とは正反対のものだ、としている。ロスバードは、自身をアナーキストであるとしており、「無政府資本主義者」だと述べている。
このイデオロギーには、賛否両論いろいろあるだろう。しかし、現実にインターネットという革命は、あらゆる既成の価値観、体制、社会構造を、根本的に破壊し始めている。赤い国境線すらほとんどインターネットの前では、用をなさなくなってきているのだ。
好むと好まざるとにかかわらず、わたしたちはこのリバタリアンの台頭にどう向き合っていくべきなのか、真面目に考えなければいけないようだ。