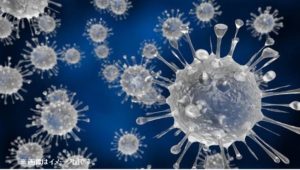思えば遠くへ・・・

これは354回目。
昔から、ボランティア(義勇兵)はどこでもあった。日本人の場合は、非常にその数は少ないと思うが、それでもあるにはあった。
つとに有名になったのは、ジャック白井だろう。実は、本名もはっきりしない。日本語もおかしかったというので、一説には朝鮮半島出身者であったいう説もある。しかし、1900年頃に函館に生まれたらしい、ということなので、1910年の日韓併合前である。従って、この線は薄いような気がする。
孤児院で育てられたので、当時のことだけに、なかなかまともな教育が受けられなかったかもしれない。青年期までの足どりについてはほぼ、わからない。
15歳頃に年齢を偽って船員になったとされている。炊事係だ。カムチャッカ行路の外国籍貨物船に乗船していたようだ。そして確実なのは、1929年の夏に、ニューヨークに上陸したということだ。それも脱船、つまり不法入国である。そして日本料理店で働き始めた。
そんなアメリカの生活で知ったのが共産主義だ。当時はアメリカの共産党もそれなりの勢力を保っていた。ジャック白井は、「日本人労働者クラブ」に入り、労働運動と反戦運動を行っていた。
ただ、白井はこの中では目立たなかったらしい。むしろその後に結成された「食糧労働者組合」で、多少活躍することになったようだ。
こちらにはスペイン系の移民が多かったのである。いつの頃から、ジャック白井と呼ばれるようになる。日本人の中よりも雑多な移民の中の方が気が楽だとことだったかもしれない。時代も時代である。出生からして、不運を背負った青年だ。日本を捨てて、人生の突破口を探し、必死にもがき続けたに違いない。
ジャック白井は、やがてバンガードという共産党の前衛組織に移る。これは実力行動を目的とした団体だ。デモに出て警官隊と衝突するのが任務だ。
そこに、スペイン内戦が勃発する。フランコ将軍のファシスト反乱軍が、勢力を拡大していく過程で、共和国側は劣勢に陥った。スペイン内戦は、けして教科書で言われているような、自由・民主主義とファシズムの戦いといったような単純な綺麗ごとなどではない。が、ここではその詳細は割愛しておく。
退勢著しいスペイン人民戦線は、義勇軍募集を始めた。有名な「国際旅団」である。白井は、これに応募した。米国の文豪ヘミングウェー、フランスのアンドレ・マルローらも、参加したことで知られる。
アメリカ人義勇兵第一陣は96人。その中に白井もいた。フランスのルアーブルに着いた後、パリの国際旅団義勇兵派遣本部に出頭し、正式に登録する。自分で用意した軍服に身を包み、彼はバルセロナに入った。バルセロナは、人民戦線がかろうじて死守している町だった。
「国際旅団」というものの、参加者のほとんどは軍事訓練さえ受けていなかった。そもそも銃器も足りず、訓練するにもきわめて不完全であった。白井もそうである。
米人主体のエイブラハム・リンカーン大隊に配属されるが、白井は、そこで炊事兵となる。総勢428人の大隊は、マドリード郊外に出陣、彼にとってはハラマ川の戦いが初陣となった。結果は127人が戦死。壊滅といっていい。
炊事兵では我慢ならなくなった白井は、機関銃部隊に転属を願い出る。しかし、結果はコック兼歩兵であった。本人の失望はいかばかりだったろうか。
次の戦いが、有名な7月6日からのブルネテの戦いだ。以前、従軍カメラマン・キャパの話を書いたが、キャパの恋人だったゲルダ・タローが死んだあの戦いである。
マドリード防衛のため共和国軍は奇襲に出た。すでに周囲をフランコ軍によって押さえられつつあり、ゲルニカも制圧されていた。しかもナチス・ドイツの支援を受けたフランコ軍が体勢を立て直すと、共和国軍は防戦一方となった。
戦闘が始まって5日後、夕食の運搬車輌が立ち往生したのを見た白井は、それを動かそうと飛び出した。その瞬間、白井は機関銃弾を浴びて即死した。日本人義勇兵は、37歳で散った。一度として、まともに英雄的な戦闘行為に及ぶ機会がなかったかもしれないが、本人は満足だっただろうか。とても一面的ではなく、どちらの側も醜い複雑さを内包したあのスペイン内戦の意味を、一体どれだけ彼は理解していただろうか。
しかし、日本で生きることが難しく、人種差別の大きいアメリカでも居場所を見つけることができなかった白井は、義勇兵として初めて人生に燭光を見出したのかもしれない。英語は下手だが(日本語も下手だったという証言もある)、いつも笑顔で陽気な男。そして子供好きで、勇敢な男としてほそぼそと語り継がれている。義勇兵の動機というものは、実はジャック白井とそう変わらないものが多いかもしれない。大義とは無縁の、きわめて私的な動機ということだ。
わたしの興味が尽きないのは、ジャック白井がスペイン内戦を生き抜いたら、一体どうしていたのだろうか、ということだ。また新たな戦場を求めたのだろうか。
長崎県平戸出身の石橋禹三郎は、明治元年生まれだ。商家の生まれだが、家業を好まず、アメリカ人宣教師の知遇を得て、サンフランシスコに渡り、ボーイとして働いていた。よくある話だ。アメリカへ渡るというのは、立身出世、海外雄飛を夢見ていた明治男の典型的なパターンだ。
それがどうしたことか、石橋は、南米チリの革命義勇兵募集に応募しているのだ。時に1889年、21歳。なにしろ日清戦争の前である。西南戦争からまだ10年ほどしか経過していない時分だ。
現地入りして、主に従軍記を書いていたようだから、幸か不幸か、石橋の場合は戦死することもなく、その後一旦帰国している。タイで事業を起こそうとしていたようだが、30歳で病没している。
この石橋禹三郎の場合は、当時平戸では、いわゆる南進論が盛んな時代であったから、義勇兵といっても、日本という国家を、たった一人で背負ったような使命感があったわけで、ジャック白井のような棄民さながらの義勇兵参加とはまた動機も、意味合いも違うだろう。
そうかと思えば、まったく(この言い方はあまり妥当ではないかもしれないが)趣味や道楽の延長上の外国軍への参加というケースもある。
その名は、バロン滋野。滋野清武男爵である。名古屋出身。1896年に、父を亡くして襲爵している。父親は、長州奇兵隊出身の軍人であった。
生来芸術家肌であったため、陸軍幼年学校を全うできず、神経衰弱となったため中退し、遊興にあけくれていた。東京音楽学校で、コルネットを習得し、そこで知り合った子爵の三女と結婚している。が、この若妻は早逝してしまい、これを機に渡仏。
もともと音楽を勉強するつもりだったらしいが、パリの音楽学校在学中に、ライト兄弟たちの活躍による飛行機ブームに呑みこまれた。フランスの飛行学校を渡り歩き、操縦技術を習得。1912年1月には、フランスで、日本人初の万国飛行免状(アエロ・クラブ)を取得している。
1912年には、自ら設計した飛行機に、亡き妻の名を冠した「和香鳥号」とともに帰国。陸軍の教官になっているが、上官(徳川氏)と馬が合わず、1914年には再び渡仏している。
折りしも第一次世界大戦勃発で、滋野はフランス陸軍航空隊に志願して、飛行大尉に任命されている。外人部隊である。フランス外人部隊は、法的にはれっきとした正規軍であり、傭兵とも、また義勇兵のように身分の保証のないものとは違う。しかし、立場や動機からすれば、ある種の義勇兵といってもいい。フランス軍飛行隊には、10人ほどの日本人パイロットがいたというから、驚きである。
エースを集めた、「コウノトリ飛行大隊」の操縦士として、ドイツ軍機を6機撃墜。第一大戦では、日本人唯一のエース・パイロットとなっている。この戦功で、レジオン・ドヌール勲章を授けられている。
滞仏中に、戦争未亡人のフランス人女性と結婚しているが、病気療養のため飛行隊を離れた。3年後、夫人を伴って帰国。航空事業発展に尽力したが、成果を挙げないうちに肺炎と腹膜炎のため、死去。享年42。
一言でいえば、なにしろ恵まれた生い立ちだ。ジャック白井とは、あまりにもかけ離れた境遇といっていい。ただ、人間は与えられた環境の中で、とにかく糸を手繰り寄せていく以外にない。本人にとってみれば、その選択には、それなりの動機があったに違いない。
義勇兵というのは、言葉こそ誇らしいが、失望に満ちたものであることは容易に想像できる。ヘミングウェイは、スペイン人民戦線に義勇兵として参加した前にも、第一次大戦では従軍記者としてイタリア戦線に志願している。その経験から生まれた長編の一つが「武器よさらば」なわけだが、あの行動主義者ヘミングウェイとは思えないほど、厭戦的な内容となっている。結末たるや、主人公男女二人の敵前逃亡であるから、およそヘミングウェイのイメージらしくない。
また、スペイン内戦の経験で書いた「誰がために鐘は鳴る」は、もっと複雑な彼の思いが反映されている。ファシスト反乱軍(フランコ軍)が行ったテロより、彼が組した共和国軍側において、共産主義者がアナーキストに行ったそれのほうが遥かに苛烈を極めており、むしろヘミングウェーは、そちらの描写のほうに詳しく頁を割いている。
義勇兵は(道楽を別とすれば)必ずといっていいほど、失望を味わうということだ。その失望の結末は、結局自分自身が引き受ける以外にはない。傭兵のような、金銭授受によるきれいさっぱりの割り切りが、無い。まだ中東では、ISIS(イスラム国)に参加した外人義勇兵が、多少は残存しているらしいが、彼ら現代の義勇兵たちは、その動機はともかく、結末を引き受ける覚悟が一体どこまで出来ているのだろうか。