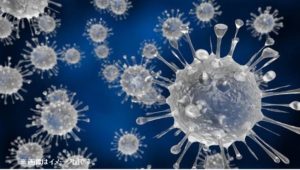恥を忘れた文化は・・・

これは405回目。
むかしむかし、アメリカの女性文化人類学者ルース・ベネディクトが「菊と刀」を著しました。第二次大戦中、アメリカは敵である日本を徹底的に研究しようとしたときの、中心的な教材でした。
:::
「菊と刀」は日本でもつとに有名な名著である。これだけ外人が日本文化の本質に迫ろうとした論考も当時少なかったのだ。
ルース・ベネディクトの論考は、当時の米軍にとって、日本軍の将兵の行動原理やメカニズムを知る上で非常に役に立ったようだ。戦場における日本軍の行動パターンの把握に効果的だったわけだ。
ベネディクトは、日本を訪れたことはなかったが、日本に関する文献の熟読と日系移民との交流を通じて、日本文化の解明を試みた。少なくともアメリカ文化人類学史上最初の日本文化論である。
余談だが、ルースは同じく文化人類学者で名高いマーガレット・ミード(ルースの教え子)と、同性愛の関係でもあったようだ。
この「菊と刀」は、日本文化の本質の一つに「恥」の概念の大きさを指摘している。欧米キリスト教文化が、「罪」の概念に重きをおくのと違うというわけだ。
たとえば、山登りをしたとする。誰も見ていなければ、ゴミを捨てていくが、誰かいればきちんと自分のゴミは自分で始末するといった類いだ。
さて、どうだろうか。日本人として、「なるほど、そういうところはあるなあ」と思う一方で「まてよ、それって外人も同じじゃないのか。」とも思う。
個人差があるから、こういう文化人類学というのは非常に線引が難しい。下手をすると、大変な民族性の誤解へとミスリードしてしまいがちだ。
日本の文化を外的な批判を意識する「恥の文化」と決め付け、欧米の文化を内的な良心を意識する「罪の文化」と定義しているのだ。
結果、この「日本人は恥の文化」という一言が独り歩きをしてしまい、日本人の本質は「恥知らず」だという一般常識形成に寄与したともいえる。
ただ、この「恥」という概念の日本人の精神における重さというものは、根底に「恩」と「義理(義務)」という価値観があることもしっかりルースは見抜いていたのだから、その意味では日本精神文化への一方的な批判として理解するのも、間違っているような気がする。
実際、ルースはそうしたやや偏向的で、日本人批判的な論旨を気にしていたのか、教え子たちには「あまり『菊と刀』は読まないように」と忠告していた。
本人の意図(著作発表時と、その後では本人の認識も変わっていった可能性がある)はともかくとして、「罪の文化のほうが、恥の文化より優れている」という論調に読めてしまうのは事実だ。
また「恥」を重んじるあまりに、集団主義的傾向が強まる。一方「罪」の文化は、個人主義的(神と自分との関係が基本であるから)傾向というステレオタイプの文化論になっている側面もある。
ルースが人生を通じて、最終的にどういう結論に至ったのかは知らないが、思うに、日本人の「恥」という文化性は、かなわらずしも「ひと」の目を気にしているだけではなかったのではないか。
つねづね思うのだが、日本人には「畏れ」という概念も非常に強い。怪談文学・怪談説話といったものが日本は世界中でもとりわけ豊かななものがある。突出しているといっていいくらいである。
これは、西洋の一神教とは違うが、明らかに霊性という認識が根底にあり、「バチが当たる」ではないが、見えない何らかの絶対価値によって、復讐される、呪われる、祟られる、怨まれるといった「畏れ」を非常に意識した精神文化であった。
「恥」を意識するというのは、単に生きている「ひと」の目を気にするだけではなく、見えない、うかがい知れない存在に対して、言いようのない「畏れ」を抱いたのが日本人である。その「畏れ」という感覚は、たとえば先祖の霊や、神仏に対して自分の行いが「恥」であるおちう認識とまったく表現こそ違え、同じものだ。
要は自分意外の「もの」の目を気にするということだ。
じつはこのように突き詰めてみると、西洋人の「罪」をベースにした価値観と、実はそれほど大きな違いがあるようには、わたしには思えない。
強いて言えば、「恥」の文化性というものは、きわめて情緒的・感情的な心の働きだが、「罪」の文化性というものは万事理詰めだということくらいだろうか。
どちらも自分の行動原理を規定・判断する場合の動機である。その動機は、自分以外の何ものかに依存しているということだ。
正義の理屈に従うか、反するかが行動基準であるキリスト教文化と、恥知らずなるまいという心持ちが行動基準である日本文化と、どちらが現実的だろうか。
正義は、時代によって、立場によって、まったく異なる場合が多発する。しかし、恥ずかしくないようにあろうという心持ちは、理屈抜きでかなり誰にでも通用する汎用的な基準である。
正義は間違えることが多いが、恥という認識はたいてい間違っていない。
極端なことを言えば、百人いれば、正義などというものは百通りあるとさえ、わたしは思っている。しかし、恥ずかしい行いというものは、百人いておそらくほとんど似たような恥ずかしさを覚えるものであることが多いのだ。
どちらが社会の静謐を維持するのに有効だろうか。少なくとも、こういう観点からすれば、「恥」のほうが優位にあると思ってしまう。
セックスというものも、恥があるからこそ、淫靡さを伴う。それがただの欲の処理にとどまらず、文化をつくってきた。
これが現代社会のように、青空のもとのスポーツや、オープンな表現として市民権を得てしまったから、欲望の処理というただのつまらない機械的動作に堕落してしまっているのだ。
これなどは、セックスが神から与えられた人間の当然の権利であり、罪深い行いではないのだ、という西洋的「解釈」がもたらした弊害と、わたしは思っている。
権利か、どうかそんなことは、日本人の旧来の精神文化からいった、まるでとんちんかんなことなのだ。恥ずかしい行い、という「後ろめたさ」が性風土、性文化というものを、重厚で芳醇なものとしてきたのだ。
いまや日本人も、この「恥」というものを、さまざまなフィールドで意識しなくなってきているとすれば、薄っぺらい民族性に堕落しているということなのだろう。
だいじなものは、常に見えないはずなのだ。