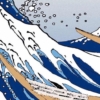無形の価値~日本人は台湾に何を残してきたのか?

これは39回目。学生時代、長い休みに台湾で中国語の勉強をしに行ったことがあります。これは一番最初に行ったとき、連休をはさんでバスなどを乗り継ぎながら、一周してみたことがあります。忘れられない人たちがいます。
:::
学生時代、湯島の聖堂で募集していた台湾での中国語研修に参加して、二度ほど長い休みの期間に台湾に滞在したことがある。旧米軍宿舎に6人一組で泊り込み、毎日、外国人向けに中国語教育をしていた新聞社まで通った。
午前中はマンツーマンで、午後は先生一人に生徒二人で会話力を中心にトレーニングするのだ。参加者のほとんどが大学生だった。台北にある大学生との交流の機会も多かったし、もちろん同行した日本人学生にも知人が増えた。
週末などは、できるだけ小旅行をしたが、長距離の場合はたいてい一人で動いた。なにしろ学生の分際であるから、バックパッカーの貧乏旅行に決まっている。
花蓮では、不思議な体験をした。タクシーに乗って、台湾人学生の実家に向かっていたときだ。運転手は、子供のころ日本統治下だったこともあって、日本語がそこそこ話せた。途中、アミ族という原住民(ほとんど半裸状態だったが)が、車を止めた。「おい、これ○○へ行くか」。「いや、△△へ行くんだ」。「ああ、それじゃ方向が違うわ。すまん」。タクシーは再び走り出した。
当時まだ、車両が少なかったため、タクシーは乗り合いが普通だった。なんとはなしに聞いていたが、やがておかしなことに気がついた。彼らの会話は、すべて日本語だったのだ。運転手は、「みんな言葉が違うから、日本語なら話が通じます」、と。台湾という世界の断面をまざまざと見せつけられた最初の経験だった。
あるとき、台南を訪れたときだ。夏だったので、なにしろ暑い。ゼーランジア城まで歩いたのだが、途中、とある公園で一息ついだ。大きな檳榔樹(びんろうじゅ)の木陰にベンチがあり、そこで老人たち3人が集まって、中国将棋を指していた。私はその隣のベンチに座った。老人たちは、すぐに話しかけてきた。これまた、見事に流暢な日本語だった。
「日本人の学生さんかい」。「はい」。「日本はずいぶん発展したねえ」・・・。ときに、1970年代の後半。80年代の黄金時代に道が開かれようとしていたときだ。音楽界では松任谷由美、山下達郎、そしてサザンオールスターズが登場し、時代のBGMが大きく変化しようとしていた時期だ。会話は、ほとんど彼らの一方的なもので終始した。
きわめつきは、「うちの倅(せがれ)が今、ベルギーで働いているのだが、今度日本へ出張に行くそうだ」・・・。「せがれ」などと言う言葉は、いまではもう日本でも使う人が少ない。うちの父親がよく使っていたのを思い出し、妙に懐かしい思いがした。まるで親の世代の日本人と話をしているようだ。いや、もっと日本人的に思えたかもしれない。
その3人が興味深い話をしてくれた。戦前、小学校の先生は当然日本人だったわけだが、終戦で帰国する際に、みんなで米やらなにやらいろいろ持ち寄って先生に持たせ、基隆港まで見送ったそうだ。「なにしろ、東京は焼け野原で何もないと聞いていたものだからね」。戦後、日本は混乱の最中であったし、台湾は台湾で蒋介石の国民党が進駐してきて、「2.28事件」のような凄惨な内戦状態も経験した。以来、長いこと、恩師とは音信不通だったそうだ。
戦後30年を経て、たまたま仕事で日本に行っていた仲間が、ようやく恩師の消息を得た。存命だった。生き残っていたかつての台湾人生徒たちは、またみんなでお金を出し合って先生を台湾に招待したのだという。終戦後、初めての同窓会である。先生の旅費、食費、すべてをみんなでまかなった。「去年、それが実現したんだな。いやあ、先生、年とってたわ。みんなも喜んでねえ。また来年やろうといってるんだよ」。
殖民支配をしていた日本人が、かくまで台湾人に慕われたケースはこればかりではないだろう。ただ、台湾人の彼らに、そこまでさせるほどの人徳が日本人教師にあったことも、容易に想像できる。昔の教師は労働者ではなく、聖職者としての自覚が強かった。
かくいう私の父親は、北海道の羽幌の出身だ。かつての炭鉱町である。父は10人兄弟の末っ子で、貧困は辛酸をきわめたようだ。思い出すのも嫌なのか、子供の時分のことを、ほとんど話そうとしなかった。姉の一人は、事実上の身売りをした「らしい」という話を聞いたくらいだから、その気持ちも分からないわけではない。自然環境も苛烈をきわめ、その苦労は想像を絶するものがある。近隣では、大熊に村が襲われて多数の犠牲者がでるような大事件(「熊嵐」と呼ばれる)も発生した地域だ。
父はなかなか優秀だったらしく、先生が家にやって来て、息子さんを上の学校にぜひ上げてやってくれと、父の両親に頼んだそうだ。両親は、上の兄弟をすべて学校にはやらずに働かせたので、末っ子も同じ対応をするつもりだったらしい。先生はなんと父を師範学校に入れて、卒業するまでの費用は面倒を見る、と言ったのだ。度重なる説得に、とうとう両親は折れて、実際にその通りになった。父は往時を回想して、あの先生がいなかったら今のおれはなかったなあ、とよく話していた。
父親が私に話してくれた、若いころの数少ない逸話である。そういう教師は、あの時代、確かにいた。台湾人のその「先生」も、そうした人物の一人だったかもしれない。その薫陶を受けた台湾人の生徒たちが、日本人より日本人的に見えても、なんらおかしくないだろう。
あるとき、また小旅行をした。金曜日、体調が悪いと仮病をつかって、はやばやと出かけたのだ。高雄から台東に長距離バスで横断し、鉄路で台北まで戻ってくるというコースを取った。その長距離バスで移動中のことだった。途中、夕刻が迫るころ、とある場所で休憩に止まった。とんでもない田舎のバス亭で、数軒農家が見えるだけの、さびしいところだった。バス亭横には小さな小売店があって、弁当や果物、お菓子、日用品も多少は置いてあった。
その薄暗い待合に腰かけて出発までぼんやりしていると、また年配の台湾人が話しかけてきた。「田中といいます」。彼は、日本統治時代の名前で名乗った。「本当に日本はよくなりましたねえ」。彼らは、日本が発展していくことに、たとえようもない喜びを覚えるようだ。まるで、自分の国がよくなっていっているような気がするのかもしれない。この複雑な思いは、支配者と被支配者という単純な割り切りでは到底説明のできないものだ。
「ところで、中村大尉はご健在ですか」・・・知るわけがない。「いや、済みません。存じ上げませんが」。「そうかあ。中村大尉には公私ともに、えらくお世話になりましてね。元気にしているかな。もう亡くなっているだろうか」・・・。ひとしきり話し終わると、出発の時間が来た。わずか4、5分の会話だったが、別れを告げてバスに乗り込むと、窓の外からコンコンと叩く人がいる。
ふと窓ごしに外を見ると、その台湾人が立っていて、窓を開けろという身振りをする。開けたとたん、どっと重いビニール袋を中に押し込んできた。中には、果物やパンや飲み物などが、いっぱい詰め込んである。「台東まではえらい時間がかかるよ。途中、ほとんどなにも売っているとこはない。これ、途中で食べていきなさい」・・・。彼は、バスが走り出てからも、夕焼けの中でずっと手を振って見送っていた。私は、どういうわけか涙が止まらず、夜半、台東に着くまで、結局ビニール袋のものを何一つ口にすることができなかった。
日本人は、台湾という島国でいったい何をし、何を残してきたのか。日本国内を上回る数の小学校と上下水設備、どんな田舎でも電気が通じなど、インフラでは本国顔負けの施策をしたのは分かっている。ただ、それだけで台湾人が、独特とも言える対日感情を抱くことはない。朝鮮半島でも、満州でも同じようなことをしているはずだ。どこに違いがあったのだろうか。
少なくとも台湾では、目には見えない「無形の価値」を残してきた、個々の日本人がいたのだ。それが日本人的かどうかは、この際どうでもよい。民族を超えて、なお琴線に触れる何かを残してきたに違いない。そのほとんどは、私たち日本人が忘れかけているものかもしれない。しかし、彼らはそれを覚えている。そして、それが次の世代に連綿と地下水脈のように継承されていく。
ちなみに、東北大震災に対する各国の義捐金では、台湾が140億円を超えてダントツであった。次の韓国が25億円であるから、いかに台湾のそれが大きなものだったかが分かる。しかも、その8割が民間からのものだという。間違っていなければ、この台湾からのアクションは、各国の中で一番早いものだったと記憶している。確かに、お金ではない。しかし、お金に思いを込めることはできる。