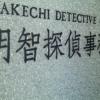南洋幻想

これは243回目。日本人だけではありません。北半球の人間というのは、どういうわけか赤道周辺の南洋諸島に、言うに言われぬ郷愁と幻想を抱きがちなのです。
:::
ハワイにしろ、タヒチ、サモアなど、南洋諸島がなにゆえ「楽園」のようなイメージでくくられ、また旅情を掻き立てるのか。
もともと、南洋には白人の流浪者(ホワイト・ボヘミアン)たちがぞろぞろと集まってきていたのだ。彼らは、母国の窮屈な生活に嫌気がさし、あるいは仕事や事業、恋愛に失敗し、逃げるようにして出てきた連中もいただろう。
現代は、「引きこもり」というが、南洋に出奔していった連中は「外こもり」と呼んでもいいかもしれない。毎日、原住民と同じく裸同然でうろつき歩き、酒をくらい、なにすることもなく日を送る。原住民たちからは、からかわれ、ときに調停者として尊重され、親しまれた白人の流浪者たちも少なくはなかった。
その後、どんどん植民地化が進み、えらそうな階級の白人たちが、気候の悪い欧州にいたころと同じ格好でやってきて、彼らが信奉する現代文明を振りかざしては、土着文化を駆逐していった。
先にきていた流浪者たちは、後からやってきたこの傲慢な白人支配者たちに、剥き出しの憎悪をぶつけた。タヒチにいたゴーギャンもそうだろう。
南洋の土着の人たちからみれば、どこで外来人に線引きをしたであろうか。おそらく、土着化しようとしてた白人と、通りすがりの白人とで線を引いたはずだ。ゴーギャンは、その線上にあり、やや現地人側に傾斜していた、といったところだろうか。
南洋小説の傑作を多く書いた作家に、有名な人物が二人いる。サマーセット・モームと、ルイス・スティーブンソンだ。
この二人とも、通俗小説の面白さに満ちていて、いまだに世界中で好んで読まれている。が、現地では二人の評価は、かなり違う。
スティーブンソンは未だに、サモアで深い尊敬と愛着を持って語られるが、モームのほうは嫌われているといってもいいくらいだろう。
(スティーブンソンー=左と、ハワイ王朝カラカウア大王=右。ホノルルのカラカウア大王のボートハウスで)

モームは、皮肉屋なのだ。だから、文面からして、原住民を小ばかにしたような筆致が見え隠れしており、それが土着人の気に障るのだろう。愛情を感じないということだ。が、モームのその「クセ」は、なにも「南洋の土人」に対してだけではないのだ。文明人に対しても、平等に皮肉屋なのである。
・・・わたしはいつも人々に興味をもってきたが、彼らを好きになったためしはない。(Sモーム)
いかにもモームらしい言葉だ。だから、彼が南洋で嫌われているというのは、いささか気の毒な気もする。
(モーム)

白人の貧窮流浪者たちは、南洋の持っていた自由さ、純朴さに心惹かれたのだが、後からやってきたキリスト教文明は、それをことごとく「野蛮だ」の一言で片づけ、「教化」していった。しかし、その情熱も今となっては当初の意図とは違う形で結実していっている。
たとえば、南洋のある島では、『死者の出た家を訪問すると死ぬ』という言い伝えがあった。しかし、白人宣教師が訪れたら死ななかった。宣教師たちは、『それは聖書を持っていたからだ』と布教の材料にしていったのだ。
純朴な原住民たちは、次第にキリスト教へ入信していった。しかし、行けばわかるが、キリスト教は、あくまでその地の土着文化の上に「接ぎ木」されただけであって、よく見ると、「キリスト教だけれども、キリスト教とは違う何か」に変容しているのだ。もともとあった土着の精霊信仰は、まったく消滅するどころか、マリア像や磔刑像に形を変えていただけなのである。
モームの場合、現代文明に変容したかにみえて、本音はまったく違う文化を脈々と伝えている現地人たちのずる賢さを皮肉り、一方で自分たちの文明強化策が一定の成功を治めたと信じてご満悦の白人支配階級を軽侮するのだ。
モームの傑作の中に、とりわけ有名な「雨」という作品がある。皮肉も皮肉、凄絶なまでの皮肉である。読み手を衝撃のラストで、最後にぺしゃんこにさせるところは、いかにもモームらしい。「雨」の場合は、白人宣教師と白人娼婦の話であるから、なにも南洋が舞台である必要はないが、それこそ南洋特有の雨が状況を劇的にさせているのは確かだ。
もう一つの傑作「赤毛」もそうである。これは、白人船員とカナカ人女性との恋物語だ。美しい描写でつづられた悲恋は、そのまま終わるのかを想えば、ラストはやはり強烈な皮肉で読み手を、失望と愕然の淵に叩き落す。
モームが、ホモセクシュアルであったということも影響しているのかもしれないが、男女間の愛をことごとく破壊しつくさなければ気が済まないという側面は、もしかしたらあるのかもしれない。もっとも、ホモセクシャルではなくても、こういう小説は書けるだろうし、このへんは過去さまざまな論評をされているが、今に至っても判然としない。(ちなみに、モームは結婚しており、娘もいた。バイセクシャルといったほうが正確かもしれないが)
ただ、わたしが思うに、モームはその仕事(本業)がこうした人間の裏面を突き詰めてみようとするスタンスにさせていたのではないかという気がしている。
モームは、第一次大戦が勃発すると志願してベルギー戦線(西部戦線)の赤十字野戦病院に勤務した。やがて諜報機関に転属。スイスのジュネーブに滞在して活動を行う。
表向きは作家を続けたが、1916年に健康を損ない、諜報活動を休止。翌年、アメリカから日本、シベリアを経由して、ペトログラードへと向かった。大英帝国情報機関MI6の所属である。スパイだ。
なにをやったかというと、ロシア革命が勃発しており、アナーキストが帝政ロシアを打倒して、革命政府が樹立されていた。無政府主義者も、自由主義・民主主義者も、共産主義者もごったまぜのケレンスキー革命政権である。
当時大英帝国は瀕死のフランスとともに、ドイツ軍と激しい消耗戦を西部戦線で行っていた。一方、それまで帝政ロシアは東部戦線でドイツ軍と戦っていた。
もし、革命政権がドイツとの単独講和に踏み切ってしまい、戦線から脱落すると、ドイツ軍は東部戦線の全軍を西部戦線に振り向けてくるだろう。これは英仏連合軍にとっては、とどめの一発をくらわされる危険性があった。だから、なんとしてもロシア革命政権がドイツと単独講和するのを阻止しなければならない。
モームはその任務を帯びて、ロシアに潜入、ケレンスキーと交渉したのである。資金援助をすることで、革命政権は引き続き対ドイツ戦を継承することで落ち着いた。ところが、その矢先、レーニンがクーデターでケレンスキー革命政権を倒し、赤軍による政権奪取に成功。これで、ソ連が成立し、ソ連はただちにドイツとの単独講和に踏み切った。モームの調略は失敗した。
モームは、司令部からレーニン暗殺の命令も受けたともいうが、これは都市伝説の域を出ていないので、何とも言えない。スパイのことだから、ほとんどの事績は闇の中だ。
こういう経歴のある人間だから、人間の裏の裏の、またその裏が見えてしかたがなかったのではないだろうか。疑わなければ、生きていけない、そういう世界にモームは生きていたのだ。それが、彼の小説にも色濃く反映されているような気がしてならないのだ。
モームというと、ついつい「月と六ペンス」を思い出してしまうだろうが、それならゴーギャンの伝記を読んだほうが、遥かにマシだ。モームの真骨頂はやはり「雨」や「赤毛」だろうと思うのだ。
これに対してスティーブンソンは、批判や否定をしない。肯定できるものを、ひたすら肯定するのだ。
・・・人生は良いカードをどれだけ揃えられるかではありません。手持ちのカードを使って何ができるかです。
・・・すべての人に必ずどこか学ぶべき点があります。
・・・幸福になることほど過小評価されているものもないでしょう。幸福に過ごす人々は、誰も知らないところで、しかし世界に大きな利益をもたらしているのです。
(サモアのスティーブンソンの家、現在記念館。1935年撮影なので、死後40年経過した時点の写真。)

スティーブンソンは40代の若さで、死んでしまったが、それこそ「ジキル博士とハイド氏」や「宝島」などの傑作を世に出している。モームが90代まで生きたのに比べると、あまりにも早い死だが、その割には、モームより多くの人に好まれる小説を多産したと言えるだろう。
夢で見たことをそのまま書いた「ジキル博士とハイド氏」や、妻の連れ子二人(男女)がいずれも物語好きで、スティーブンソンがつくり話を考えて読み聞かせてやっていたのが、気に入られて自信を持ち、そのまま「宝島」に結実していった。
「宝島」は大人が呼んでもわくわくする名作だ。少々、子供には乱暴すぎる内容であるかもしれない。
(宝島)
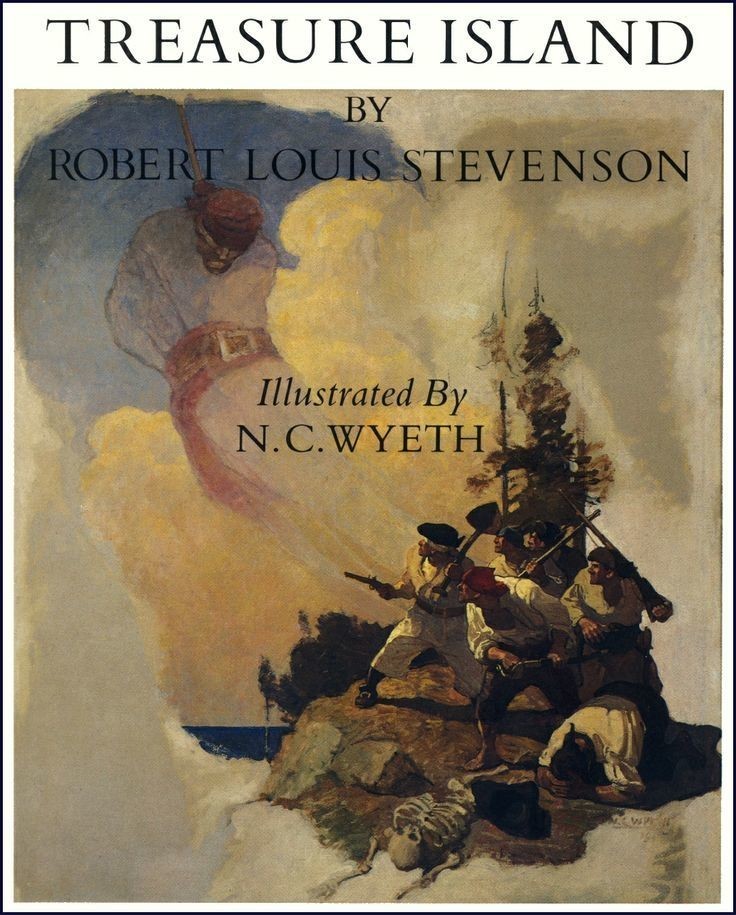
スティーブンソンは子供の頃から非常に体が弱く、何度か結核になっている。最終的には妻と話をしながら、ワインボトルの栓を開けた瞬間に脳溢血で倒れ、死んだ。
その妻というのは先述通り連れ子二人がいて、スティーブンソンより10歳も年上のアメリカ人女性だった。パリで知り合って、それを彼はアメリカまで追いかけていって結婚したのである。体はひ弱だが、やることは情熱的である。この「熱さ」が、おそらくモームと違うところだろう。
その後、スティーブンソン一家は彼の転地療養を兼ねて、南太平洋はサモア諸島ウポル島に落ち着く。現地では、「語り部」として大変人気が高かったそうだ。
このスタンスの違いが、南洋におけるモームの不人気と、スティーブンソンの人気と、明暗をくっきり分けることになったようだ。
ちなみに、スティーブンソンは日本人から、吉田松陰の話を聞いており、その情熱的な生涯に感じ入ったのだろうか、「吉田寅次郎」という伝記を書いている。おそらく世界の歴史で、一番最初の吉田松陰の伝記であろうかと思う。
わたしはまだ読んだことがない。スティーブンソンはなぜ、聞きかじりで松陰を書こうとしたのだろう。なにが心を打ったのだろう。一度、みなさんも探してご覧になったらよろしいのではないでしょうか。