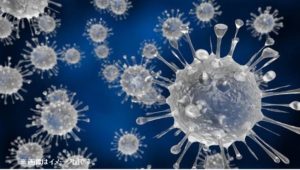神の見えざる手

これは398回目。
近代資本主義理論の嚆矢となったアダム・スミスの言葉です。市場経済というのは、不思議なものです。
:::
元々はキリスト教の終末思想に由来しているという。
「人類最後の最終戦争には、信徒は神の見えざる手により救済され、天国へ行くことができる」
当時、アダム・スミスたち経済を論じたものたちは、これを経済論に比喩としてつかった。
市場経済において、各個人が自己の利益を追求すれば、結果として社会全体において適切な資源配分が達成される、とする考え方だ。
スミスは個人が利益を追求することは一見、社会に対しては何の利益ももたらさないように見えるが、各個人が利益を追求することによって、社会全体の利益となる望ましい状況が「見えざる手」によって達成されると考えた。
スミスは、価格メカニズムの働きにより、需要と供給が自然に調節されると考えた。
この市場経済というものの自浄作用というものは、ときにバブルを生み、ときに暴落や恐慌を生む。
その熱狂(マニア)と恐慌(パニック)をなんとか回避しようと、以来さまざまな経済学者たちが頭を悩ませた。
極端な話、そうした市場メカニズムそのものを忌避し、独裁権力の統制下に置いて、だれよりも国民の幸せを「知っていると自称・自認」する一握りの人間が、最適な資源配分を計画経済によって実現しようとする共産主義も生まれた。この考え方は、ナチズム(国家社会主義)や、現在の中国共産党が標榜する「国家資本主義」も同じ穴のむじなである。
逆に、バブルになろうと、恐慌になろうと、それが「自然なこと」なのだ。市場が間違っていないとすれば、それは「行き過ぎたことは、必ず反動を引き起こし、修正させる」のだから、放置すればよい、重要なのは経済や市場を均衡に陥らせず、不断のイノベーション(技術革新)が必要なのだというウィーン学派(オーストリア学派)、ひいてはその延長上にある、超自由主義にまで発展していく流れにもなっていった。麻薬でさえ、無限解禁を標榜する過激派も存在する。
経済学者は右から左まで、百人いれば百人十色だが、過去30年間に限っていえば、経済学は進歩するどころか退歩したとさえ言われる。
ノーベル経済学賞を受賞したポール・ローマーがそう言ったのだ。
同じくノーベル経済学賞のポール・クルーグマンも、「経済学の大部分は、良くて甚だしくやくたたず、悪くて全くの有害」とさえ言った。
クリントン政権時代の財務長官で、ハーバード大学の学長も勤めたローレンス・サマーズは、「主流の経済学モデルは、政策担当者にとって、本質的に無益だった。」と言っている。
2008年のことだが、英エリザベス女王が、経済学の世界的な権威たちに「なぜ、危機を事前に察知できなかったのでしょう」と訊ね、一同を絶句させ、誰も回答できなかったのは有名な逸話だ。
経済学の根本的な間違いは、「一般均衡理論」であると言われる。
「完全な情報をもつ合理的な個人が、完全な競争市場において、最適な行動をする」というきわめて非現実的な仮定(一般均衡の概念)をもとに、経済モデルをあれこれ考えるものだから、現実から極端に乖離してしまう癖があるのだ。
それは市場メカニズムというものを蛇蝎のごとく嫌う共産主義的なイデオロギーも、極端にこれを放任させようという超自由主義派も、しょせん同じ間違った仮定にこだわって、批判・非難を繰り返している以上、同床異夢である。
経済という学問分野は、いまだに数学だの、純粋理論だのでイデオロギー偏重を伴った憶測や、子供じみた情熱を克服できていない、といったのは、「21世紀の資本」を書いたトマス・ピケティである。
彼によれば、その結果、歴史研究や他の社会科学との共同作業が犠牲になっており、経済学者は彼らの内輪でしか興味をもたれないような、どうでもいい数学問題にばかり没頭しているという。
この数学への偏執狂ぶりは、科学っぽく見せるのにはお手軽な方法だが、わたしたちの住む日常世界が直面する、遥かに複雑な問題には答えられない。
たとえば(これは以前書いたかもしれない)、現在主流の経済学は、「商品貨幣理論」を前提としている。
経済の進化というものは、物々交換の原始的経済から、その不便さを解消するために、現代の貨幣経済に変化したという考えだ。
このような経済史観の問題点の一つは、貨幣を貴金属から変化したさまざまな財(商品)の一種とみなしている点だ。
しかし、現実には物々交換によって経済を発展させていったという歴史的事実はいまだにどこにも立証されていないのだ。
素朴な感覚としての「物々交換→貨幣経済」という歴史観は実はきわめてお粗末な通俗的なイメージでしかない。
物々交換の問題点は、異時点間の取引が成立しないという点だ。
たとえば、同じ生活圈の中でなら、物々交換は有効性を持つかもしれないが、異時点間の財の交換こそ、社会を飛躍的な進歩させたと考えられるからだ。
秋に穫れるサンマと、夏に穫れるスイカを交換しようとしても物々交換は成立しない。そこで、借用書の概念がでてくる。いわゆる、「ツケ」である。経済学的に言えば、「負債と弁済」という概念といってもよい。
夏にスイカを受け取った人が、秋にサンマを渡すことで債務が弁済されるのだ。「信用」という経済概念の発生でもある。
このような時間差の発生する取引を成立させたのが、貨幣の発祥起源ではないのか、と社会科学をはじめ、経済学の外にいる人たちからの批判である。
つきつめていえば、世の中「借金で回っている」といってもいいくらいだ。
貨幣理論一つとっても、経済学と呼ばれるものはこのていたらくである。
そして、彼らがどんなに口から泡を飛ばして理想的な経済政策は・・・と主張しても、永遠に変わらない一つの事実がある。
市場を動かしている、「神の見えざる手」だ。
2011年3月11日、東日本を未曾有の大震災が襲った。このとき、一瞬で経済価値が吹き飛んだ。
経済学的な表現をすれば、ストックが25兆円、フローが10-15兆円である。もちろん、失われた貴重な地元のコミュニティー(生活共同体)を経済価値に換算できないから、これは省くとしても、少なくとも50兆円の価値は文字とおり「消滅」した。
震災と同時に発生した東京市場の暴落では、15日までの立ち会い3日間で、あっと言う間に時価総額総計で52兆円が減滅した。
ほとんどアイコである。なぜ、個々の投資家が、それぞれの思惑や恐怖や、熱狂(空売りしている人が大喜びだったろう)など、ばらばらな阿鼻叫喚に陥っていた中で、誰も意図していなかったのに、市場全体としてどんぴしゃりの「計算」をしてみせたのか、誰にもわからない。それを「神の見えざる手」とでも呼ぶのだろう。
経済学者や政府、中央銀行など最も優秀な人たちが必死でその「価値の減滅総額」の算出を終えたのは(どのくらいの財政出動が必要かという計算だ)、一番早いところでも震災当日から1ヶ月後である。
その市場をコントロールしようと思うほうが、どうかしているような気がしてならない。