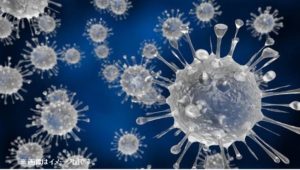趣味は、なんですかと問われて・・・

これは455回目。
趣味を軽く扱ってはならない。
趣味は選択だからだ。
つまり、その人の生き方に直接つながっている。
良い趣味と、悪い趣味という違いはあまり気にしなくても良い。
その人にとって、それがブーメラン効果で生き様にポジティブな影響を与えるようなものであれば、なんであろうと、良い趣味だ。
ただ、消費者の側に立ってばかりいないで、できるだけクリエイターの域にまで足を踏み込んでみたい。
古来、これは多くのクリエイターたちに、過大な負担を強いてきた。
・・・一生を通じて、わたしは一つの渇望を抱き続けた。なにか創造的な形式によって、自己表現を成し遂げる力、それをわたしは望んだのである。(TEロレンス=アラビアのロレンス、「智慧の七本柱」)
たとえば、音楽一つそうだ。
「趣味はなんですか?」と聞かれて、「音楽鑑賞です」と答える人は、趣味を消費の世界にとどめていることになる。
そこから、一歩踏み出して、ギターを実際に弾いてみる。ピアノを奏でてみる。そうした能動的な世界に入って、初めて趣味は本来の趣味の輝きを見せることになる。
作曲をしなくてもよいのだ。
歌ってみる、演奏してみるだけで、原曲の持ち味とは違う、その人でなければ表現できないものが現れる。
だから、出来合いの音楽を「なぞる」行為でも、実はその人ならではの世界観がそこには生まれてくるのだ。
トスカニーニの指揮するベートーベンと、フルトヴェングラーの指揮するベートーベンでは、まったく違って聴こえるのと同じだ。
すでにベートーベンの世界を超えて、そこには、トスカニーニの、そしてフルトヴェングラーの世界をわたしたちは目撃する。
さらに言えば、もう一歩踏み出したところに、作曲という純粋にあなただけの世界を生み出す行為がある。
そこまで行けば、もはやプロとアマの違いなどまったくどうでもよくなる。
アニメが好きなら、読んだり観たりするだけではなく、自分のアニメをつくろうとすることだ。
絵画が好きなら、鑑賞するだけにとどまらず、実際に自分で描いてみようとすることだ。
ここで大事なコツがある。
どうしても趣味を、消費行動から一段能動的な域に進めようとするとき、得てしてわたしたちは、技術論にこだわる。
上手な絵(なにが上手か下手かはともかくとして)、見事な演奏、高度な和音和声や音階の駆使、・・・大事なことだとは思うが、あまりこだわらないほうが良い。
たとえば、わたしはここでこういう随筆まがいのものを書いているが、得てして文体や構成にこだわる。
これを気にし始めると、もう収拾がつかなくなる。
ものを書くのであれば、もちろん日記のようなものからでもいいだろう。
文体は、試行錯誤していれば、そのうちに独自の文体が生まれてくる。
それよりも重要なのは、「なにを書きたいか」のほうである。
それが一番の難問だ。
なにを書きたいかがみつかれば、文体はしょせんおのずからついてくる。
だから、これが適当なたとえかどうかわからないが、同じ江藤淳の評論の中でも、「作家は行動する」で指摘している文体云々のことよりも、「決定版・夏目漱石(角川文庫版が、よくまとまっている)」に著された思想のほうが、はるかに重要であり、ショートカットでもあるのだ。
絵画やアニメであろうと、音楽であろうと同じで、「なにを伝えたいか」がクリエイターとしては、命についで重要な課題であるはずだ。
たとえば、江藤淳は「作家が行動する」で言いたかった、生きている文体と死んだ文体に区分して、平たく言えば、「既製品の単語ではない、自分自身の言葉で人間や世界に名前をつけてみたり、編集し直してみる」ということにでもなるのだろうが、それは何を書きたいか、訴えたいかで、おのずと手に宿ってくるものなのだ、とわたしは思っている。
だいたい技術論とは、そういうものだ。
基本は知っていたほうがいいし、勉強をして悪いことなどけっして無い。
が、それは片手間でも良いのだ。
自分の表現したい世界の本質に、自分がどれだけ迫ることができるかのほうが、遥かに大事なのだ。
だから、ものを書く場合であれば、技術論より思想を学ぶほうがずっと早道だ。
そして、その答えは、これまたよくわたしたちが陥る悪弊だが、ひたすら自分をみつめて自分の中に見出そうとするが、それは無駄だ。
自己実現などという言葉が、多くのクリエーターを惑わす元凶といってもいい。
そんなものは、最初から無いのだ。
自分がなにかを実現する場というものは、自分の外部にしか存在しない。
だから、思想を得るためには、外界をじっと、深く観察していくことがなにより重要なのだ。
それに、結局自分が投影されてくるはずだからだ。
理屈を書いてみたが、言うのは易いものの、いざやってみるとなると意外に難しく思うかも知れない。
そんなことはないのだ。
コツは、「関心を持つ」ということに尽きる。
この世の中、薄っぺらい価値観で溢れている。
それは、「ありもしない自分にしか関心のない人」が多くなってきたからだろう。
民主主義の成れの果てが、このように文化のある意味堕落をもたらしたのだろうか。
かつて、アラビアのロレンスは、中東で暗躍し、オスマン・トルコ帝国領内のアラブ人たちを独立に向けて煽動する工作に従事した。
いわゆる諜報活動だ。
もともとは考古学者だったが、非常に毀誉褒貶の激しい人物だ。
工作員としての任務は、(趣味と言ったら怒られそうだが)本職ではない。趣味が高じて抜き差しならない陰謀に飛び込んでいってしまったようなものだ。
少なくとも文学者ではない。だから、残された文章は、単に記録的な諜報員らしいものばかりだ。
その中に、はっと思わせるような、美しい描写が(少なくともわたしには)たった一つだけある。
(確かアカバ攻略戦の後だったと記憶しているが、間違っていたらすみません。)
敗退し、撤退していくドイツ軍の様子を描写したものがある。
それは、破れたりといえども、見事な一糸乱れぬ撤退の様子だった。
銃を担い、砲を引き、整然とした隊列を組んだ退却の有様だった。
仮に「われわれ(ロレンスたち、アラブ軍)」が背後から追撃しようものなら、敢えて踏みとどまり、一戦も辞さないという覚悟が、退却するドイツ軍全隊にみなぎっていたと言う。
ドイツ恐るべし。
ロレンスはその退却するドイツ軍に、必ず将来彼らは復活するということを予覚したのだろう。
ロレンスは、攻撃をとどめ、精気みなぎるドイツ将兵たちの退却を、ドイツの復興を祈念する思いと、称賛、そして羨望の眼差しで見送った。
なんの衒いも、表現技術に凝ることもない、荒削りのさっと書きなぐった短文でしかないが、そこにロレンスの感動が行間から溢れている。
もし、ロレンスが自身の率いたアラブ軍の活躍ばかりに心を砕いていたら、この文章は絶対に生まれてこない。
彼がどれだけ、他者(敵ですら)に関心を抱いていたかということが、この一事でもわかる。
そのロレンスの死は、バイクを疾走させているときに、少年を避けようとして自損事故を起こしたためだったのは、偶然だったろうか。