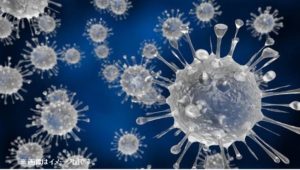日本の回帰不能点は、いつだったのか?
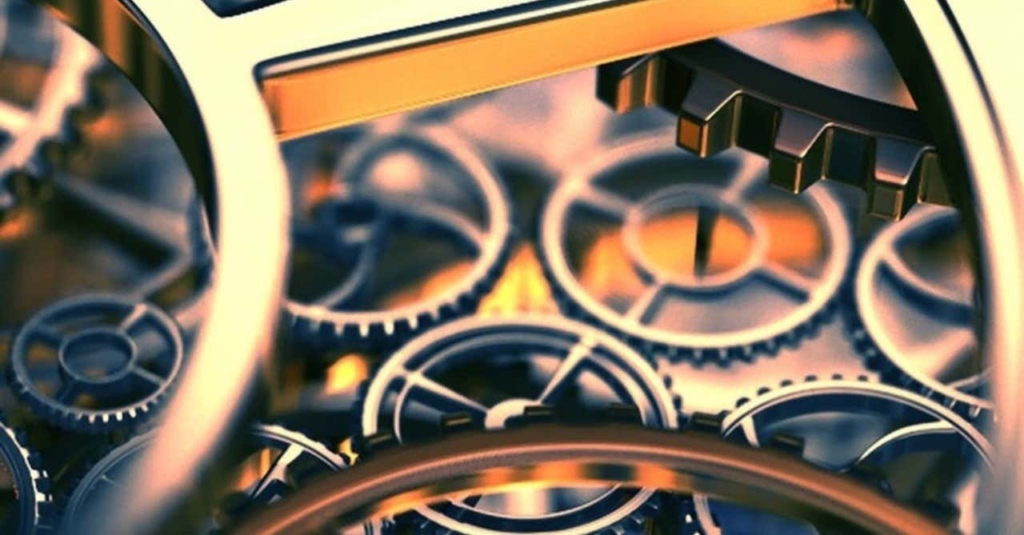
これは32回目。日本が第二次大戦で未曽有の敗戦を喫するに至った経緯については、さまざまな研究がなされています。一体、どこから軌道を外れていったのでしょう。結果論としての敗戦を回避できたとしたら、どの時点までさかのぼらなければならないでしょうか。
:::
回帰不能点。英語では、「The Point of No Return」という。この先進めば、もう二度と後戻りできない分岐点のことだ。そこでつらつら考えるのが、日本が太平洋戦争に突入していくプロセスのことである。何度も、何度も、回帰可能点が存在した。真珠湾攻撃直前でさえ、実はまだ「回帰可能点」はあった、と言われている。
しかし、元を正せば、いったいどの時点から間違ったコースを走り始めたのだろうか。一つ指摘されているのが、日露戦争終結直後である。辛くもロシアの脅威を押し返して、あろうことか南満州の権益を手に入れた日本は、南満州鉄道株式会社をその殖民政策の尖兵としていく。
このとき、実はアメリカ人から、「仲間に入れてくれ」という申し入れがあった。アメリカの鉄道王、ハリマンが来日したのだ。ハリマンは、日本に満州の鉄道の共同経営を持ちかけてきた。もともと、ハリマンは世界一周鉄道を作る構想を持っていた。
これは、日露戦争で疲弊しきっていた日本にとっては、「渡りに船」だった。井上馨、伊藤博文、桂太郎、渋沢栄一らはハリマンの提案に賛成。まだロシアの大軍は満州の北に駐屯していたし、きっかけがあればロシアの報復戦も覚悟しておかなければならない。だから、満州の鉄道経営をアメリカと一緒に行ない、利益を分け合ったほうが良いと判断したのだ。こうして桂首相は、伊藤や井上など元老の意向に沿って、ハリマンと仮条約を交わした。
ところが、である。外相の小村寿太郎がポーツマス条約の調印を終えてアメリカから帰国。この事実を知るや、激怒した。そして、この仮契約に猛反対したのだ。10万人もの犠牲を払い、20億円もの国費を使ってようやく手に入れた満州の権益を、アメリカに半分くれてやるなど言語道断、というわけだ。
小村は、ロシアとの講和交渉が決裂すれば日本は破滅だという、ぎりぎりのところで過大とも言える責任を負って渡米していた。それだけに、元老たちも小村の意見を無視するわけにはいかなかった。
この結果、日本政府は仮契約のキャンセルを決定した。その電報をハリマンは、サンフランシスコに上陸してから受け取った。ハリマンの意思は、アメリカの意思でもあった。「遅れてきた」アメリカは、中国という膨大な市場に進出したいと考えていた。だが、この仮契約のキャンセルをきっかけに、日本が中国利権を独占するのではないか、という懸念を覚え始めたのだ。
しかも、仮条約を一方的に破棄されたことにも、アメリカは不快感を覚えた。有色人種の日本が、白人の大国ロシアに「勝った」ことにも脅威を感じていた。しかも、当時のアメリカは太平洋に展開する近代的な艦隊を持っていなかったから、日本が太平洋を渡って攻め込んでくるのではないかという、ほとんど妄想に近いものすら抱いた。アメリカが、急遽太平洋艦隊の創設に乗り出したのは、このときである。
もともとアメリカは、日清戦争の頃に西部開拓が終わり(フロンティアの消滅)、幌馬車と騎兵隊が、艦隊になりかわって太平洋を越え、中国という最後の巨大なラストリゾートとしての市場に参入しようとしていた。
世界を分割し、今またそのラストリゾートを分割支配しようとしていた西洋列強に対し、「門戸開放 機会均等」を訴えたのは、中国市場を俺にも寄こせという意味だった。
日露戦争で勝つ見込みのない日本に肩入れしたのも、あわよくば日本が勝てば、満州の利権を分かち合い、そこから大陸市場を共同で享受する橋頭保にしようと考えていた。
それを日本がソデにしたわけだ。アメリカが、日本というにわかに台頭してきた極東の成り上がりに、不信感を覚えたとしてもなんら不思議ではない。ここから、昭和20年8月15日の結末へと、歴史は動き出したのである。
最初にできた「ねじれ」や「よじれ」とは、早い段階で解いておかないと、後々どうにももつれ合ってしまい、収拾がつかなくなる。日米確執の原点は、おそらく南満州鉄道の権益を巡る、ハリマンとの交渉だったろう。そして、これが最初の回帰「可能」点だったとも言える。
しょせん、後講釈には違いない。しかし、後講釈なしに先々の知恵は生まれない。相場でも、どうして「やられた」のか、できるだけ後悔してみることが大切だと思っている。深く真摯な後悔がなければ、次にまた同じ重大な失敗をしかねないからだ。
さもなければ、この国は、百回戦っても、百回敗れることになるだろう。