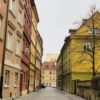日本が死んだ日~ポピュリズムの原点

これは147回目。もう日本人が、誰も気にも留めず、覚えてもいないような一人の人間の死というものがあります。しかし、今のわたしたちの国のいろいろな意味での不甲斐なさや情けなさは、遡ればその人物の死の意味に結局は突き当たります。
:::
世界中の精神文明や哲学というものは、ある象徴的な人物の死の上にすべて築かれている。
西洋文明や西洋哲学が、しょせんどうあがいてみても、イエスの死とソクラテスの死という二人の人物の死を、どう意味づけ、どう受け止めるかの堂々巡りにほかならない。
日本ではどうだろうか。私見だが、古来からの日本の精神文明や哲学ということでは、これに類する例が今一つ見当たらないのだが、こと近代国家としての日本においていえば、間違いなく、明治末年における乃木大将の自決が、その後の日本と日本人にとって、きわめて重大な課題を残したものだったろうと思う。
それは、夏目漱石が「こころ」でこの事件をモチーフにして書き、日本に訪れる悲劇的な運命を予告したことでもわかる。森鴎外などは、乃木自決以降、これをモチーフに「興津弥五右衛門の遺書」「阿部一族」をものにした後、一切「小説」を書かなくなってしまった。
実は鴎外は、その後も書いてはいるが、「小説」ではない。歴史という「事実」しか書かなくなってしまったのだ。当時の文壇の巨星二人に決定的な創作活動の転換を強いた乃木自決事件を、その後の日本人は軽んじた。ほとんど無視したと言ってもいい。その結果が、泥沼の日中戦争であり、アメリカとの総力戦であった。
とくに、多くのインテリや識者は、乃木の自決を「時代遅れの封建思想」と批判したり、武者小路実篤のように「不健全な理性」と否定した。志賀直哉などは「馬鹿なやつだ」の一言である。社会主義者の多くも口をそろえて罵倒した。
漱石や鴎外とは違い、多くの日本人はあの当時、私人としての乃木の自決はともかくとして、日本と日本人にとって乃木の自決がどれほど重大な意味を持っているかを深刻に受け止めず、軽んじたのである。時代を象徴した人物の凄惨な死に仮託された、言葉にできないほどの悲劇性を、それこそ衝撃をもって受け止めた人は少なかった。
時代どころか、歴史や精神文明そのものを左右しかねない、ある象徴的な人物の死は、いずれも「死ななくてもよいのに、死んだ」という点で共通している。
イエスはいくらでも逃亡し、布教し続けるチャンスはあった。乃木は、言うなれば、後追い腹(殉死)であるし、それを称賛する時代ではもはやなかったにもかかわらず、逝った。
ソクラテスもそうである。ソクラテスはアポロンの託宣を通じてもっとも知恵のある者とされた。ソクラテスはそれを聞いて、納得がいかなかった。彼自身は、「自分は何も知らない」ということを知っていたからだ。
その反証のために、彼は知者を僭称する賢人識者たちと論争にあけくれた。ところが、それはかれらの無知を暴くことになったのだ。
プラトンが記録した、『ソクラテスの弁明』によれば、自説を曲げたり自身の行為を謝罪することを決してせず、追放という軽い判決も拒否し、結果的に死刑(毒殺刑)を言い渡される。
票決は2回行われ、1回目は比較的小差で有罪。刑量の申し出では常識に反する態度がかえって陪審員らの反感を招き大多数で死刑が可決された。
その罪状たるや、ほとんどいいがかりである。論争にあけくれ、相手の無知さ加減を完膚なきまで暴露してしまう結果となった彼の半生は、恨みを買ったのだ。罪状のすべては「おまえなんぞ口先三寸の詐欺師だ。」「人を不快にさせる」「周囲の空気に水をさす」そのていどの罪状である。だから、「死んでしまえ」という判決になっただけである。
ソクラテスが一体、法に照らしてどんな罪を犯したのか、は具体的には一切指摘されていない。噂や世論という化け物によって増幅された、大衆心理や感情の暴走の結果が、ソクラテスを無実の罪で死に追いやった。しかも、ソクラテスはそれを拒否しなかったのである。それは、大衆が論理や合理性で動かないということを、ソクラテスは重々承知していたからだ。
このソクラテスの死刑判決は、現在、ソーシャルネットワーク(SNS)上で炎上しては、一人の人間をリンチにかける悪弊と、なんら変わりはしない。その事象の、一断面のみを取り上げて(それすら、どこまで事実で、どのような背景があったのかの確認もはっきりされていない状態にもかかわらず)、一方的に断罪するネット上やメディアの炎上というものを、「ポピュリズム(大衆迎合)」という。トランプ大統領ではない。トランプ大統領によって自らの利権が脅かされる人々の感情論こそがポピュリズムなのである。
この大衆という化け物は、定見がないから、右に左に揺れる。ソクラテス刑死後、人々は、あまりも偉大な人物を、それも不当な裁判で殺してしまったことに激しく後悔し、告訴人たちをなんと裁判抜きで処刑してしまったというオチまでついている。これがわれらが民主主義社会の原型となった、アテネの現実である。
まるでそれは、戦前、海外への版図拡大に歓喜し、対中国戦争を煽りに煽って、政府に泥沼の戦争拡大を強い、戦争不拡大のために中国軍と和平交渉をしていた現地軍の努力を台無しにした、日本国民の『支那撃つべし』の大合唱を思い起こさせる。しかも日本国民は、終戦後は手のひらを返したように、「軍国主義が悪いのであって、国民が被害者だ」と開き直り、今度は「なにがなんでも反戦」と口から泡を飛ばすようになった。
いずれもこの国民のご都合主義の先導をし、扇動をしてお先棒をかついだのはメディアであった。朝日新聞の、戦前戦中の政府も軍も真っ青というくらいの「極右」「侵略主義」と、戦後の「極左」「中国・韓国の御用メディア」へと、極端な立ち居振る舞いの手のひら返しを見ればよくわかる。
そもそも、最近「流行り」の『ポピュリズム(大衆迎合主義)』だが、トランプ大統領や、欧州に雨後の筍のように台頭してきている右派勢力を批判する場合によく使われている。そのくせ、メディアは自分たちこそが、戦前戦後と一貫して、大衆に迎合してきた事実を棚に上げている。自分たちに都合が悪ければ「ポピュリズム」と批判し、自身の主張は「民意」と正当化する。自己撞着とはこのことだろう。
アメリカでも、欧州でも、この20年にわたって、大人の対応をしてきたことに、みな辟易としているのだ。みな、本音を言い始めているのだ。綺麗事や、理想主義などどうでもよい、とにかく現実に今目の前にある問題に、手をつけろ、という「うねり」が、西側諸国に渦巻いているのだ。時代錯誤なのは、ポピュリズムと批判する側のほうだろう。
ちなみに、ソクラテスは相当の皮肉屋だったようだ。妻のクサンティッペが「無実の罪で死ぬなんて!」と嘆いた時も、「じゃあわたしが有罪で死んだほうがいいのかい?」といったといわれる。
もともと、ソクラテスは、プラトンが『ファイドン』で記録したように、死後の世界を信じていたようだ。人間は、「死を眠りであるとか、夢であるとか表現するが、そうではない。死によって魂は覚醒するのだ。目覚めるのだ」と述べている。
生まれてくるとき、人間はその魂の記憶の95%をあの世に置いてくる。その5%だけはどういうわけか抱いたままこの世に生まれてくるという。だから、ときに深層心理の奥底に閉じ込められたわずか5%のあの世の記憶が、臨死体験や突然変異で、ある日急に思い出されてしまう人がでてくる。それが、預言者や大宗教の教祖と呼ばれるような人たちだ、ということらしい。
彼によれば、死は自身にとって禍ではなく、一種の幸福であると言う。なぜなら、論理的には死後については二説あって、唯物論者たちの言うように、死が虚無に帰することであるという考え方が一つある。
全ての感覚の消失であるならば、それは人生において他の昼夜より快適だった、夢一つ見ない熟睡した夜のごときものであろうから、なにもつらいことも、苦しいこともない。
他方で冥府(ハデス)があるとしたならば、そこで真誠な半神たちによる裁判を受けることができるし、ホメロスやヘシオドスと交わったり、オデュッセウスやシシュフォスと問答することもできる、どちらにしろ幸福である、というわけである。これは、後のパスカルが『パンセ』の中で言った「賭けの理論」に通じるものがある。であるがゆえに、死を恐れて不正な裁判に屈することなどなく、善き生を貫徹できるし、善き生を貫徹した者は、死に際しても幸福である。そういう認識でソクラテスは毒を仰いだのだ。
このような偉大な賢人を、当時古代ギリシャにあって、もっとも民主的であったアテネのポピュリズムが、殺したのだ。常に、といっていいくらい、真実を殺すものは大衆である。
ヒトラーを悪魔だと罵ることなど、馬鹿にでもできる。しかし、実体はその悪魔を生んだのは、当時第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約に対する、ドイツ国民の言い知れぬ反発と「怨嗟」「憎悪」が、ヒトラーを生んだだけなのだ。ヒトラーは、正当な選挙によって、圧倒的にして熱狂的な国民の支持を得て、権力の頂点に上り詰めたことを、よもやドイツ人は忘れていまい。
日本人は、その点、あの先の敗戦に至る最大の戦犯が、われわれ国民であったという事実を、完全に見て見ぬようにしている。だから、日本人はあざとい。とても、ほめられた国民ではない、という結論になる。ソクラテスを殺した古代ギリシャ人と同じレベルなのだ。
ピラト総督が、イエスを不当な処刑にしたくない、と思っていた。前夜妻も「あの正しい人を殺さないでください」と懇請したにも関わらず、群衆のイエス処刑を求めるポピュリズムに押されて、イエスを磔刑に処したのである。日本人はイエスを磔刑に送ったのと、同じレベルなのだ。
覚えておくべきである。世に、中立・中道という立場ほど、無慈悲にして残酷、無定見な立場はないのだ。フランス革命が激化していく中で、左翼のエベールを断頭台に送り、右翼のダントンも断頭台に送り、そこから徹底した連日連夜の無差別処刑という恐怖政治に突入していったのは、中道のジャコバン党(ロベスピエールやサン=ジュストたち)だったのだ。
日本が死んだ日(乃木が自決した日)以降、わたしたちはこの重大な悲劇をまともに正視してこなかった。先の戦争の原因や失敗の研究・分析、1990年以降「二度目の敗戦」と呼ばれるデフレ経済の反省というものもさることながら、その原点である、あの1912年9月13日に乃木が自決した日が、一体どういう民族と国家の悲劇を象徴していたか、もう一度立ち返ってみるべきである。乃木という人物そのものではなく、乃木という人物に象徴されたものが、明治天皇大喪の葬列とともに消えていった意味である。以降、だれも、このとき漱石の「こころ」や鴎外の「興津弥五右衛門の遺書」が投げかけた民族の問いに、こたえてはいないのだ。それなくしては、この国は永遠に三流国家であり続ける。