人間、 その気高さと幻滅。

これは237回目。人間は崇高な理想を掲げたりはするものの、現実には見るもおぞましい幻滅にも平気で陥ります。文学はその激しいギャップを、現実以上に際立たせようとします。そんなお話です。
:::
ハリウッド映画というのは、基本的に、勧善懲悪である。ヒーローと悪玉がはっきり分かれている。大衆受けする娯楽としては、ごく単純明快。筋立ての面白さはほとんど、トリックと土壇場の大逆転に依存している。
ただ、観て、それで終わりということなら、それで十分楽しめる。ところが、原作にされることが多い文学(小説)は、ハリウッドがつくった映画とは、まったく違うということが多々ある。
たとえば、1943年公開の「誰が為に鐘は鳴る」だ。戦争中でもあり、反ファシズム(対日独戦争)遂行中だったというアメリカの社会背景がそうさせたのか、それはわからないが、戦時中でなかったとしても、多かれ少なかれ、同じような作品に仕上がっただろうと推測する。
この映画は、当時の大スター、ゲイリー・クーパーと、イングリット・バーグマンの主演で、大ヒットした。
バーグマンは、この原作小説を読んでいたく感動し、ヒロインのマリアが短髪であることから、自慢のロングの金髪を切り落として、ヘミングウェイの自宅まで押しかけて自分を映画製作に起用してもらおうと売り込んだらしい。
(誰がために鐘は鳴る、映画のポスター)

スペインとは何の関係も無い、アメリカ青年ロバート・ジョーダンが、スペイン内戦に義勇兵として参加する物語である。ナチス・ドイツの支援を受けた、ファシスト党のフランコ将軍率いる政府軍と、それに抵抗するスペイン人民戦線(自由主義者、アナーキスト、共産主義者など、反体制派の共同戦線)が、全土で激しい内戦を繰り広げていたのだ。
ジョーダンは、人民戦線側に立って参戦した。人民戦線は、多くの反体制派が集ったものの、事実上、共産主義革命軍だったといっても良い。このスペイン内戦は、その直後に起こる第二次大戦という、ファシスト側(日独伊)と、民主主義側(英米仏)の衝突の前哨戦となった内戦である。いわば、両サイドの代理戦争の体をなしていた。
映画のほうでは、ジョーダンが人民戦線ゲリラに参加し、ある命令を司令部から受ける。ファシスト軍が通る橋の爆破である。これを巡って、ゲリラ仲間たちとのさまざまなやり取りが展開している。とくにマリアとのロマンスが伏線として描かれている。
マリアは親が共和政支持者で、反ファシストであった。親は殺され、マリアはファシスト軍兵士らに凌辱された経緯がある。そのとき、みせしめに髪を坊主のように刈られたのだ。
最終的に、ファシスト軍の布陣が変わってしまったことで、橋の爆破は全く意味が無くなってしまったが、現場を知ることなく、教条主義・官僚主義にはやくも陥っていた人民戦線側の司令部は(左翼というのは、得てしてそうなりがちだ)、それを許さない。
やむなく、ジョーダンたちは実行するが、彼は脚を負傷し動けなくなる。ファシスト軍が攻め寄せてくる。ジョーダンは、自らを犠牲にして機関銃を最後まで打ち続け、マリアたちの逃走を助ける。
まあそういう流れだが、ハリウッド映画はいかにもハリウッドらしく、ジョーダンとマリアの純愛に仕立てて、その悲恋と英雄的行為に観衆は涙するのである。
ところが、原作を読んだ人は、まったく映画とはトーンも、テイストも違うということにすぐに気づく。ジョーダンは、決して英雄として描かれてなどいないのである。ここがポイントだ。ヘミングウェーの意図と、かなり映画のトーンは異なっている。
(壮年期のヘミングウェー)

この小説のタイトルは、「誰がために鐘は鳴る」だが、中世英国の詩人、ジョン・ダンの「瞑想」という詩からヘミングウェイはとったものだ。
なんぴとも一島嶼(とうしょ)にてはあらず
なんぴともみずからにして全きはなし
人はみな大陸(くが)の一塊(ひとくれ)
本土のひとひら
そのひとひらの土くれを
波の来たりて洗いゆけば
洗われしだけ欧州の土の失せるは
さながらに岬の失せるなり
汝が友どちやなれみずからの荘園の失せるなり
なんぴとのみまかりゆくもこれに似て
みずからを殺(そ)ぐに ひとし
そはわれもまた人類の一部なれば
ゆえに問うなかれ
誰がために鐘は鳴るやと
そは汝がために鳴るなれば
(意訳)
地球に存在する総てのもの、それは私たちが共に生きる世界だ。
この地上で起きる出来事、行われることの総ては私達に関わっている。
何者であろうとも、それ自身で完全な島であるものはいない。
誰であれ大いなる大陸の欠片であり大地の一部なのだ。
一塊の土が波に洗い流され
その流されたぶん欧州が小さくなるのは
さながら岬ひとつが失せるようなものであり
あなたの友人、或いはあなた自身の領土が削られるようなものなのだ。
誰が死にゆくとしても、それは自らが削られ死にゆくのに等しい。
なぜなら私自身が人類の一部だからだ。
ゆえに、誰の為の弔いの鐘かと問うてはならない。
それはあなたの為に鳴らされている鐘なのだから。
・・・
つまり、戦場で鳴り響く鐘の音は、戦火に倒れて死んだ者のためにのみ鳴るにとどまらない、それを聞く者すべてのために鳴るのだという意味を、ヘミングウェイはタイトルに込めた。
ロバート・ジョーダンは、スペイン人民の自由と民主主義のために、情熱をもって異国の地の内戦に飛び込んだのだが、そこで彼はそんな正義感とは裏腹に、内戦が生み出す欲望と憎しみが作りだした、「戦いのための戦い」でしかないことに幻滅している。
彼が参加した人民戦線側は、言葉上は美しく、理想的、普遍的な価値をうたっているものの、やっていることと言えば、結局ファシスト軍となにも変わらない暴虐と強制という現実である。
その醜悪な一面を、ゲリラ仲間のパブロを通してヘミングウェイは描いている。先述のように、橋の爆破にはまったく意味がなくなったことを知ったジョーダンたちは、爆破の中止、命令の撤回を司令部に要請したのだ。
ところが、それは聞きいれられなかった。内部抗争、主導権争いにあけくれ、現実の戦線の状況に関心もない人民戦線の司令部である。ジョーダンたちは、多大な犠牲を払って(犬死である)橋を爆破する。命令違反をすれば、自分たちが人民戦線裁判によって粛清・処刑されることは明らかだったからだ。しかし、パブロたちは、土壇場で参加せずに、公然と戦線を離脱していた。
命令を順守して命を落とす悲劇的なゲリラたちと、略奪暴行をして歩くだけが目的の野盗と何ら変わらない自称ゲリラたち。その構図は、あまりにも冷酷な対象をみせる。おそらく、パブロたちは、どういう世の中になっても(ファシスト政権が確立し、人民戦線が敗れても)なお、のうのうと生きのびていくことができるだろう。革命を動かすほとんどの大衆とは、橋の爆破で犠牲打となったゲリラたちではなく、パブロのような人間たちなのだ。それが、革命の実体という皮肉である。
この戦いにはどんな意味があるのか。なぜ他国にまでやってきて自分はそんな戦争をしているのか。自分の死は、報われるのか。そういう思いが、ジョーダンの心から離れるときがない。原作には、ヘミングウェイの政治に対する(とくに共産主義)に対する、激しい幻滅が活写されている。
しかし、原作はその幻滅を描くのにとどまらない。もっと残酷な答えを用意している。それは、自分がファシストやパブロと、なんら変わらないのだ、という真実である。
なぜならジョーダンは、女性を暴力的に支配したいという欲望を持っているからだ。そこにヘミングウェイが対比させたのは、「非現実的なほど従順なマリア」という存在である。ジョーダンの暴力的な欲望と、マリアを強姦したファシストへの暴力的な怒りとにとらわれたジョーダンが、実は自分もただの自己矛盾だと気づくのだ。
信じられないくらい従順なマリアは、ファシストの欲望の対象として強姦され、ゲリラに救出されてからは、女首領ピラールの同性愛の対象となり、それがピラールからジョーダンに譲り渡されていく。つまり、マリアは常に他者の欲望を映し出す鏡である。
ヘミングウェイは、映画のようにジョーダンをヒーローのように描いてはいない。むしろ批判の対象として見ている。
マリアを守るジョーダンの男らしさというものは、傲慢に裏打ちされた暴力そのものであることを描いている。(平たく言えば、それはレイディ・ファーストという偽善と、コインの裏表なのだ。レイディ・ファーストという価値観は、女性を無能・無力・弱者と規定するピューリタニズムなどキリスト教的世界観あればこそ、つくられた概念である。)
ある意味、このヘミングウェーの名作は、アメリカに伝統的に根付いている、ピューリタニズムの欺瞞を激しく非難している作品と言うことも言える。それをロバート・ジョーダンという登場人物に仮託しているのだ。
マリアとジョーダンとのぎくしゃくとした会話、ぎこちないお互いの態度などから、はっきりわかる。二人が交わる場面でもわかる。とても、熱愛に溶け合っていく二人の男女のロマンスなどではない。ジョーダンは明らかにファシストと同じく、暴力とエロスが結合したものとして描かれている。
自らの欲望を一方的にマリアに押し付けるジョーダンは、最初からマリアを事実上強姦していたようなものであり、橋の爆破前夜の二人の交渉は、ファシストの強姦と重ね合わせて描かれている。
しかも、結末では、ジョーダンは脚を負傷し、身動き取れないまま、暴力性にとらわれたまま死を待つのだ。
(映画「誰がために鐘は鳴る」のラストシーン)

「自由のため」「共和国のため」、そういった大義のために死ねないことに気付いたジョーダンは、機関銃を掃射している真っただ中、死のぎりぎりのところで、「マリアのためなら踏みとどまって死ぬまで戦える」と気づく。初めて、マリアを尊厳のある他者という存在として認識するに至るが、すでにそれはあまりにも遅すぎたのである。
思うに、優しさを伴わない力は、ただの暴力である。柔軟さを伴わない力は、ただの頑迷である。信頼を伴わない力は、ただのエゴであり、智慧や理解を伴わない力は、ただの無謀にすぎない。そして徳性を伴わない力は、ただの野蛮にすぎないのだ。
これらすべてを伴ったとき、力はただの力ではなく、初めて高度に知的にして理性的な勇気に置き換わる。ジョーダンは、死の寸前にそれに気づいたに違いない。しかし、やはり遅すぎたのである。マリアは危地を脱したのであろうが、彼女の魂もまた救われていないままだからだ。
ヘミングウェイの小説は、「老人と海」のような数編を除いて、長編はほとんどが暗い幻滅に彩られている。「日はまた昇る」もそうであり、「武器よさらば」もそうである。Lost Generation(失われた世代)ならではの、残酷なまでの幻滅である。
ここで、対照的な作品をもう一つ挙げてみよう。ギィ・ド・モーパッサンの「脂肪の塊」だ。バルザックなどとともに、19世紀フランス文学の代表的な作家だが、彼の多くの小説のうち、最高傑作とさえ言われるのが、この「脂肪の塊」だ。
(モーパッサン)

Boule de Suif(ブール・ド・シュイフ)とは、娼婦の蔑称である。主人公の娼婦エリザベート・ルーセは、どうやらちゃんとしたモデルがいたらしい。ルアンに実在した娼婦、アドリエーヌ・ルゲーという人であったという。また問題の場面となったトートの宿舎、コメルス亭も実在していて、最近まで「白鳥亭」という名前で営業していたそうだ(2016年ごろまでか?)。ということは、モーパッサンはもしかすると実際にそういう場面に出くわし、それを小説にしたのかもしれない。確かに、読んで思う感想は、あまりにも人間模様がリアルなのである。
小説のポイントは、要するに、他者のために自己犠牲をするが、それは報われないという現実である。「誰がために鐘は鳴る」の60年前に、モーパッサンが残酷なまでにこの人間の醜悪さというものを描き切っているわけだ。
この物語は、そういう蔑すまれた娼婦に、紳士淑女たちが助けられるという話だが、結末は何とも言えないやりきれなさを残す。
(脂肪の塊、挿絵)
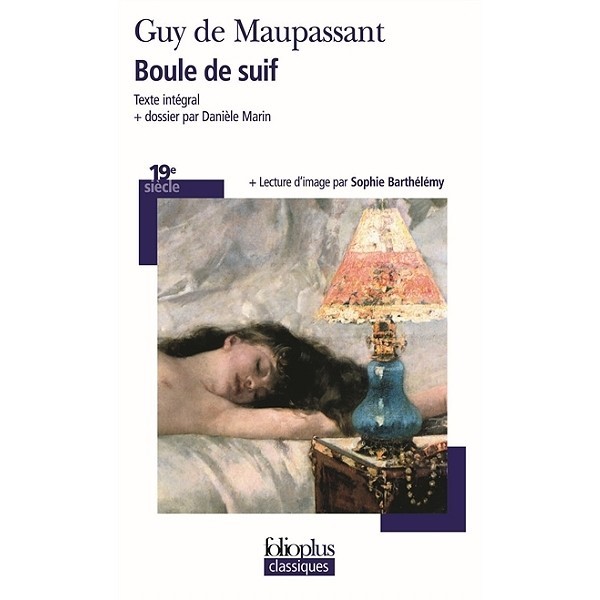
時代は普仏戦争である。プロシア軍に攻め込まれたため、フランス人が安全な地域まで逃避行しようとする。すでにプロシア軍に占領されているルアンを抜け出し、ディエップに向かう10人の6日間の旅である。
彼らは、馬車でディエップに向かい、そこから海路フランス軍が集結しているル・アーブルに行く手筈になっていた。ところが、大雪のため馬車は遅々として進まず、ルアン北方34キロの村トートに到着する予定が、午後になっても一向に目的地に到着しなかった。
乗客たちの空腹は耐えがたいほどになる。乗客たちはみな、政治家、工場主夫妻、伯爵夫妻、富裕な商人夫妻、修道女たちであり、社会的に「立派な」人たちばかりである。しかし、緊急事態に備えた「用意」をしていないのだ。さいわい、娼婦エリザベートだけが食料を持参していたので、彼女は気前よくみなに分けて救われる。
彼女には、ちゃんとエリザベート・ルーセという名があるのに、モーパッサンは敢えて「ブール・ド・シュイフ」という蔑称で書くようにしている。このへんに、他の乗客達がエリザベートをどう見ていたかという視点がよく表れていよう。
さて、トートを出発しようという段になって、次の危機に襲われた。すでにトートはプロシア軍の占領下にあった。そして、そのプロシア軍士官が、馬車の出発を許可しないのである。
なぜなのかというその事情がわかってきた。プロシア軍士官は、一目エリザベートを見るなり、欲情に襲われていたのだ。「今夜、自分に抱かれろ」と迫っているのだ。
ところが、エリザベートは心底愛国者だった。こんなことで、敵であるプロシア士官に体を許すことなど、毛頭ない。
しかし、穏やかではないのは、他の乗客たちだ。もしもそこで士官の機嫌を損ねでもしたら、トートを抜け出すこともできなくなる。
9人の乗客たちは、心無いことを言って、エリザベートを説得する。
「おまえは人に抱かれるのが商売なんだから、さっさと抱かれろ」
「敵とはいえ、一夜の同衾(どうきん)ぐらいなんでもないだろう」
トートを脱出できない乗客たちは、イライラが募る。そして、エリザベートに妥協をせまる。修道女たちは、つとに無関心を装おう。ついに彼女は一行の身の安全のために、こころならずもプロシア軍の士官に身をまかせた。翌日の朝、一行はディエップに出発することができた。
昼時になり、乗客たちは弁当を出して食べはじめた。しかし、エリザベートはプロシア軍士官とのやりとりもあったので、慌ただしく朝を迎えてしまっていた。今度は彼女だけが弁当の用意ができなかったのだ。ところが、前日、彼女のおかげで空腹を脱することができた乗客たちは、誰一人、この局面で哀れな娼婦に弁当を分け与えようとはしなかった。またしても彼女の自己犠牲で、トートを脱出することができたにもかかわらず、である。
それどころか、彼らは同じ馬車に乗り合わせていること自体を嫌悪し、不潔なもののようにさげすみ、白眼視した。エリザベートの心の中には、果てしない怒りと幻滅と悲しみが満ちていく。
ラストでは、政治家(厳格な民主党員で革命家)の乗客が、他の乗客へのあてつけのように、「ラ・マルセイエーズ(革命歌にして、国歌)」の口笛を吹き、歌う。エリザベートは、失われた尊厳にすすり泣きを耐えることができない。
一体、誰が本当の愛国者であり、偽善者なのか。ラ・マルセイエーズの旋律の中で打ち砕かれていく娼婦の自尊心や愛国心。このラストの対照性は、多くの作家や読者たちから、激賞された名場面だ。
原作者のモーパッサンは、この普仏戦争に志願兵として参加していて、ルアン東方にあるアンドリーの森のあたりで軍務についていたことがある。
プロシア軍がルアンに侵攻してきた際、モーパッサンが所属していた仏軍は大敗。一斉にポン=トドメール(原作の中にもでてくる)を通過し、英仏海峡をのぞむル・アーブルへと敗走している。
おそらくモーパッサンは、このときの経験を生かしてこの小説を書いたものと思われる。モーパッサンが20歳のときだ。その屈辱的な敗北の経験が、これを書かせたとも言える。先述のように、おそらくこの敗走過程で、彼は実際に小説中に描かれたような現実をその目で見たのであろう。でなければ、あまりにも迫真性に満ちた描写はありえないだろう。
(「白鳥亭」、旧コルメス亭)

「誰がために鐘は鳴る」も、「脂肪の塊」も、どちらも人間に対する激しい幻滅である。自己犠牲という原動力によって生まれた行動が、ことごとく実は矛盾であったり(誰がために鐘は鳴る)、ことごとく実は利用され、使い捨てられてしまうという現実であったり(脂肪の塊)で終わる。ほとんど絶望に近い読後感だ。こうしたすぐれた文学は、この人間の一番の暗部を切り開いて、「よく見ろ」と迫るのだ。
しかし、けしてそこに答えを書かない。書こうとすれば、それはもはや文学の領域を超えた世界に足を踏み入れなければならないからだ。神、信仰、あるいは宗教的な倫理観という世界である。しかも、それを拒否する権利も選択肢も読者にはある。


























