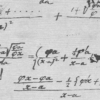ディオダディ荘の怪奇談義

これは385回目。わたしはついぞ知らなかったのですが、エル・ファニング主演『メアリーのすべて』という映画が、昨年公開されていたのです。あの怪奇ゴシック・ロマンの名作『フランケンシュタイン』の作者、メアリー・シェリーの人生を描いた作品だそうです。知っていれば、映画館に観に行ったものをと、大変残念です。
:::
メアリー・シェリーは、長いことシェリー夫人と呼ばれてきた。シェリというのは、英国詩人だが、『冬きたりなば、春遠からじ・・・』と謳ったことで有名だ。
メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』は、その原題を『フランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウス』という。
18歳のメアリーが、なぜこの後世に残る傑作を書き上げたのか?
1816年、スイス・レマン湖の畔にあるディオダディ荘に、詩人のバイロンと、主治医のポリドリが滞在していた。
当時バイロンは28歳、ポリドリは21歳。ポリドリは主治医といっても、実質的にはバイロンのホモ・セクシュアルの相手であった。
当時バイロンは、天才詩人の名をほしいままにしていたが、自らのスキャンダルによって妻アナベラから離婚を迫られ、スイスに逃亡していた。
スキャンダルとは愛人クレア・クレモントとの不倫のほかに、異母姉オーガスタとの間に娘メドラをもうけた近親相姦、さらには同性愛疑惑(ポリドリ)である。
そこにやはり天才詩人のシェリー、シェリーの愛人だった(その後結婚する)メアリー、その義妹クレアが押しかけた。このクレアが、バイロンの不倫相手クレア・クレモントだ。
一方、シェリーにも妻子がいたが、メアリーは道ならぬ恋に落ちたのだ。当初シェリーは、妻子とシェリーと自分が一緒に同棲することを真剣に考えたほど、思考や感覚が尋常ではない。天才とはそういうものなのか。
結局すったもんだした挙げ句、シェリーとメアリーは駆け落ち。二人は逃亡し、義妹のクレアもついてきた。
シェリーも奔放という概念から飛び出してしまうほどだったが、メアリーも負けず劣らずだった。なにしろ、母親(継母)がフェミニズムの先駆者であり、父親は無神論者にして、無政府主義(アナーキズム)の先駆者だったのだ。
メアリーの実母はすぐに亡くなっていたのだ。継母と父は、そろってフランス革命の支持者であり、そもそも結婚制度そのものに否定的な急進主義者だった。
シェリーとメアリー、そしてクレアたちは、ナポレオン戦争が完全集結を見た翌年、荒廃したフランスにとどまらず、スイスにいるバイロンのところにやってきた。クレアがバイロンの元へと誘ったのだろう。
バイロンにしてみれば、もう正直クレアに興味はなかったが、クレアはバイロンの子を身ごもっていた。バイロンは、そんなクレアより、シェリーとメアリーには大いに関心を持ったようだ。
当時、世界の天候は、異常気象だった。前年の1815年にインドネシアのタンボラ火山が大噴火していたのだ。この結果、地球の北半球はすっかり寒冷化していた。
とくに1816年は「夏のない年」と呼ばれ、長雨が続いた。レマン湖畔も例外ではなく雨が降り続き、バイロン卿ら一行は外出もままならず大いに退屈した。
バイロンとシェリーはしばらく哲学談義にふけっていたが、どちらかというと現代のSFに近いような話題だったようだ。
そのうちに、ドイツの怪談本を皆で読み合わせ始める。そこでバイロンが提案したのだ。
We will each write a ghost story.
(それぞれに、幽霊小説を書いてみようじゃないか。)
どうだろうか。これだけ異様なメンツが揃った、長雨で陰鬱な洋館に閉じこもった連中が、怪奇小説に思い耽り、それぞれ書き始めたのだ。想像するだに、奇っ怪な情景だと思わないだろうか。おそらく、現代でもなかなかお目にかかれない異空間がそこにはあったかのようだ。
そしてこのディオダディ荘怪奇談義によって生まれたのが、ポリドリの『吸血鬼』、そしてメアリーの『フランケンシュタイン』だった。
ポリドリの『吸血鬼』は、小説としてまともに吸血鬼をテーマにした、世界で最初の小説である。もともとはバイロンが書きなぐったエピソードを、ポリドリが、バイロンと別れた後、それをもとに書きあげたという経緯がある。
ポリドリはその後、生活が荒れ、おそらく薬物中毒だろうが、25歳で急死している。
メアリーのほうは、こつこつと書き溜めていき、完成に一年をかけている。
後に、あらゆる怪奇小説のステレオ・タイプとして、さまざまな影響を与えていくことになる『フランケンシュタイン』だが、単にその影響は怪奇小説にとどまらない。
宗教の高みにまで問題は突き詰めていく内容だけに、世界文学史上に重大な一石を投じた名作と言ってもよい。
ゴシック小説の代表であるが、同時にロマン主義の小説でもある。書簡体小説の形式もとっている(ブラム・ストーカーの『ドラキュラ』も書簡体小説である。)。科学技術を背景とする着想であることから、最初のSF小説とする評価も生まれた。
『フランケンシュタイン』のような怪物を、なぜ18歳のメアリーが思いついたのか。それ自体が大きな謎でもある。
科学者フランケンシュタイン博士が創造した「怪物」は、死体をつなぎ合わせたものであり、その醜悪さから、創造主である博士からも見捨てられてしまう。
「怪物」に罪はなかったはずだ。すべての責めは、創造主であるフランケンシュタイン博士が負うべきものであったはずではないか。
しかし、文学というものが、作者の生き様の写し鏡であるとするなら、その「怪物」こそは、メアリー自身だったと解釈するのが一番自然である。きっかけは、ディオダディ荘滞在中、メアリーが見た悪夢だった。しかし、それはほんとうにただの悪夢だったのか。それとも、現実が悪夢だったのか。
日記の延長としての私小説を書こうとすれば、そこには当然作者本人が投影されている。そう考えると、シェリーと夢見た自由にして奔放、輝かしい幸福感に満ちているはずのメアリーの人生というものは、恐ろしいほど過酷で、悲劇的なものだったということになる。メアリーが、そこに自身を投影させていたとするならば、である。
彼女は、自身のすべてをそこに書き尽くしたのだろう。が、その甲斐もなく、メアリー・ゴドウィンという本名でなく、匿名出版であった。
当時まだ女性の主体性はまったく認められず、男性の従属物でしかないという社会通念のなせるわざか。それとも、それが自分自身であったためだろうか。
実際、ディオダディ荘での怪奇談義(5月)の後、12月にはシェリーの妻が自殺しており、シェリーとメアリーは結婚している。メアリーは、正妻の死によって、最愛の夫を得たのだ。
自由恋愛といえば聞こえがよい。しかし、人間であれば、当然自身の中に地獄を見るはずだ。
メアリーにとって、シェリーは至福をもたらす天使のはずだった。その天使は、『フランケンシュタイン』出版(1816年)の4年後、地中海でのヨット遭難事故で死ぬ。発見が遅れ、美少年を歌われたシェリーの遺体は無残な状態となっており、まったく見分けがつかなかったという。彼はそのまま海岸で荼毘に付され、メアリーはそれに立ち会っている。
メアリーが、前妻から奪い取ったも同然の幸せは、もろくも崩れ去った。
作中の怪物は、創造主の博士に、「自分と同じ存在を生み出してくれ」と懇願する。死体のさまざまな部位をつなぎ合わせ、電気によって生み出される怪物だ。それによって、自身の存在という絶望的な孤独をせめても癒やそうとしたのだ。しかし、博士は拒否し、怪物を見捨てる。怪物は、博士が大切してにたるものを次々に破壊していく・・・
聖書の『創世記』に記述されている、創造主とアダムの関係に似ている。
天才的な詩人、知的で感性豊かな人々との交歓、自由気ままな漂白生活、名声に彩られた誇り、・・・あらゆる素晴らしい「部位」を寄せ集めた幸せであったはずなのに、どういわけか結果的にメアリーは残酷なほどの悲しみや孤独感、そして死が周りにつきまとう。
前妻の自殺、シェリーの遭難死、そしてその2年後にはバイロンがギリシャの独立戦争に参加し、熱病で死ぬ。翌年にはバイロンのかつての同性愛の愛人だったポリドリが急死する。
『フランケンシュタイン』の初版、そしてシェリーの序文をつけての再度出版、いずれも匿名を余儀なくされた、女であるがゆえの「自分という存在の喪失」。時代がそういう時代だったのだ。
さらに、この前後で、長男・長女の夭折。
なぜだろう。望んだもののすべては、結果的にことごとく滅んでいってしまった。理想を求めて生きてきたはずなのに、それは逆に自分を襲いにきているのではないか。
メアリーが格闘した相手が、神(創造主)であったのか、それとも、運命そのものであったのか、それはわからない。
作品のラスト部分で、博士の遺体を前にして、怪物が嘆く。
・・・夏の心地よいあたたかさ、葉のざわめきと鳥のさえずり、これらが私にとっての総てであった頃なら、私は死ぬのに泣いたかもしれない。けれど今、死だけが私の慰めなのだ。罪で汚れ、つらすぎる後悔によって引き裂かれた今、死以外のどこで私は安らげるだろうか?・・・
その慟哭は、メアリー自身の慟哭でもあったはずだ。
メアリーは1851年に死んだ。
翌年、新世界アメリカでは、ストウ夫人の「アンクル・トムの小屋」が大ベストセラーとなる。奴隷制度反対を訴えた名作である。それは、男女同権がまだ存在しなかった時代にあって、ようやく女性が本名で著作を発表し始めていた。
時代が変わり始めていたのである。同じ頃(1852年)、アメリカの東インド艦隊提督ペリーが、日本に向けてノーフォーク港を出航していた。・・・