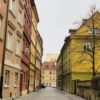ゲティスバーグの黄昏(たそがれ)

これは、315回目。
:::
これまでもいくつか、戦争に関するテーマで書いてきました。司令官の無能ぶりについては、第二次大戦中の日本軍によるインパール作戦のことを、「ある日のチッタゴン」で詳しく書きました。ここでは、世界の戦史上、実に考えられないほどの無謀な作戦例を挙げてみましょう。
:::
一体、なぜ、このような無謀な作戦が実施されたのか。失敗の本質は、なにも日本軍だけではない。
南北戦争のゲティスバーグの戦いである。1863年7月1日から3日まで行われた。このゲティスバーグを境に、北軍の攻勢への転換点となったと言われるが、実際には西部ではほとんど南軍は支配地を失っており、食糧・弾薬など補給も行き渡らず、すでに劣勢に立っていたといっていい。
しかも、その守りすら、満足になしえていなかったといっていい。したがって、リー将軍(南軍)の狙いは、イチかバチかの賭けに出て、一気に攻勢をかけて逆転しようとする意図があったと推察される。
南北戦争史上最大の激戦となったことで知られるが、その後半戦で、南軍が行った信じがたい作戦があった。一般に「ピケットの突撃、 Picket Charge(ピケット・チャージ)」と呼ばれるものだ。
動員兵力は、北軍がミード将軍以下93921人。南軍がリー将軍以下71699人。結果は、北軍の勝利だが、被害は両軍ともあまり変わらない。北軍負傷14531人、戦死3155人。南軍負傷12693人、戦死4708人だ。捕虜あるいは行方不明は、北軍が5365人、南軍5830人。
こうしてみると、被害状況はほぼ互角。しかし、退却したのは南軍だった。数字上は互角のダメージだが、人口の少ない南部にとって、損耗兵力合計2万3000人というのは、あまりにも致命的なものだったのだ。
ゲティスバーグはワシントンから見るとむしろ北方だが、南軍は南部からワシントンの西側を迂回するかたちで軍隊を送り込んだ。そこは、北軍の補給と部隊増強の要衝となっていたからだ。
(南北戦争とゲティスバーグの戦い、地図)
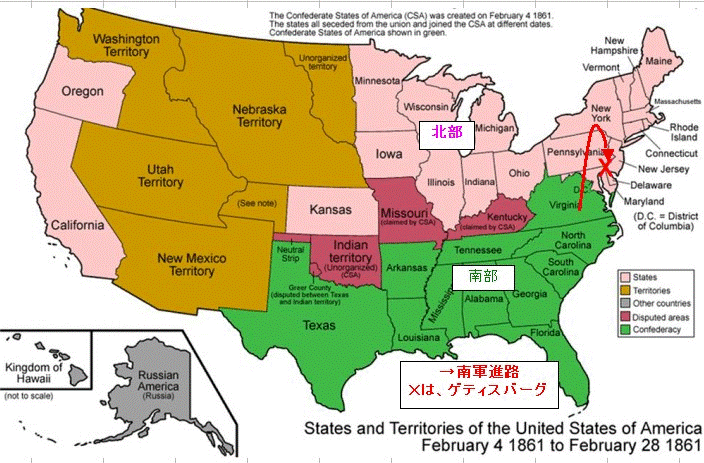
南軍は、当初威力偵察のつもりで、6月には現地に軍隊を進出させていたが、なにしろワシントンのすぐそば、それも首都の北わずか80kmのところに南軍が進出してきているわけだから、尋常ではない。この戦いに敗れれば、北部首都圏(ワシントン、ボルチモア)、は総崩れという決勝点だったといっていい。
裏側から北軍の手薄なところを突破して、一気に首都圏を占領し、リンカーンや連邦議会を捕虜にしてしまえば、形勢は大逆転する可能性は確かにあった。もっとも、リー将軍にそこまでの腹があったかというと、非常に疑問である。
一方リンカーンは、直前、北軍の司令官をフッカーから、ミードに更迭している。ミードを選んだ理由は、彼がアメリカ出身者ではなかったからだと言われる。アメリカ市民であっても、アメリカで出生していない人間は、大統領に出馬することができないからである。結構、リンカーンもあざとい。この大決戦で、ミードが勝った場合、その後の影響力を恐れたということだ。平たくいえば、自分が次の選挙で追い落とされる心配のない人間にした、ということである。
さて南軍は、直前に、チャンセラーズビルの戦いで勝利していただけに、勢いに乗って、一気に北部の継戦意欲を喪失させようとした。それで、大胆にも南部から長駆して軍を発進し、北部の首都ワシントンの北側に進出させたのである。
すでに6月3日から、偵察部隊などによる前哨戦は始まっていた。小競り合いが続き、本格的な戦闘に突入していったのは、7月1日、午前5時からだった。
この7月1日の時点では、戦場に投入された兵力では、南軍のほうが優勢であった。一日目の初戦で、南軍は北軍の防衛ラインの突破に成功している。まだ、北軍には最高司令官のミードが到着しておらず、リー将軍は戦場にいた。南軍がゲティスバーグ南方に広がる標高差12mのなだらかな丘陵の尾根を確保するのには、絶好の機会だった。
(南軍総司令官、リー将軍)
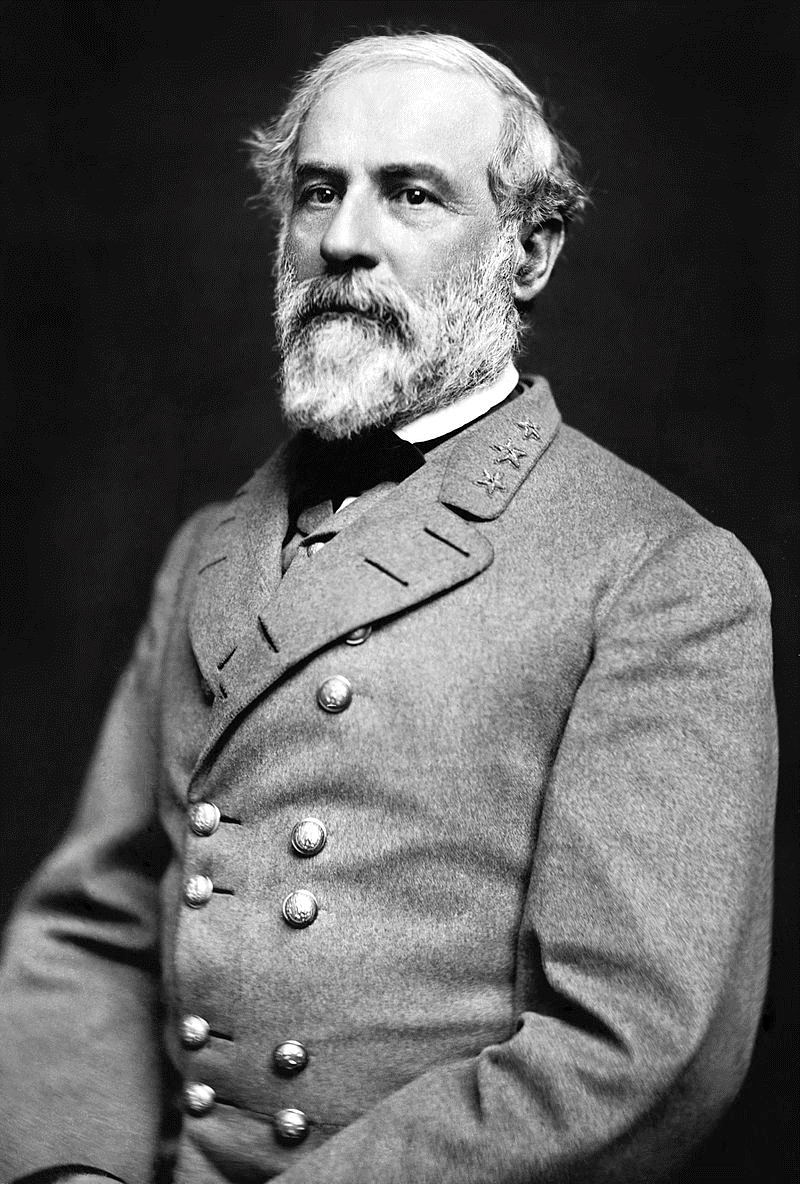
しかし、リーはここで致命的な失敗をする。その好機を生かせなかったのである。北軍が、退勢を立て直して、丘陵地帯の尾根を確保し、防衛線を構築するのを阻止できなかったのである。
実は、リーはこのとき、北軍が防衛線を完成させる前に叩くよう、配下のイーウェル将軍に命令をだしたが、イーウェルは攻撃をしかけなかったのだ。
リーが、イーウェル将軍に下した命令は、次のようなものだった。
「もし君がそれを合理的だと思うならば、丘の上にいる北軍を攻撃するべきだと私は思うが、残りの部隊が到着するまで大規模な戦闘は避けるように。」
これは、非常に曖昧な内容である。現代のわたしたちがこれを読んで、果たして命令と思うだろうか。そもそも何を命令されているのかもわからない。
命令というものは、簡潔にして、目標を具体的に指示することである。しかし、リーと言う人物は、幕僚に自分の意図を推しはからせるような命令ばかりするタイプだった。
指揮官としてのリーは、指揮に関して「分権的」なアプローチを好んだと言われる。現場の部下の判断に任せる、というスタイルといっていい。また、部下に命令 する事を好まず、部下に何かを勧める という態度をとることが多かった。英語で言うならorder ではなくadvise である。
これでは司令官なのか、軍事顧問なのか、立ち位置さえ不明瞭である。ただ、リーという人格者、そのカリスマ性が、このような指揮命令が不明瞭な南軍司令部であっても、南軍の団結力を維持していたといっていい。
リーが、地図を指して見せただけで、彼の真意をすべて読み取ることができたジャクソン将軍のような名将に恵まれた時は、このシステムは非常によく機能した。しかし不幸なことに、このゲティスバーグでは、リーの右腕だったジャクソン将軍がすでに戦死していた。これは、ある意味ゲティスバーグで南軍が敗北した大きな一因だったかも知れない。
ある南軍兵士は、その手記に、「ゲティスバーグで戦った後、やっとリー将軍はジャクソン将軍が本当に戦死したという事に気づいたようである」と書いている。
さて、このきわめて曖昧で、不明瞭な命令を受けたイーウェル将軍は、前哨戦で被った自軍の損害を過大に評価していたこともあり、この日の攻撃を中止してしまった。これで、千載一遇のチャンスを逸したのである。
1日の夜、ついに北軍にはミード将軍が援軍とともに到着。2日目の戦いは、北軍が判断ミスを行い、戦線南部から一部兵員移動をした地点に間隙が生じた。すかさずそこに南軍が攻撃することで始まった。
終日、つど手薄となった北軍防衛陣地に、機動的な攻撃をかける南軍と、その後は見事な采配で陣地補強を繰り返した北軍の、いわばモグラ叩き状態の戦闘だった。内線をフル活用した北軍の防戦が勝ったといえる。そもそも、兵力で互角、あるいは若干少ない南軍が、北軍を包囲する攻撃態勢自体、無謀であった。
3日目、重大な戦闘が二か所で行われた。スチュアート将軍の率いる南軍騎兵隊が、北軍の背後(つまり、ゲティスバーグの東5km)に大きく迂回して、北軍の補給・通信網の遮断にでたのである。
(北軍総司令官、ミード将軍)

これを許すと、小高い丘陵の尾根に沿って布陣している北軍は、包囲殲滅される重大な危機であった。この南軍騎兵による強襲を、猛戦して撃退したのが北軍のカスター将軍の騎兵隊だった。(このNOTEの「第七騎兵隊全滅」を参照。)南軍の迂回戦術は、このときカスター・ダッシュと呼ばれる強行突撃で頓挫してしまう。
(ゲティスバーグの戦い)赤が南軍、青が北軍。
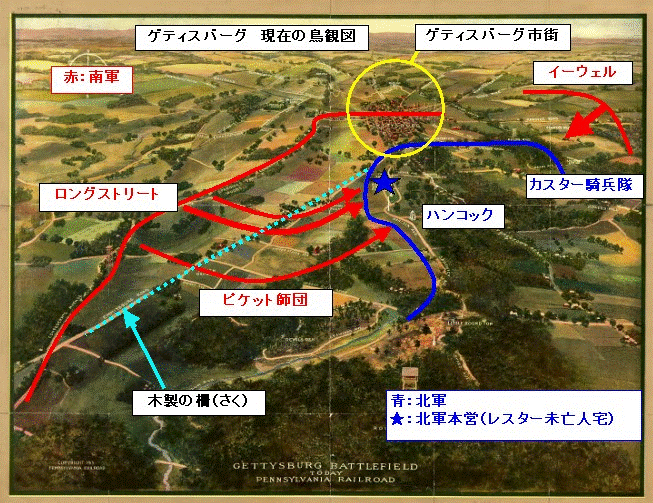
もう一つは、丘陵地帯西側から北軍陣地を圧迫している南軍の、歩兵による密集隊形突撃、「ピケット・チャージ」だ。
午後1時から、南軍の総力を挙げた砲撃が行われたが、弾薬不足で北軍に大きな損害を与えるまでには至らなかった。しかし、これは北軍の罠だったとも言われる。北軍は、この日の午後の南軍の砲撃攻勢に対して、応戦していないのである。その結果、リーは、北軍のダメージを過大評価した可能性があるわけだ。
そうでもなければ、この後、3時に行われた、ピケット・チャージ(ピケットの突撃)はあり得ない無謀な作戦であった。ピケット・チャージと言われるが、実際には、三人の将官がそれぞれの歩兵集団を率いて攻撃したもので、ピケットはその一人にすぎない。
南軍の砲撃がさほどの効果は無かったとはいえ、心理的に北軍兵士を動揺させるには十分だった。実際には、しばしば南軍砲弾は、北軍の防衛陣地を飛び越して後方に直撃していっただけだったが、ミード将軍ら司令部を置いていたレスター夫人の小さな家も、その直撃を受けるなどして、北軍司令部はさらに後方に移動を余儀なくされたくらいだった。
(北軍司令部、レスター未亡人の居宅~ゲティスバーグ戦直後と現在)

北軍が、砲撃で応戦しなかった理由は、砲兵隊を指揮していたハント准将が、わずか80門の大砲(南軍は150-170門だった)と、弾薬を節約するために、午後の応戦を停止させたのだが、一説にはこれが意図せざる罠になったともいわれる次第だ。
ミード将軍は、南軍の猛烈な砲撃に委縮する北軍兵士の士気を盛り返すためにも、砲撃応戦せよとハントに強い口調で叱咤するが、ハントは頑として抵抗し、砲撃応戦をしなかったのだ。
これが、ほんとうにそういうやりとりだったのか、北軍司令部の巧妙な罠だったのか、今となっては不明だが、結果として南軍に、無謀な歩兵の密集隊形突撃を誘発することになる。
砲撃が止むと、南軍の戦列が動き出した。この日は暑く、気温は31度。湿度も高かった。
リー将軍が、このピケット・チャージを命令したわけだが、どういうわけだかこのときは、かなり明確な命令であった。不運なことだった。いつもの曖昧な命令だったなら、現場指揮官が揉みつぶす可能性もあったかもしれない。
幕僚のロングストリート将軍は、この突撃に反対していた。むしろ、北軍側面に回り込む斜行戦術を彼自身は好んでいたようだ。ロングストリートは、リーにこう言った。
「閣下、わたしは終生軍人でした。わたしはときに二人で、班で、連隊で、師団で、そして軍隊で、兵士たちとともに戦ってきました。他の者と同様、兵士たちには何ができて、なにができないかを知っています。この突撃で、1万5000人の兵士を配置したとしても、あの陣地を奪取できないというのが、わたしの結論です。」
(ロングストリート将軍)

しかし、リーは北軍が応戦しないのを、相当のダメージだと誤認したのか、あくまでピケットらの密集突撃を命令する。ロングストリートはなぜ、反対だったのか。長年の勘であろうか。それとも、南軍による猛烈な2時間に及ぶ砲撃も、じつは大して北軍にダメージを与えていないと正確に認識していたからだろうか。
南軍砲兵隊長のアレクサンダー大佐は、猛烈な砲撃の末弾薬が尽きかけたところで、上官のロングストリートに、ピケット・チャージに移るよう要請した。弾薬が完全に尽きてしまってから歩兵の突撃に移れば、歩兵はまったく援護射撃の無い裸の突撃をしなければならないからだ。
ロングストリートは、自身の言葉では命令しなかった。なかなか下令しないロングストリートに、アレクサンダーは業を煮やして詰め寄った。「突撃命令を伝達してよろしいですね」と繰り返し、許可を求めたのだ。ロングストリートはただ、うなずいただけである。もはや、ロングストリートには、次に起こる惨劇が見えていたのだろう。納得できない命令を下すことに、せめてもの抵抗を示したのかもしれない。
ピケットの突撃に移った南軍歩兵は、合計12500人だった。ペティグルー、トリンブル、そしてピケット、9個師団の投入である。
(ピケット将軍)

突撃(Charge)と呼ばれているが、実際には、これは全長1.6kmに及ぶ、大規模な密集横隊が、整然と小高い丘陵の北軍陣地に前進していったのである。それは、もはや当時からさかのぼることすでに50年前の、ナポレオン戦争時代の歩兵による攻撃方法であった。いわゆる「戦列歩兵」による強襲である。
当初は、北軍からの砲撃で、荒っぽく南軍の両翼がなぎ倒された。倒れる兵士によって空いた間隙をすぐさま埋めて、横隊は粛々と前進していった。南軍は砲弾をこの時点では完全に消費しつくしており、歩兵の密集体形の強襲を援護することができなかった。南軍歩兵師団は、遮蔽物の無い平原を、全隊露出したまま、一方的に撃ち込まれる砲撃と銃撃の弾幕の中を、黙々と前進していったのである。
(映画の中の「ピケットの突撃」シーン~南軍歩兵師団が、砲兵陣地を出て、まず木柵を目指して前進し始めたところ。)
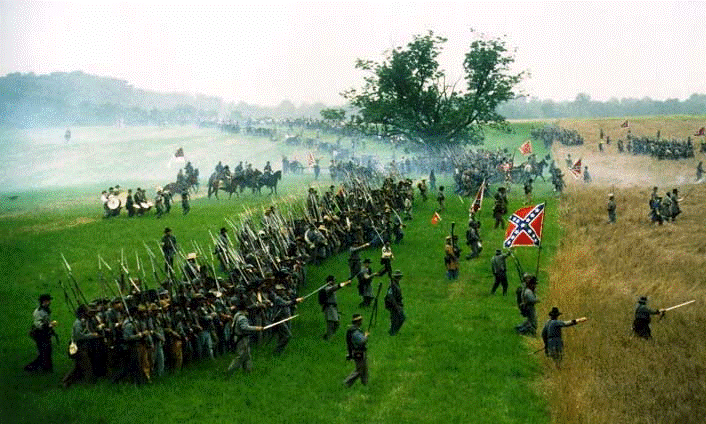
南軍師団は、長大な密集横隊のまま前進し、半分を過ぎるころには、木製の柵(さく)が立ちはだかる。これを過ぎると、緩やかな登り降りの斜面をいくつか超えて、北軍の前哨部隊が石を積み上げた低い堡塁に到達することになる。
柵を超えて、北軍陣地から360mに近づくと、北軍は散弾とマスケット銃の一斉連射に入った。北軍は、散弾の量を通常の2倍装填にせよと命令している。1.6kmもの長大な横隊は、この段階ですでに800mに縮小していた。後には累々たる南軍兵士の屍が戦場を埋め尽くしている。
(映画のシーンから~北軍の一斉射撃)

この後は、両軍の兵士の顔がはっきり視認できる距離に接近しており、北軍の大砲の砲弾が、南軍兵士を直撃するほどであった。運悪く砲撃の真正面にいた南軍兵士は、小隊ごと吹き飛ばされた。
それでも南軍の一部は、北軍の前哨堡塁(低い石垣)を超えて、大砲の鹵獲(ろかく)までするにいたっているが、それもわずか120名足らずの南軍兵士たちだけである。ほとんどは、北軍の前線堡塁に到達する前に、大混乱をきたし、ほとんど至近距離による大量殺戮に近い状態と化していた。投入歩兵の半分以上が斃れた。
(映画の1シーン~ピケットの突撃の最深部、前哨堡塁に突入した120人)

ここに逸話がある。ピケットの突撃が行われた戦線の中央部では、北軍の前線指揮官ハンコック少将と、南軍のアーミステッド准将(ピケット師団揮下)が、激突している。この二人は、実は南北戦争前、アメリカ陸軍がまだ分裂していなかった当時の親友である。それが、運命の皮肉か、この南北戦争最大の激戦で、しかも決勝点となりうるピケットの突撃という局面で、激突したのである。
南軍アーミステッド隊は、北軍堡塁まであと800mという地点にあった木製の柵で、いったん前進が止まっている。砲弾と銃撃が激しくなってきた地点である。相次いで斃れていく南軍兵士の有様を目の当たりにして、ようやく木製の柵という遮蔽物を前にした南軍兵士たちは、歩みを止め、怯える子供のようにうずくまった。
(映画のシーン~木柵までたどり着いた南軍師団)

中には柵を盾にして、銃による応戦をするものもあったが、完全に北軍の一斉射撃の前にすくんでしまったのである。ここからの残り800mはあまりにも遠かった。
アーミステッドは、このまま柵を盾にして応戦すれば、かえって危険だと判断した。ミニエー銃の一斉射撃では、弾丸が回転する方式であるため、薄い板塀など連射されているうちに、見る影もなく破壊されてしまうだろう。
(木柵周辺に横たわる南軍兵士の屍~実際の戦闘後の写真)

時間の経過とともに、これでは壊滅するからである。そこで、彼は軍帽をサーベルで突き刺して高く掲げ、「バージニア人よ。残りたければ残ってもよい。俺とともについてこれるものは、ついてこい!」
(アーミステッド准将)
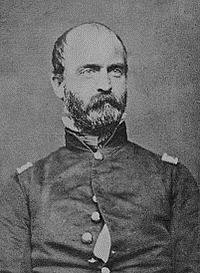
彼の率いていた部隊は、ほとんどがバージニア州人であった。彼らはアーミステッドに従い、柵を乗り越え、再び横隊を編成して前進を始めた。この一隊は、最終的に北軍の最前線の堡塁に突入した、唯一の120人である。
(軍帽を掲げるアーミステッド准将)
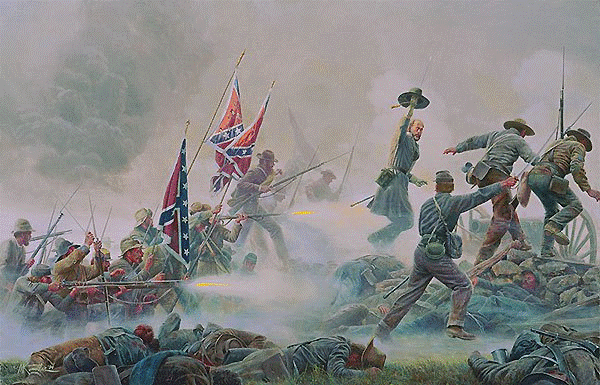
このアーミステッドに従ったわずか120人だけが、北軍最前線の堡塁に突入している。アーミステッドは、そこで3発被弾して斃れた。語り伝えられているところでは、アーミステッドはフリーメイソンのメンバーだったということだ。フリーメイソンの間で通じる、「救護要請」の合図(身振り)をしたそうだ。
ちょうど乱戦の中、北軍大尉のヘンリー・H・ビンガムがやはりフリーメイソンだった。(後に高名な連邦議員になる)ビンガムは、堡塁に到達した南軍兵士たちのほとんどが殺戮され、あるいは敗走する中で、アーミステッドの介抱を申し出た。ビンガムは、アーミステッドに「ハンコック将軍が、この防御陣で指揮していたが、ちょうどさきほど流れ弾に当たって重傷を負ったところです」と伝えた。
それを聞いたアーミステッドは、号泣して許しを請うたという。ハンコックが死ぬのではないか、と悲観したのだろう。自身は、3発被弾とはいえ、致命傷を受けたわけではなかったのだ。その後アーミステッドは近隣のスパングラー農園に収容され、治療を受けたが、敗血症と熱中症を併発し、2日後に死亡した。
かつて、南北戦争開戦にあたって、ハンコックたちは、アーミステッドのために決別のパーティを開いたことがある。アーミステッドはそのとき、「もし、戦闘でハンコックに対して手をかけるようなことがあれば、神が私に死を給う」と告げている。その予言は成就したことになる。
(北軍陣地側からみた戦場跡)

大砲の向こうに北軍の前哨堡塁が見える。北軍の最前線である。そのすぐそばに、白い石造りの記念碑(中央右)が見える。これが、アーミステッド准将の一隊が到達した、南軍としては攻撃の最深部である。ここで、アーミステッド准将は被弾して倒れた。さらに遠くに白い木柵が見える。一番向こうの森で、南軍は横隊編成を整え、ひたすらこちらに前進してきたことになる。
(北軍陣地後方から見た写真。手前で射撃している北軍横隊のところが前哨堡塁。南軍師団のいくつかの横隊集団が波状的に押し寄せてくるのがわかる、ずっと向こうに南軍砲兵隊が見える)
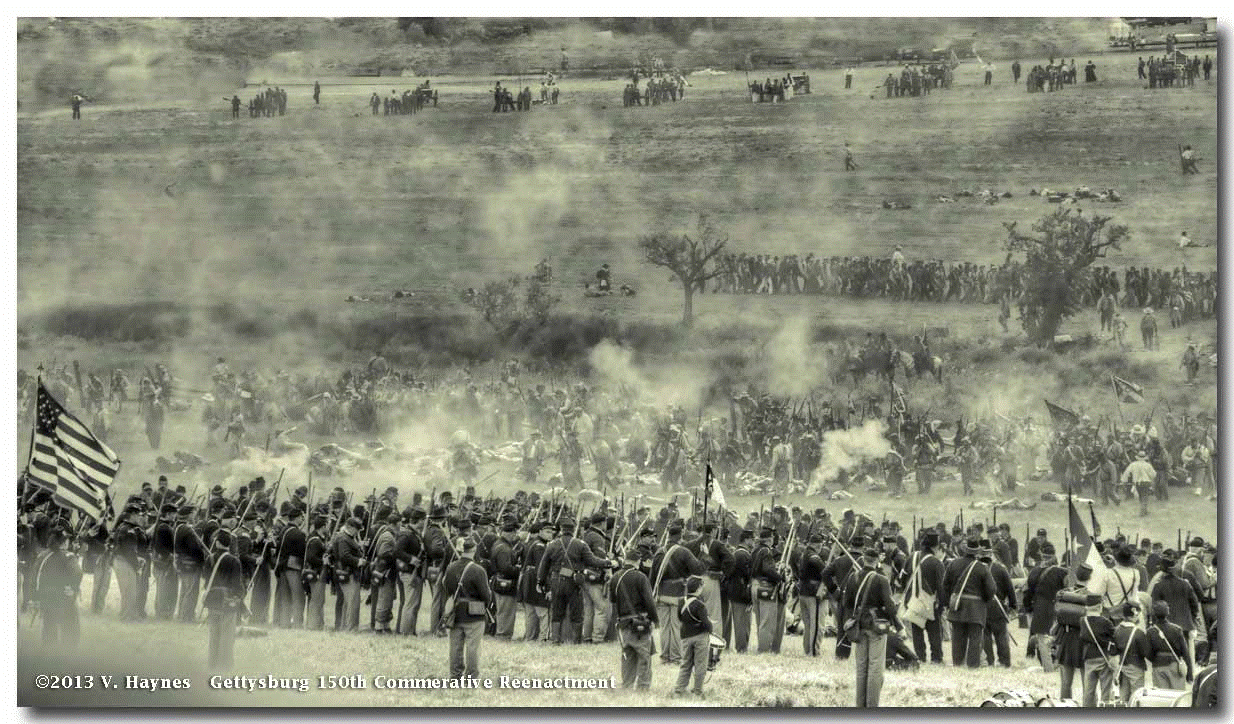
ハンコックは、ピケットの突撃前に南軍が行った全弾打ち尽くすほどの猛烈な砲撃に対して、最前線にあって馬上で睥睨(へいげい)しており、部下から抗議された。
「将軍、軍団指揮官はそのように命を危険にさらすべきではない」
「軍団指揮官の命が換えみられない時もある」
このハンコックの返事はあまりにも有名である。実際、部下の懸念通り、銃弾が右内股に入り、木片や釘などとともに深手となった。止血帯で処置を施された後、先のビンガム大尉から、アーミステッドが致命傷を負ったという知らせを受けた。ハンコックは、自身重傷であったが、戦闘の決着がつくまで後方に下がるよう部下から強いられたが、これを拒否。最後まで前線にとどまった。
(ハンコック少将)

ちなみに、ハンコックは、その高潔さと誠実さで栄達。南北戦争後は、共和党から大統領選に立候補しており、ガーフィールド候補(民主党)と、歴史上最小の票差で敗退している。
さて、ゲティスバーグでは、ピケットは歩兵師団の後方に位置していたため、ほとんどの将官たちが戦死した中では例外的に無傷だった。彼の階級と立場から言えば正確に軍法通りであり、後方にいたことは、決して非難されるべきものではない。
三々五々撤退してきた南軍兵士たちを迎えたピケットは茫然とするばかりだった。大部分のバージニア兵を失ったピケットのありさまは、慰めようのないほどの失意に落ち込んでおり、以後、突撃を命じたリーを許すことは無かった。
(南軍戦死者)

リーは、この無残な歩兵突撃の失敗の後、それまで防戦一方だった北軍が、一気に総反撃に出てくることを恐れ、敗残兵たち呼び集めさせた。リーがピケットに、防御のためにばらばらになった師団を集合させよと言ったとき、ピケットは、「閣下、わたしにはもはや師団がありません」と答えた。
結局、北軍の反撃は無かった。3日間の戦闘で、南軍と同じくらい疲弊していたのである。ミード将軍は、陣地を維持したことで満足していた。4日、非公式の休戦となり、死体や負傷者を集めた。
このゲティスバーグにおける、リー将軍の意図について、本当のところなんだったのか、なぜ、あの段階で、砲兵隊の支援ができない状況にもかかわらず(砲弾枯渇)、歩兵の密集隊形で突撃を命じたのか。ほんとうに砲撃で相当のダメージを北軍が被っていると誤認したのか。いつもは曖昧な命令形式なのに、なぜこのときだけ断固として突撃を命じ、幕僚が公然と反対したにもかかわらず、これを固辞したのか。すべては闇の中である。
リー自身は、戦後、自叙伝を出版することは無かった。ゲティスバーグ戦の各前線将校たちによる戦闘報告書も、突撃を実際に行った上級士官のほとんどが戦死しており、報告書そのものが無かった。
ピケットの報告書は、明かにあまりにも苦渋に満ちたものであったらしく、徹底的な否定と批判に溢れていた。リーは、この報告書の受け取りを拒否し、訂正を命じたが、ピケットは納得せず、結局リーはそれを廃棄するよう命じ、その写しも発見されていない。ピケット自身、その後、このときの無残な突撃に、自分の名が冠され、「ピケットの突撃、Picket Charge」と呼ばれることを、終生忌み嫌った。
同じようなことが、53年後、1916年に起こっている。第一次大戦中の西部戦線、ソンムの戦いである。すでにドイツ軍と、英仏連合軍は、開戦から3年目、塹壕戦による膠着状態に陥っていた。
その膠着を打破しようと、連合軍はソンムで大攻勢をかける。奇しくも、ゲティスバーグの戦いと同じ、7月1日の朝だった。どうも7月1日というのは鬼門のようだ。1939年にはノモンハン事件で、日本軍が悲惨な対ソ戦を経験している。1942年には北アフリカ戦線で、ドイツのロンメル将軍が率いる無敵の機甲師団が、敗退している。
連合軍は、周到な準備の下、6月5日から砲撃を開始し、ドイツ軍を圧倒していた。まず第一陣地を破壊し、第二陣地の砲撃は、6日間も続けられた。飛行機も援護して、ドイツ軍陣地の後方を攪乱した。
7月1日早朝、英仏両軍の歩兵は援護砲撃と連携しながら、塹壕を出て前進した。しかし、この近代戦においても、結局ゲティスバーグと同じ過ちを犯している。ドイツ軍は致命的なダメージを被っていなかったのである。ドイツ軍の防衛陣地が多重防御を備えた強固なものだったのだ。
しかもゲティスバーグと同じく、歩兵たちは徒歩で前進していったのだ。司令部は、砲撃でドイツ軍は壊滅しているから、ピクニックにいくようなつもりで歩いて行って、占領すればよい、と公言していたくらいである。
ドイツ軍兵士のこのときの手記にも、「敵兵は、まるで散歩にでも出かけるように歩いてきた。われわれは、狙いも定めずにかたっぱしから撃ち倒すことができた」と書いている。
結果、英軍はドイツ軍の防衛ラインを突破するどころか、そこまでたどり着かないうちに、わずか数十分のうちに、7万人以上を失った。攻撃に参加した歩兵の91%に相当する。つまり、壊滅である。うち戦死は2万人を数える。これは第一次大戦において、一日で発生した戦死者数としては最大である。
ナポレオン戦争の最終戦、ワーテルローでは、英軍歩兵はもはや抵抗力を失っているとの判断から、ナポレオンは無謀にも近衛兵の密集隊形での総攻撃を仕掛けた。丘陵の反対斜面にはいつくばって待機していた英軍歩兵軍団は、一斉に立ち上がってフランス近衛兵を射撃し圧倒した。48年後のゲティスバーグ、そこから53年後のソンム。兵器の進歩は著しいものがあったが、まったく変わらなかったのは、無残な密集歩兵の突撃と壊滅、砲撃による支援効果が不完全な中での攻撃という二点である。そしてその共通した原因は、指揮官の誤断である。
百年の間に、人間は同じ失敗を3回、それも歴史に残る恥辱的な失敗を繰り返したことになる。歴史というの一見すると、似たようなことが繰り返されている。しかし、同じことは二度とない。しかし、わたしたちは過ちを犯すとき、そのほとんどは、いつも同じ過ちなのである。
ワーテルローのナポレオンも、ゲティスバーグのリーも、ソンムのヘイグ(英軍)やフォッシュ(仏軍)も、みな致命的な過ちを犯している。それは、敵情判断の誤認と、それによる無謀な総攻撃である。かつて、野村克也監督が名言を吐いている。
「勝ちに不思議の勝ちあり。負けに不思議の負けなし。」
勝つときには偶然の勝利ということもあるだろう。しかし、敗北には、それはない。必ず合理的な要因がある。不合理な判断ということだ。