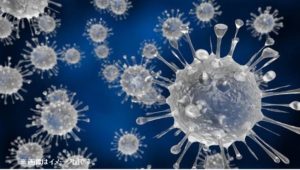市場は、何のために存在するのか?

これは442回目。昨日、10月1日は、歴史上初のシステム・ダウンによる東京証券取引所の終日売買停止となりました。あらためて、市場というものは何のためにあるのか、それを考えてみましょう。上の写真は、オランダ東インド会社の株券だそうです。
:::
世界に名高いNY証券取引所(NYSE)は、1792年、24人の商人と競売人が集まり、現在のウォール街に当たる場所で始まった。
彼らは、毎日「鈴懸(すずかけ)」の木の下に集い、証券取引を行い合うことを誓った。世にいう、「鈴懸の木の協定」である。
以来、銘柄も増え、やがて公式の指数が登場する。
1884年のことだ。明治16年である。西南戦争が終わってまだ6年。
日清戦争の10年も前である。
ダウ輸送株指数といい、これがチャールズ・ダウが発案した最初の指数だった。わずか11銘柄だった。
構成銘柄は物流を担う企業ばかりで、鉄道株はその代表的なものだった。なぜチャールズ・ダウがこの業種に最大の関心を寄せたのかというと、物流の増減こそが、景気循環の先行指標だと見抜いたからにほかならない。
経済は景気である。
景気とは、公式化すれば畢竟、数量X値段である。
そしてこの2つの構成要素のうち、最初に動くのは、数量であり、値段は後からついてくる。
たとえば、景気が良くなっていくとしよう。
まずそれまでの不況期に溜まった在庫を減らすことから始まる。
社会に需要が出始めたら、この在庫から物品が売られていくのだ。
この時点では値段は変わらない。在庫処理をしたい業者は、値段が安くても構わないと思うからだ。
在庫を抱えて倉庫料がかかるほうが恐ろしい。無駄なことだ。
だから、値段は安いままであまり変わらないが、在庫から出てきて世の中に出回る物流量だけは増大してくる。
しかし、だんだん景気が温まってくると、在庫もそのうち無くなってくる。
そして払底する。
今度は作らなければならなくなる。
そこからは生産が始まる。在庫処理をしていたときより、遥かに需要される物品の数量が増大するのだ。
そこからようやく値段が上がり始めるのだ。
このように、数量→値段で、景気がスタートを切ったことがわかる。
チャールズ・ダウはここに着眼して、ダウ輸送株指数を最初につくったのだ。
世に有名なダウ工業株指数ができたのは、1896年。
輸送株指数に遅れること12年。日露戦争が終わった翌年である。
以来、ダウ工業株はアメリカが世界の中心軸になっていくにつれて、アメリカのみならず、世界の株価指数のベンチマークとなっていった。
発足以来、この指数は現在まででは変質しているため、連続性が何度か絶たれている。
史上最悪の暴落となった1929年の大恐慌のときの安値、1932年41.22ドルを起点とすると、昨晩2020年10月1日の終値は27816.9ドル。
つまり、88年間で674倍になったことになる。
インフレ率など知れているから、とんでもない資産膨張だ。
債券や、商品市況、不動産ではとてもこれだけの倍率にはならない。
その株式市場が、昨日(2020年10月1日)に、なんとシステム・ダウンで一日中売買停止となったのだから、たまらない。
なにがたまらないのだろうか?
売れない、という大問題が発生するからだ。
株式市場とは、一体なんのためにあるとお思いだろうか?
買うためだろうか?
なにかの銘柄を買って、値上がりを期待するためだろうか?
そうではない。
そもそも株式市場ができた最初の事例にさかのぼってみれば、その意味がよくわかる。
それは、17世紀初頭の東インド会社からだというのは、あまりにも有名な話だ。
アジアの香辛料を奪いに、大量の艦隊が組織された。
水夫はもちろん、医者や学者、護衛する戦闘船団など、コストは大変なものである。
しかも、最短でも1年は往復にかかってしまう。
しかし、何隻か難破して帰ってくることができなかったとしても、わずかな艦船の帰還だけで、膨大な利益をもたらす。
そのため、大船団を組織するのに投資が呼びかけられた。
その投資に見合う証文が発行され、ここに株式会社が誕生することになったわけだ。
さて、そこで問題が生じる。
1年で帰って来れれば良いが、2年かかるかもしれない。
一体、いつ自分の株券は換金できるのだろうか?
株主たちは、それまでの長い期間に、本業や私的なことで支出しなければならないことが出てくる。
船団が戻るまで、待っていれば、大きな利益が得られるが、そこまで待てない事情だとしたら?
そこで、手持ちの株券を売りたい需要が発生してきた。このようにして、いつでも売り出して換金するために、市場が生まれた。
だから、株式市場の本来的な意味は、買うためではない。
売るためなのだ。
これを現在の投資にまで敷衍して考えると、なかなか売れない、売りにくい(出来高が少ないなどの理由で)市場には、投資してはならないということになる。
だから、昨日の東京市場のように、終日システム・ダウンで売買できないということは、とんでもない事件なのである。
市場が、その付託に応えることができなかったのだ。
株主たちは、自分の本業で数日後になにかの支払いをしなければならない人たちがいるのだ。それが仕事上のものであれ、私的なものであれだ。
不動産を持っていても、すぐに売ることなどできないではないか。換金性が致命的に低いからだ。
株は、その点、かならず3日後には換金できる。株価がそのとき高いか安いかなど、その人にとってはどうでもいいことなのだ。とにかく換金する必要があるのだ。
それが売れない、ということになったら、どうする?
場合によっては、破綻するかもしれないケースも出てくるだろう。債務不履行になるからだ。
だから、この事件は絶対に二度と起こしてはならないのだ。
かつて、1987年に、ブラックマンデーという暴落が発生した。
そのとき、日本では、軒並みストップ安で値段がつかず、ほとんど売買が成立しなかった。そういう意味では、売りたい需要に応えることができなかったのだから、まだ未熟な市場だったということだろう。
同じ時、香港市場では暴落の恐怖に怯え、取引所は3日間、取引を強制的に停止した。人為的にである。言語道断と言っていい。だれにそんな権利があるのだ。
このブラックマンデーでNYはどうだったろうか?
暴落当日の夕方、相場が終わった後に、取引所の代表がスピーチを行った。未だに名演説と言われている名高いものだ。
「今日、NY市場は暴落した。大変残念なことだった。しかし、たった一つだけ、良かったと思えることがある。それは出来高(売買件数、株数、代金)は史上最大だったことだ。少なくとも市場の付託に応えることができたことは、なにより幸いだったと思う。」
だから、株式投資では、「売れないものに投資をするな」という大原則は、17世紀から語り継がれてきた奥義と言っても良い。
投資理論には、こうした大原則がいくつかある。
このほかにも、「徴税能力の無い国家には、投資してはならない」という不文律もあるのだ。
それを専業としている機関投資家は、そうも言っていられないが、純然たる個人投資家の場合は、厳に守るだけの意義はある。
たとえば、中国である。
徴税能力は無い。
税金というものがそもそもほとんど無いに等しかったからだ。
それはそうだろう。
共産主義国家ゆえである。
革命で、旧政権、旧財閥、旧地主たちから、資産をすべて没収し、それを使っていたので、徴税する必要性もなかったのだ。
しかし時代が下るにつれて、そうもいかなくなった。
当然なんらかの口実をつけて、税金を掛け始めたものの、西側にくらべてそれはきわめて軽微である。
だから、2-3年前のデータだが、中国の全税収に占める個人所得税収はわずか8%にとどまっている。
しかも、中国では、税逃れをしていても、咎められるわけではないと、当たり前のようなコンセンサスが一般国民にあるのだ。驚きだろう。
5年前などは、個人所得税を収めたのは、全人口の2%にすぎないというデータも明らかになっている。
しかし、共産主義国家になる前から、基本的に中国というのは徴税能力が無い社会なのだ。
国と国民は、常に互いに騙し合い、それで一種の均衡が取れているという恐ろしい社会なのである。
ここに、不正・汚職の温床がある。
脱税のやりたい放題、それが中国だ。
なぜなら、国民の間に、政府が税収を賢く使うことは無い、という徹底的な不信感が根付いた社会だからにほかならない。
一帯一路などという、貧困国に金をばらまく政府のやり方にも、国民はなぜ、自分から税金を取って、そんなところに金をばらまくのだ。
自分に、なんの得があるのだ、と思う。
だから、政府も暗黙の了解で、脱税にどうしても甘くなる。
これが共産国家・中国の税を巡る微妙な均衡なのである。
もし、中共政府が徴税を強行するとどういうことになるだろうか?
国民は、「税金を払う以上、その目的・使途、方法論、結果や収支」を開示し、説明することを当然ながら政府に要求することになる。
それが、資本主義の原理だ。
中共はそこには恐ろしくて踏み込めない。
共産主義体制が一気に瓦解してまうからだ。
資本主義を認めるということは、民主主義を認めることにそのまま直結してしまうからだ。
中共は、歴史的にも税というものに恐怖を感じている。
かつて、彼らが倒した蒋介石・国民党政府は、なんで崩壊し、台湾に逃亡する羽目に陥ったのか?
いろいろな理由はある。
が、経済的には、塩に課税したことが直接的に国民の支持を完全喪失した原因だったことを、共産党は身にしみている。
だから、中国には永遠に徴税能力は育たない。
そんな国に、生産拠点をつくるにしろ、販路を拡大するにしろ、金融投資をするにしろ、マネーをつぎ込むことは、ほぼ自殺行為だという結論になる。
中国国民はそれに気づくだろうか。
気づけば、革命が起こる。
気づかなければ、国外に脱出する。
どちらにしても、波乱は必至だということだ。