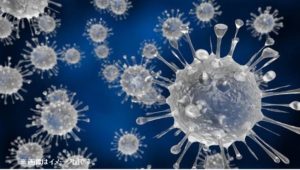消えゆく蒼き狼の子孫たち

これは440回目。
内モンゴルの話だ。掲題の写真は、かつてわたしが半年に一度は訪れていた、霍林河というところだ。露天掘り鉱山で有名だが、廃鉱となったあたりの跡地が緑地化された様子だ。
その内モンゴルが、今悲劇の舞台と化し始めている。
法輪功学習者の絶滅、香港の人権弾圧、ウイグルの民族浄化、続いてこんどは内モンゴルだ。中共の民族同化政策はとどまることを知らない。
モンゴルは2つに分かれている。
一つはモンゴル人民共和国だが、これは中国側から見たら外側にあるので、外モンゴルと読んでいる。内側、つまり中国領土内のモンゴル地区は内モンゴルと中国人が呼んでいるのだ。
モンゴル人民共和国は、長らくソ連の事実上の属国扱いだったから、ロシア語のキリル文字でモンゴル語を書いていた。それがソ連崩壊、ロシアも頼りにならず、ついにナショナリズムに目覚めたのか、彼らの伝統的なウイグル文字を使い始めた。
母国がそうであるから、中国領内の内モンゴルのモンゴル人たちもそれにならった。
それが中共には気に食わなかったらしい。
学校教育におけるモンゴル語、モンゴル文字の廃止を進めている。
モンゴルの歴史は破棄、中国の歴史だけを教え始めた。
これがモンゴル人の反感を買い、ほぼ90%の内モンゴルの学校では親の意向で登校拒否となり、事実上学校教育はストップしている。
この「事件」が国際社会でやり玉に上げられた。中共の説明は、「モンゴル語やウイグル文字の廃止などしていない。中国語を学び、バイリンガルになってほしいだけだ」としている。
誰もそんなことを信じない。チベットで、ウイグルで、中共は同じように少数民族の言葉と文字と歴史を奪ってきた前科があるからだ。
内モンゴルは、わたしにとっては遠い世界ではない。大学を出て就職した会社で、中国担当となったから、一年のうちほぼ250日は中国大陸の鉱山現場をドサ回りしていた。
後、香港に一人事務所を構えて、そこから同じように大陸でのドサ回りが続いた。香港に返ってくるのは、給料を取りに帰るときだけだ。一週間もすれば、また大陸に舞い戻る。
大陸で5kg痩せ、香港で5kg回復し、また大陸で5kg痩せるという繰り返しだった。
1980年代前半、食うものが無かったのだ。
内モンゴルには、霍林河(huo lin he)という露天掘りの炭鉱がある。わたしたちは日本語で、「かりんが」と呼んでいたが。
北京から夜行で通了(tong liao)まで行く。ただ、大抵の場合、通了で降りず、名もない、駅舎すらない、真っ暗闇の草原のまっただなかで降ろされた。
たぶん通了より、その地点のほうが炭鉱に近かったためなのだろう。星空は満天に散りばめられ、夏は見事な風情だった。
汽車はやがて出ていった。商社の相棒と二人で大量の荷物といっしょに鉄路脇の草原に佇んで、夜空を満喫していると、そのうち暗い草原のかなたから車のライトとおぼしく光が見え隠れしくる。
解放軍のジープがわたしたちを迎えにきたのだ。
そのジープ何台かに荷物と分乗して、こんどは延々と草原を走り抜ける。
(霍林河の丘陵地帯)

緩やかな緑豊かな草原を走ること、6-7時間。夏の豪雨で、洪水となったときには、12時間かかった。
道が無くなってしまうからだ。
霍林河の炭鉱は、当時キャタピラーや小松の大型ダンプが疾走しており、そのタイヤの使用状況のチェックをして、サンプルタイヤの要求性能を測るのが主な仕事だった。
(ダンプ用タイヤの内側を覗き込んでいる米粒のようなのが、わたし)
中国山東省2-300x210.jpg)
一日中、ジープに乗って、ダンプを追いかけ回し、積載重量の測定、満載時の走行速度と距離、ワインディングや傾斜、路面の状況、ダンピングした後、空になったダンプの走行速度・・・要するにタイヤが破壊されるとき、カットでやられるのか、ヒートでやられるのかを見極めるのだ。
(往年の霍林河炭鉱)

霍林河の石炭は、せいぜい発熱量が1kg当たり、3000kcalしかない。5000-7000kcalないと話にならないのだ。つまり、油をかけなけば燃えないといっても過言なくらい、劣る石炭だ。
しかし、当時中国は開放経済が始まったばかりで、明るい明日に向かって重厚長大産業優先で驀進し始めたときだ。一般家庭でも大量の石炭が暖房に使われていた。
冬の霍林河は零下30度に下がるから、二重窓もほとんど役に立たない。朝になるとガラスの間に氷柱ができていて一驚したこともある。
一度などは、ボイラーがぶっ壊れてしまっており、ももひきからなにからありとあらゆるものを着込み、軍大衣(ジュン・ダー・イー、軍用の綿入れコート)にくるまって、布団をかぶって一晩明かしたこともある。
(1986年冬、軍大衣を着た28歳のわたし、霍林河にて)
中国-内モンゴル-300x202.jpg)
夏は爽快だ。夜9時に美しい夕焼けが草原の果てに消えていくのをあかず眺めたものだ。
土煙を上げて疾走するダンプ。まさにその後塵を拝した一日の終わり。
食い物といったら、羊しかない。米が食えたらラッキーだ。たいていは、ばさばさの饅頭(まんとう)だ。当然中には何もはいっていない。
料理の油はかなり傷んでいる。慣れないとすぐに腹を壊した。
味つけなどほとんど無いか、塩っ辛すぎて食えない。要するに、料理人たちが味を見ないでつくっていたのだ。万事適当にやっていたから、無味であったり、やたら塩っ辛かったり、どうにもまともな味付けのものに出会わなかった。
味がないときには、いつも醤油を持っていってぶっかけて食った。醤油の持ち合わせが無いときには、現地の黒酢をぶっかけ、ごまかして食った。
塩辛すぎるときには、いったん水につけて塩分を抜いてから、食い直した。招待処の厨房は時間制で早々と閉まってしまうので、いつもこういときにはキャンプ用のガスバーナーでもう一回熱して食った。
野菜など皆無に等しい。たまに、にんにくの茎の炒めものが出たくらいのものだった。
働いている漢人たちはみな純朴だった。日曜日にはいつも遠出に誘ってくれたものだ。モンゴル人はいるにはいたが、炭鉱で働いている人には少なかった。牧畜が多かったようだ。
招待処の受付や、給仕などにはモンゴル人が比較的多く混じっていたように記憶している。
漢人の作業者たちが、最初にわたしを誘ってくれたときというのは、わたしのことをあることで気の毒に思ったかららしい。
ちょうど前夜の豪雨で、現場に鉄砲水が走り、作業中のわたしたちは襲われた。運良く脱出できたが、下半身はいったん濁流や泥水に埋もれた。そのとき、安全靴の片方が脱げてしまい、流されてしまったのだ。
わたしはやむなく、普段用のスニーカーを代用せざるをえなかった。鉄板の入った安全靴でないと、やはり現場は危ない。スニーカーは厳禁だが、致し方なかった。
漢人たちがそれで晴れた最初の日曜日、わたしを誘ってくれたのだが、なんと狼狩りだという。
モンゴル人たちにとって狼は神と同じだ。ジンギスカンも蒼き狼と呼ばれ、彼らはその子孫であることを誇りにしていた。
ただ、狼が家畜を襲うときだけは、狩りをしていたようだ。
漢人たちはただの遊びである。気晴らしで狼を狩っていたのだ。わたしはそんなことをよく知らずに、物見遊山でついていった。何時間も一定の場所で待ち続け、ようやく彼らは一頭の狼をしとめた。
記念にといって、その見事なほどふさふさの尾を切り取って乾燥させ、「車の刷毛(はけ)にでもしろよ」とくれた。
後で、湿度の高い日本の夏に返ってきたら、あっというまに腐り、とんでもない臭気に悩まされたので、結局捨てた。
狼には可哀想なことをしたとつくづく思う。ただの遊びで殺されたのだ。漢人たちも悪気があったわけではない。陸の孤島に放り出されて、四班三交替で24時間石炭塗れの一生を送っているのだ。
内モンゴルの狼は今、どうなっているだろう?
おそらく絶滅に近いだろう。
そして今、狼だけではない。その子孫を自認するモンゴル人そのものが、あの美しい草原から消え去ろうとしている。中共による漢人生存圏の飽くなき拡大・膨張である。かつてのドイツ第三帝国によるゲルマン民族生存圏を彷彿とさせるおぞましいイデオロギーだ。
そして、日本人も、リベラルという人権重視を謳う人たちも、みなその悲壮な現実を見て見ぬ振りをするのだろう。
法輪功学習者、チベット人、香港人、ウイグル人に対して取ったのと同じ態度で、モンゴル人の悲劇はまるで存在しないかのように振る舞うのだろう。
日本と日本人は、やがて、自分たちも同じように、多くの西側諸国から「見て見ぬ振りをされる」ことに気づく。
そのときには、もうすでに遅すぎるに違いない。
気づくなら、今だ。
ところで、わたしの安全靴の片方は、今頃内モンゴルのどの当たりで土砂に埋もれているのだろう。