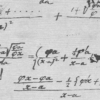誰もが「李陵」だ

誰もが李陵だ。
これは463回目。
凡人の話だ。
多少、才能があったところで、凡人はただの凡人。
才能の良し悪しなど、どうでもよいくらい些末なことだ。
凡人と非凡を分ける差はなにか?
精神力のようだ。
中島敦という小説家がいた。
作風は、読めばわかる通り、芥川龍之介の作品に非常に似たものを感じる人が多い。
口の悪い人は、中島敦は芥川文学の亜流だとすら言う。
戦後ずいぶんと評価が変わり、亜流どころか、芥川を遥かに凌ぐ高い文学性を有するとさえ評価する人もでてきている。
わたしもその一人だろうか。
文学といい、小説というものを読む人が、娯楽性に幸福感を味わい、いくばくかでも生きるための知恵を得ることを求めているのだとすれば、芥川などの比ではないとすら思える。
人間誰しも抗いがたい運命に弄ばれる。
その回避は不可能である。
しかし、危機に直面したとき、なにが一番重要なのか。
わたしたちが捨ててはいけないものとは何なのか。
中島の名作の一つに『李陵』というのがある。
漢代の実在の武将だ。
悲運の武将ということで知られる。
匈奴との戦いで、武王の重用する李陵は、その優秀さゆえなかなか最前線に派遣されない。
李陵本人は不満である。
輜重隊ばかりを任されるのだ。
直訴して、前線に送ってもらえることになった。
5000の兵を率いて、最前線で苦戦する漢軍本隊へと合流を急ぐ。
途中、匈奴と遭遇し、3万の大軍を一時は駆逐する。
が、波状的な攻撃にさらされ、ついに矢が尽き、敗退。
降伏して、捕虜となる。
このとき、李陵は2つの選択肢の間で悩む。
いまはこれまでと自刎して果てるか。
それとも、一旦敵に降り、気を見て脱走するか。
李陵は後者を選択した。
匈奴の勢いは凄まじく、その後漢軍は負け戦が続く。
漢では、「とうやら李陵が裏切ったらしい。李陵は匈奴軍に参加して、対漢軍戦の作戦に助言している」という噂が広まる。
武王は怒り、李陵の家族をひとり残らず処刑する。
唯一、朝廷にあっては、学者の司馬遷が李陵を擁護したが、これが武王の臣下たちの讒言に遭い、宮刑(強制的に宦官にさせらる。生殖器切除の刑。)を処されるというあまりといえば、あまりの醜刑の憂き目に遭う。
家族を失った李陵は、漢軍以外の敵に対しては、匈奴のために尽力し、王や将軍たちとも親しくなる。
実は匈奴には、ほかにも漢人の捕虜がいた。
蘇武という。
かれは、敗戦した際に、自ら胸を突き、自決しようとした。
が、匈奴たちによって一命を救われた。
勇者ぶりは高く評価された人物だっただけに、匈奴からは味方になるよう勧められたが、蘇武はあくまで辞退し、荒野で困窮を極める生活に甘んじた。
李陵は、自分のように蘇武に、「匈奴へ恭順せよ」と勧めるが、蘇武は硬骨漢だ。
絶対に漢を裏切らない。
そのため、匈奴から嫌がらせを受けたりして、さんざんな目に遭い続ける。
李陵は陰ながら、食料などを送り届け、蘇武を支えた。
やがて、武王が逝去した。
匈奴の捕虜となった漢人将兵たちに、漢に戻らぬかと誘いがくる。
李陵は、いまさらなんで故郷に帰れるものか、家族もいない、心は懐かしい祖国に今にも舞い戻りたい思いで満ちるが、結局彼は戻らない。
蘇武は、国へ帰っていった。
蘇武とて、決して幸福ではない。
捕虜になっていた長い間に、妻は他の男に嫁していた。
実母は死んでいた。
帰国してからも、ある事件に巻き込まれたことから、息子は処刑されてしまう。
一体何が幸福で、なにが不幸かはわからない。
一見すると、蘇武は本能で動く直情径行、李陵は理性を働かせて考える人物という対比に見える。
中島敦の作品にはこうした対比が多い。
たとえば、『悟浄歎異』の沙悟浄と、孫悟空の関係も同じだ。
中島自身が、李陵や沙悟浄と自らを重ね合わせているのかもしれない。
『弟子』の中でも、考える孔子に対して、行動の人・子路を対比させる。
しかし、この『李陵』の中で、最も悲惨な悲運をかこつこととなったのは、司馬遷である。
宮刑という、ありえないほど恥辱的な仕打ちを受けるのだ。
そして、生涯全精力を傾けて、いまだかつてなかった大歴史書『史記』を書き上げていく。
中島敦が憧れたのは、李陵や孔子や沙悟浄のような思考の人間像ではない。
彼らは、優れているかもしれないし、理性的で、知恵をよく働かせたかもしれない。
しかし、凡庸な精神力なのである。
李陵、孔子、沙悟浄と、中島敦の描いた彼自身を投影した登場人物はみな、才能はあるものの、中身がない、ダメさ加減がちょうどいい賢人たちなのだ。
誰もが自分の理想とするありかたに、自分自身を追い込み、はめ込もうとする。
そこに本心はない。
しかし、蘇武、子路、悟空は、(たとえば、「義に殉じる」といったように)一見すると、短慮で直情径行に見えるが、どうしてどうして、それ以外に自分の善と幸福を全うする選択はないというものに、命がけで身を委ねる。
硬骨漢を言えば、それまでだが、それを非難する人たちは、そうした一徹な選択に身を委ねる情熱も勇気も無い人たちと決まっている。
わたしを含めて、多くの人間は、みな「李陵」なのである。
その選択によって、世間的な意味での「良い結果、喜ばしい結末」を迎えられるかどうかは、この際問題ではない。
人間が、どう生きるべきか、選択するべきかを、『李陵』は問うている。
わたしたちは、抗いがたい運命に襲われたとき、あるいはなんらかの錯誤によりそうした窮地に陥ったとき、李陵の選択をするのか?
それともあくまで蘇武や司馬遷の選択を取るのか?
それが中島作品では執拗に問いかけられる。