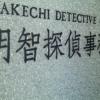いのちの叫び

これは191回目。非常に複雑な思いにかられる文学というものがあります。
わたしの場合、そうした作家の多くは自殺している。書き残した作品は、あまりにも魅力的であり、多くのことをわたしに投げかけるのだが、本人の実際の生き方にはどうしても納得がいかない、あるいは微妙に釈然としない思いに駆られるのです。
:::
有島武郎もその一人だ。軽井沢の人の別荘で、愛人と縊死。6月に死んで、管理人によって7月に発見されたので、どういう状態だったか想像に難くない。
愛人には夫がいて、彼から脅迫されたのが直接的な動機だったようだ。この人生の終わり方というのは、どういうことなんだろうか。やはり納得がいかないのだ。
生きざま、死にざまと作品とは、別個であって別個ではない。太宰治にもこのことは当てはまる。芥川龍之介もそうだ。三島由紀夫もそうだ。ヘミングウェーも同様である。まったく好きではないが、川端康成もそうだ。生きざまというのは、多くはその死にざまとも通じる。この作家たちはすべて自殺である。
しかし、自殺した作家の書き残したものこそ、逆に言えばほんとうはこうでありたかったという命の叫びのようなものが凝縮されているのかもしれない。そう考えると、その生きざまや死にざまにどうしても納得がいかなくても、心を震わせるなにかがあるのかもしれない。
作家を理解する上での、この大きな壁については一応横に置いて、もしかしたらその命の叫びのようなものを、一つ挙げてみよう。
『小さきものへ(有島武郎』から抜粋
お前たちをどんなに深く愛したものが
この世にいるか、或はいたかという事実は、
永久にお前たちに必要なものだと
私は思うのだ
私はお前たちを愛した。そして永遠に愛する・・・
お前たちの若々しい力は
既に下り坂に向おうとする私などに
煩わされていてはならない。
斃れた親を喰い尽して力を貯える
獅子の子のように、力強く勇ましく
私を振り捨てて人生に乗り出して行くがいい・・・
私の一生が如何に失敗であろうとも、
又私が如何なる誘惑に打負けようとも、
お前たちは私の足跡に不純な何者をも
見出し得ないだけの事はする。
きっとする。
お前たちは私の斃れた所から
新しく歩み出さねばならないのだ・・・
不幸なそして同時に幸福な
お前たちの父と母との祝福を胸にしめて
人の世の旅に登れ。
前途は遠い。そして暗い。
然し恐れてはならぬ。
恐れない者の前に道は開ける。
行け。勇んで。小さき者よ
ここに有島武夫の真実があったとするなら、その人生の終わり方はあまりにも釈然としないのだ。言葉は悪いが、そういったこと以前に、もっと自分に図太くても良かったのかもしれない。
感受性が強く、繊細であればあるほど、一番大事な自分というものを支えることができなくなる。有島武郎のような結末を、とても肯定できないものの、一方では言うに言われぬ共感を覚えてしまう自分が、確かにいる。
しかし、そんな自分にぐさりと心臓に突き刺さるような詩を書いておく。感受性だとか、繊細だとか、優しさとか、知ったふうなことを言う前に、「お前はそもそも自分の足で立っていないじゃないか」と鋭く糾弾されているような気がするのだ。
『自分の感受性くらい(茨木のり子)』
ぱさぱさに乾いてゆく心を
ひとのせいにはするな
みずから水やりを怠っておいて気難しくなってきたのを
友人のせいにはするな
しなやかさを失ったのはどちらなのか苛立つのを
近親のせいにはするな
なにもかも下手だったのはわたくし初心消えかかるのを
暮らしのせいにはするな
そもそもが ひよわな志しにすぎなかった駄目なことの一切を
時代のせいにはするな
わずかに光る尊厳の放棄自分の感受性くらい
自分で守れ
ばかものよ
これも、間違いなく命の叫びなのだ。