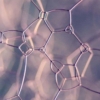こころ

これは336回目。こころはどこにあるのでしょうか。わたしたち人間存在の実態は、こころのはずです。わたしたち自身が認識する「こころ」と、そして認識しえない、わたしたちですら知らない「こころ」もあるようです。
:::
ずいぶん昔、外人に会うたびに、しつこく聞いたことがある。
「Love(愛)は、あなたの体のどこにありますか?」
この問いは、枕詞を交えず、いきなり単刀直入に聞かなければならない。考えたり、身構えたりしたら、本当の答えが出てこないからだ。
だから、いつも知り合いの外人にその日、会った最初の瞬間に、唐突に聞いた。あるいは、しばらく他愛もない話をしている途中、「ところで、Loveは君の体のどこにあるんだい?」と聞いたのだ。
多くはアメリカ人(人種はいろいろ)だが、ときに欧州人もいた。大学には結構、ドイツ人、スペイン人、イタリア人が多かったのだ。
一様に彼らの答えは、自分の頭を指して「ここにある」と答えた。ほぼ例外はなかった。
この同じ問を日本人にすると、全部ではないがほとんどのケースでは、自分の胸を指差した。
この違いは大きい。
外人は、Loveという「こころ」の代表的な作用を、頭で行っていると答えたわけだ。これに対して、日本人は「胸」にあると答えるのが普通なのだ。もちろんときに、日本人でも頭を指す人はいるが、非常に稀である。
こう解説して、果たして、あなたのLoveは体のどこにあるかと自問自答してみたら、あなたはどう答えるだろうか。頭だろうか。それとも胸だろうか。
日本人は「こころ」を非常に情緒的なものととらえているように思える。それは、ほとんど自身では制御不能の、「所与のもの」という概念なのだろう。好きか、嫌いかに近い概念である。嫌いなものを好きとは思えない。そういう事象のことである。
一方外人の場合、「こころ」は明らかに理性を指している。そこには自身の意思が反映されているのだ。
たとえば、イエスが「あなたの隣人を愛せ。あなたの敵を愛せ」と言ったが、隣人はともかく、敵など愛せるわけがない。
愛せるわけがないのに、愛せというのである。これはどうしたことか。愛というもの(こころの働きのもっとも崇高なものだ)は、憎むべき敵ですら愛することが可能だ、ということを意味している。
自分の家族を殺した犯人を愛せ、という。自分を痛くきずづけた相手を愛せ、という。好きになれといっているのではない。表現を言い換えてみれば、それは「許せ」といっているのである。
キリスト教が「許し」の宗教であるというのは、この所以だ。
これは、意思の力に全幅の信頼を寄せよ、ということでもある。憎むべき敵ですら、許すことが出来る。それが、愛なのだ、と。
一方日本人のこのこころの働きというものは、あくまで不可抗力的な、天賦のものであり、意思ではどうにもならないものという受け止め方をする。
この場合、ある意味日本人は、西洋的な愛という概念と、好き嫌いの概念を混同していると言ってもいい。曖昧なのか、同義語と誤認しているのか、このへんは諸説あるだろうが、境界線がはっきりしていないことは確かである。
では、日本人は憎むべき敵を許すことができないのだろうか。そうではない。愛と好き嫌いが不分明な精神文化だが、まったく別のアプローチで敵を許すのである。
それが「慈悲」である。文字通りだ。どんなに許しがたい、憎むべき人間であっても、その人間を前にして、あなたはごくごくわずかだが、「なんて悲しいことだろう。なぜこのようなことをする人間がいるのだろう。」という刹那が、必ずある。99%の憎悪と軽蔑で占められた心の中に、わずか1%だが、「悲しくて仕方がない」という気持ちが必ず残っている。そのたった1%の「悲しい」と思う気持ちを頼りに、許してやるのである。それが「慈悲」だ。
こうして比べてみると、外人のこころの在り方に比べると(たとえば、愛するということを教え諭すのに)、日本人のアプローチのほうが、より現実的で、具体的であることに気づく。
外人の「敵を愛することが、愛なのだ。それが許すということなのだ」とすぱっと言い切られても、なかなか人間、そうは感情がついていってくれない。
そこで日本人は、よりプラクティカルな心の在り方を進める。「悲しいって気持ちがちょっとでもあれば、それで許してやってくれ」ということだ。「許す」というこころの働きをする、手がかり、足掛かりを日本の文化というものは、示してくれる。非常にある意味、親切な、気配りのある「教え、諭し」だと言えそうだ。
この「慈悲」という言葉はもちろん、中国から来たのだが、オリジナルはインド仏教である。
それを慈悲と訳した古代の中国人は偉大だったと言うしかない。
仏経典というと、どうしてもとっつきにくい感じがある。それは、すべて漢文だからである。
明治以降、中国人の訳したものではなく、サンスクリット語やパ一リ語原典からの直訳が始まった。それも現代口語訳である。
中村元などはその代表的な先駆者だろう。
訳書に極力やさしい言葉を使うことでも知られた。その最も端的な例として、サンスクリットのニルヴァーナ(Nirvāṇa)およびパーリ語のニッバーナ(Nibbāna)がある。
彼は、それを「涅槃(ねはん)」と訳さず「安らぎ」と訳したことはとても有名だ。
読経というものは、ほぼ漢文であるからどちらかというと、呪文的な効果を求めている。魂の波動づたえ、である。意味などどうでもよい。一念を以て岩をも砕きたくば、延々と呪文としての読経や真言(マントラ)を唱え続けるのだ。これを事相という。行といっても良い。
しかし、意味を知るには、やはり現代語への直接訳がなんといっても一番良い。理解するということだ。学ぶといってもよい。これは教相という。
密教ではこの両方が無ければならない。実践と理論である。
その両方の道から、自分の他者の、死者たちの、そして仏たちの「こころ」に迫ろうとしたのが、仏教である。
おそらく、キリスト教でも似たようなものだろう。
仏陀という一人の男が吐いた言葉は、それがほんとうに彼によって吐かれた言葉かどうか、実はだれにもわからない。
経典というもののすべてが、寂滅後、何百年も経ってから書かれたものばかりだからだ。そういう意味では、仏経典のすべては偽経だといってもいい。
しかし、偽経だからといって、ウソなのではない。仏陀が伝えようとした「こころ」に何とか迫ろうとした、必死の努力が経典に結実しているのだから。
『ものごとは、こころにもとづき、こころを主とし、こころによってつくりだされる。もしも、清らかなこころで話したり行ったりするならば、福楽はその人につき従う。影がその体から離れないように。』・・・仏陀、「ダンマパダ(法句経)第1章2
『音に驚かない獅子のように。網にとらえられない風のように。水に汚されない蓮のように・・・ただひとり歩め。』・・・仏陀、「スッタニパータ」第2 10-333
『神も、人も、ものを欲しがり、執着にとらわれている。その執着を捨てよ。』・・・仏陀、「スッタニパータ」第2 14-395
平易な言葉で、ブッダは「こころ」の在り方を説き続けた。「こころ」を求めていけば、その先に世界が広がってくることを、彼は教えた。だから、彼はこう言い残した。
『滅びゆくものを、悲しんではならない。』・・・