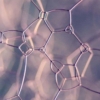青春の一冊~珠玉の掌編

これは65回目。みなさんは青春期に読んだ本で、なにが印象的でしたか。今、あなたは青少年にどんな本を気楽に勧めるでしょうか。ためになる、ということより、あくまで気楽に気持ちよく読めるというものであったら・・・
:::
今回は、短編小説、あるいは掌編の紹介をしてみたい。文豪たちの名作の中から、感動、哀歓、心が洗われる珠玉の短編をいくつかピックアップしてみた。
このところ、竹島や尖閣諸島など領土を巡って国家間で暗闘が繰り広げられている。所詮は無人島の争奪戦だが、それでも昔ならとっくに交戦状態になっていただろう。私自身、感情的になってしまう自分がいることは否定できないが。しかし一方で、どこかこの争いそのものに醜悪なものを感じてしまうのも確かなのだ。その理由は、ある一つの短編を読んだことがあるからである。
フランスにアルフォンス・ドーデという作家がいた。19世紀を生きた人物だ。有名な作品は、『風車小屋便り』という短編集で、とくに南フランスではいまだに深く愛読されている。ドーデには『月曜物語』という短編集もある。その中で教科書にも使われたりするのが『最後の授業』だが、ここで引用するのは、『ベルリン攻囲』という掌編小説である。
ときは、普仏戦争のさなか。ドイツ統一を目指すプロシャ軍と、それを阻もうとするナポレオン三世のフランス軍が激突した。結果は、フランス軍の惨敗に終わり、あろうことかナポレオン三世自身が、プロシャ軍の捕虜になるという大失態を演じてしまった。この結果、プロシャは小国分裂していたドイツを統一し、ドイツ帝国として新たなスタートを切ることになった。
小説は、その戦争の終盤を題材にしている。パリに、ジューヴという老人が住んでいた。バルコニーからは凱旋門が見える。若いころ、ナポレオン一世の時代、ジューヴは誰もが羨む胸甲騎兵(重武装した騎兵)として、「栄光の大陸軍(グランダルメ)」で活躍していた。だが、いまでは死が間近に迫った老人だ。
ジューヴの息子は、フランス軍兵士として前線に赴いている。しかし、「仏軍敗退」の報せが届くと老人はショックで倒れてしまい、そのまま寝たきりになってしまった。回復の見込みのない老人に、次に「勝報」が届くと、たちまち元気になった。しかし、実はこれは嘘だった。
戦場から息子の頼りが届かないので、老人の娘が嘘の手紙をしたため読んで聞かせたのだ。老人は死の床で、(フランス勝利を信じたまま)戦場の息子に返事を書く。
「フランス人であることを決して忘れるな・・・哀れな人たちに寛大であれ。乱暴な侵略をしてはならない・・・そして所有権を尊重せよ。婦人に対して礼儀を守れ。講和の条件としては戦費の賠償のみ・・・他に何も望むな。領土を奪って何を得ることがあろう・・・ドイツをもってフランスは作れないのだから」
これ以上、フランスにとって愛国的な言葉はないだろう。高校生の頃に、初めてこの短編を読んで、はっと目の覚めるような思いがしたことを覚えている。思想的にはかなり右寄りの私だが、以来、このジューヴ老人の「ドイツをもってフランスは作れないのだから」という最後の言葉を忘れたことはない。
こうした政治や戦争という時事的なテーマではなく、もっと個人の生と死の対比を見事に表現した名品もある。横光利一の『春は馬車に乗って』という短編だ。末期の結核を患っている妻と、それを看病する夫との壮絶な日々がつづられている。駄々をこね、暴れ、あきらめ、わずかな幸福感にすがろうとする妻。夫は真正面から向き合い続ける一方で、心身ともに疲れ果てていく。それでも、夫は機械のように尽くし、妻の命が少しでも永らえることに努める。松の葉がどんなに美しく光るかという形容詞を、たった一つ考え出す課題を妻に与え、命の灯をともしつづけさせようとする。
知人から岬をまわって届けられたスイートピーが、春爛漫であることを妻に伝え、その花を抱きしめながら息を引き取っていく最後の場面まで、夫婦の切ない、ときに醜い会話が連綿と続く。そこには高邁な思想も哲学もない。淡々と生と死の記録が綴られているだけだが、読後に何かほっと救われる思いを残してくれる。ラスト部分を引用してみよう。
彼は花粉にまみれた手で花束をささげるように持ちながら、妻の部屋へ入っていった。
「とうとう、春がやって来た」
「まア、綺麗だわね」と妻は云うと、ほほえみながら痩せ衰えた手を花の方へ差し出した。
「これは実に綺麗じゃないか」
「どこから来たの」
「この花は馬車に乗って、海の岸を真っ先きに春を撒(ま)き撒きやって来たのさ」
妻は彼から花束を受けると両手で胸いっぱいに抱きしめた。そうして、彼女はその明るい花束の中へ蒼ざめた顔を埋めると、恍惚(こうこつ)として眼を閉じた。
ちなみに、松田聖子さんの「赤いスイートピー」という歌がある(松本隆作詞)。歌詞の出だしは「春色の汽車に乗って・・・」、歌詞の最後は、「心に春が来た日は赤いスイートピー」である。花の名前といい、歌詞といい、横光利一のこの短編がモチーフなのだろうか。昔から気になっている。余談。
さて芥川龍之介が短編の天才だということは、間違いないだろう。だが、私は好きか嫌いかといったら、あまり好きにはなれない。独りよがりの知性が自己崩壊していく本人の人生そのものを、作品群は余すことなく反映しているからだ。
しかし、その芥川作品の中でもわずかに、心から読んでよかったと思う短編が一つだけある。『蜜柑』(みかん)だ。横須賀から鎌倉方面へ向かう、最初のトンネルを抜けた線路脇あたりがその舞台である。倦怠の中で自滅していく主人公が、列車の中で偶然見かけた、ほんの一瞬の刹那を切り取った短編だ。
取り立ててたいしたストーリーがあるわけではない。それだけにかえって孤独に浸り、「治りたがらない病人」然とした主人公に、瞬間、美しい人生というものを気づかせる。こんな人生でも、「生きている」と喜びを感じさせ、蜜柑の新鮮な色を思い出させてくれるのだ。信じてみたいという思いと、豊饒な人間性を思い出させてくれる短編である。
貧しく、奉公に行かなければならない娘が三等車の切符を持って、主人公のいる二等車に乗り込んでくる。不愉快な思いをする主人公には目もくれない。走り去る汽車を、見送りに来た幼い弟たちが追いかける。娘は窓から、蜜柑を投げ落とす。姉弟たちの間の、斧でも断ち切ることができないような絆が、このわずかな瞬間に閃(ひらめ)く。主人公の心情は、以下のように書かれている。
暮色を帯びた町はずれの踏切りと、小鳥のように声を挙げた三人の子供たちと、そうしてその上に乱落(らんらく)する鮮やかな蜜柑の色と――すべては汽車の窓の外に、瞬(またた)く暇もなく通り過ぎた。が、私の心の上には、切ない程はっきりと、この光景が焼き付つけられた。そうしてそこから、ある得体の知れない朗(ほがらか)な気持ちが湧き上がって来るのを意識した。
遠い地へ離れていく姉への切々たる思いと、弟たちへのわずかばかりの心遣いという、たったワンシーンが、人生に疲れ果てた主人公を生きているこの瞬間に引き戻す。芥川らしからぬ一編だ。彼自身の実体験なのだが、人間というものへの信頼を、一瞬にせよ取り戻したこの感動を、芥川は持ち続けることができずに逝った。その意味でも個人的には、大変心残りの一編である。
昔は、教科書にこの『蜜柑』がよく使われたこともあるそうだが、近年はさっぱりだ。芥川作品というと、『杜子春』『蜘蛛の糸』あたりが定番だが、まだこれらはいいとしても、圧倒的に使われているのは、『羅生門』だそうだ。やはりこの国はどうかしている。この作品は、生きるための「悪」という人間のエゴイズムを克明に描き出した作品である。そういう破滅的な思想を子供たちに教えるなら、まだ『藪の中』のほうがマシではないか。
こうしてみると、やはり名を残す作家というのは、ほんの数頁の小作品でも実にうまい。まったくのところ脱帽だ。ところで、小説というものは、作家の生き様や人となりを知って初めてその意味を解釈すべきなのか。それとも、作者本人とは切り離し、あくまで独立したものとして解釈すべきなのか。今もって、私には答えが見つからない。永遠のテーマではあろうが、読者の皆様はどちらの読み方をされているだろうか。
さて、今回三つほどここでは挙げてみたが、わたし自身が大好きで、青少年にあくまで気楽に、気持ちよく、温かい気持ちになってもらいたいと思えば、シュトルムの『人形つかいのポーレ』を一番最初に挙げるだろう。ここで、敢えて解説しなかったのは、実際に読んでもらいたいからにほかならない。